もっと専門的な知識を知りたいあなたへ。ガチでディープな小児医学に関する知識を解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 愛着障害は脳で何が起きているのか― 発達に与える影響 ―
不適切な養育(マルトリートメント)を背景とする愛着障害では、報酬系や感覚野の脳発達に特徴的な変化が生じることが示されています。本記事では、反応性愛着障害(RAD)の脳科学的知見を整理し、臨床支援への示唆を解説します。
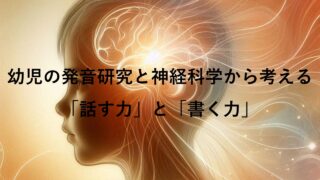 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 幼児の発音研究と神経科学から考える「話す力」と「書く力」
幼児の発音発達は、書字やなぞりの土台と深く結びついています。古典的な日本の発音研究と現代の神経科学をもとに、「話す力」と「書く力」が同時に育つ仕組みを解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 「話す」と「書く」は別じゃない発音とひらがな習得をつなぐ発達のしくみ
子どもの発音と書字は、脳内で同じ運動ネットワークを共有しています。ひらがなやなぞり書きが難しくなる理由を、医学・発達神経科学の知見からやさしく解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 サ行が気になる子どもの発音言える言葉から育てる、やさしい練習語
子どものサ行がタ行になってしまう理由を、舌の動きと音の並びから解説。発音しやすい言葉の特徴、段階別の練習語、家庭や療育で使える実践リストをまとめました。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 子どもの発音の言い間違いは、成長の途中?― サ行が言えない理由
子どもの「さ」が「ち」になるのはなぜ?発音の言い間違いは成長の途中のサインかもしれません。研究をもとに、子どもの発音が育つしくみをやさしく解説します。
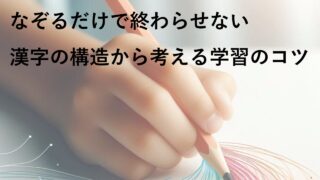 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 なぞるだけで終わらせない 漢字の構造から考える学習のコツ
常用漢字2136字の分析研究をもとに、漢字学習となぞり書きの関係を解説。構成要素・筆順・動作の視点から、書字が苦手な子への支援を考えます。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ひらがなは運動だった|研究からわかる「なぞり書き」の本当の役割
ひらがながうまく書けないのは練習不足ではありません。研究をもとに、手の発達と文字学習の関係、なぞり書き練習の本当の意味をやさしく解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ASD と統合失調症 — 「皮膚感覚」「表情認知」「社会的脳ネットワーク」のちがい
自閉症スペクトラム(ASD)と統合失調症は、一見似て見える部分もありますが、脳の働き方や感覚の受け取り方はまったく異なります。本記事では、触覚(皮膚感覚)、表情認知、社会的脳ネットワークの研究をもとに、科学的にわかりやすく解説します。
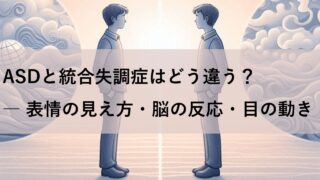 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ASDと統合失調症はどう違う?― 表情の見え方・脳の反応・目の動き
自閉症スペクトラム(ASD)と統合失調症は“似た”社会的困難を示すことがあります。本記事では、表情を見たときの脳活動(fMRI)と眼球運動検査の研究結果をもとに、両者の共通点と決定的な違いをわかりやすく解説します。臨床的な意義と日常での気づきも紹介。
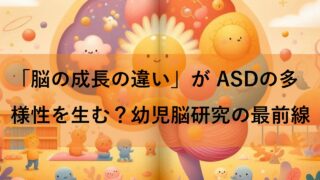 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 「脳の成長の違い」が ASDの多様性を生む?幼児脳研究の最前線
幼児期の自閉スペクトラム症(ASD)に見られる脳の特徴は?世界的にも希少な幼児用MEG研究から見えてきた感覚・運動・社会性の違いと、診断応用の難しさをわかりやすく解説します。
