もっと専門的な知識を知りたいあなたへ。ガチでディープな小児医学に関する知識を解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 「話す」と「書く」は別じゃない発音とひらがな習得をつなぐ発達のしくみ
子どもの発音と書字は、脳内で同じ運動ネットワークを共有しています。ひらがなやなぞり書きが難しくなる理由を、医学・発達神経科学の知見からやさしく解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 サ行が気になる子どもの発音言える言葉から育てる、やさしい練習語
子どものサ行がタ行になってしまう理由を、舌の動きと音の並びから解説。発音しやすい言葉の特徴、段階別の練習語、家庭や療育で使える実践リストをまとめました。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 子どもの発音の言い間違いは、成長の途中?― サ行が言えない理由
子どもの「さ」が「ち」になるのはなぜ?発音の言い間違いは成長の途中のサインかもしれません。研究をもとに、子どもの発音が育つしくみをやさしく解説します。
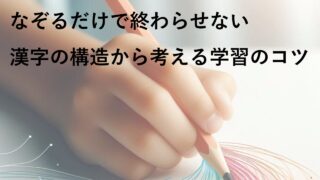 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 なぞるだけで終わらせない 漢字の構造から考える学習のコツ
常用漢字2136字の分析研究をもとに、漢字学習となぞり書きの関係を解説。構成要素・筆順・動作の視点から、書字が苦手な子への支援を考えます。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ひらがなは運動だった|研究からわかる「なぞり書き」の本当の役割
ひらがながうまく書けないのは練習不足ではありません。研究をもとに、手の発達と文字学習の関係、なぞり書き練習の本当の意味をやさしく解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ASD と統合失調症 — 「皮膚感覚」「表情認知」「社会的脳ネットワーク」のちがい
自閉症スペクトラム(ASD)と統合失調症は、一見似て見える部分もありますが、脳の働き方や感覚の受け取り方はまったく異なります。本記事では、触覚(皮膚感覚)、表情認知、社会的脳ネットワークの研究をもとに、科学的にわかりやすく解説します。
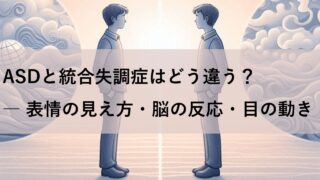 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ASDと統合失調症はどう違う?― 表情の見え方・脳の反応・目の動き
自閉症スペクトラム(ASD)と統合失調症は“似た”社会的困難を示すことがあります。本記事では、表情を見たときの脳活動(fMRI)と眼球運動検査の研究結果をもとに、両者の共通点と決定的な違いをわかりやすく解説します。臨床的な意義と日常での気づきも紹介。
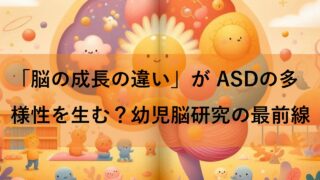 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 「脳の成長の違い」が ASDの多様性を生む?幼児脳研究の最前線
幼児期の自閉スペクトラム症(ASD)に見られる脳の特徴は?世界的にも希少な幼児用MEG研究から見えてきた感覚・運動・社会性の違いと、診断応用の難しさをわかりやすく解説します。
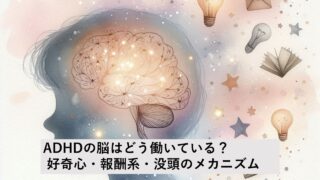 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ADHDの脳はどう働いている? 好奇心・報酬系・没頭のメカニズム
近年、ADHDは単なる「不注意の障害」ではなく、好奇心・新奇性追求・発散的思考・ハイパーフォーカスといった創造性の源泉をもつ“別チューニングの脳”として注目されています。本記事では、神経科学・進化心理学・行動研究の知見から、ADHDの特性がどのように創造性を生み出すのかをわかりやすく解説し、教育や職場で活かすための具体的なヒントも紹介します。
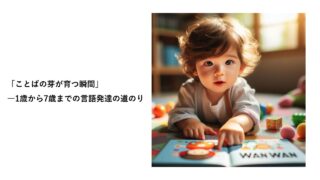 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 「ことばの芽が育つ瞬間」――1歳から7歳までの言語発達の道のり
1歳から7歳までの言葉の発達を月齢別に解説。脳の発達や家庭でできる関わり方を専門家の視点で紹介します。
親子の会話が「ことばの力」を育てるヒントが満載です。
