「うちの子、言葉がちょっと遅いのかな…」
「絵本も読んでるけど、なかなか言葉が増えなくて不安です」
乳幼児を育てるなかで、こうした心配を感じたことはありませんか?
実は、子どもの言葉の発達には、「脳の可塑性(neuroplasticity)」と呼ばれる、とても重要な仕組みが関わっています。
人の脳は、生まれた瞬間からすでに完成しているわけではなく、経験によってつくられていく臓器です。特に0~3歳ごろまでは、脳が驚くほど柔軟で、外からの刺激――とくに「ことば」が、神経回路の発達に大きな影響を与えます。
この記事では、「なぜ乳幼児期の語りかけがそれほど大事なのか?」を、脳科学の視点からわかりやすく解説していきます。
あなたの毎日の声かけが、子どもの未来の語彙力と心の土台になる――
神経可塑性とは何か?
人の脳は、生まれたときには未熟な状態であり、外からの経験によって大きく変化していく性質を持っています。この「変化できる性質」のことを、**神経可塑性(neuroplasticity)**と呼びます。
● 神経可塑性とは?
神経可塑性とは、脳の神経細胞(ニューロン)やそのつながり(シナプス)が、経験や学習、環境に応じて変化・再編成される能力のことです。
これは一生を通じて続きますが、特に乳幼児期には非常に高い柔軟性を持っています(Huttenlocher, 2002)。
🔍【用語注釈】
ニューロン:脳内の情報をやりとりする細胞(神経細胞)
シナプス:ニューロン同士のつなぎ目。情報をやりとりする接合部
新しいことを覚えるとき、脳内では神経細胞同士のつながりが強化されたり、逆に使われない回路は弱まったりします。これを「シナプスの可塑性」と呼びます。
シナプスの強化・弱化は、「使うことで強くなり、使わないと消えていく」特徴を持ち、まるで筋肉のように働くのです。
● シナプスの形成と刈り込み(pruning)
乳幼児期には、シナプスの数が爆発的に増えます。たとえば、生後2〜3歳の子どもの大脳皮質のシナプス数は、大人よりも1.5倍ほど多いことが知られています(Huttenlocher & Dabholkar, 1997)。
🔍【用語注釈】
大脳皮質:記憶、思考、言語など高次機能をつかさどる脳の外側部分
シナプス・プルーニング(synaptic pruning):あまり使われないシナプスが自然に減少する過程
この大量のシナプスは、後に「刈り込み(pruning)」によって整理されます。つまり、頻繁に使われる神経回路だけが残され、使われない回路は自然と消えていくのです。
この「選別」が行われることで、脳はより効率的に情報を処理できるようになります。
● 経験が脳の構造をつくる
つまり、どんな経験をするかによって、子どもの脳の“配線図”が変わっていくということです。
これは音楽や運動、情緒的なやりとりにも当てはまりますが、**「ことばの入力」**は特に強く影響します。
たとえば、親や保育者からの語りかけが多い環境では、言語処理に関わる脳のネットワークがより発達することが研究で示されています(Romeo et al., 2018)。
文献
Huttenlocher, P. R. (2002). Neural plasticity: The effects of environment on the development of the cerebral cortex. Harvard University Press.
Huttenlocher, P. R., & Dabholkar, A. S. (1997). Regional differences in synaptogenesis in human cerebral cortex. Journal of Comparative Neurology, 387(2), 167–178.
Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700–710.
乳幼児期は“黄金期”
子どもの脳は、生まれた瞬間からめざましいスピードで成長を続けています。特に0〜3歳の時期は、神経回路の発達が爆発的に進むことから、「脳の黄金期」とも呼ばれます。
● シナプスの増加はピークを迎える
前のセクションでも触れたように、脳内で神経細胞同士が情報をやりとりする接点「シナプス」は、生後まもなく急速に増え始めます。
たとえば視覚や聴覚のシステムは生後数ヶ月から1歳前後でピークを迎えますが、**言語や社会性に関わる領域(前頭葉や側頭葉)**のシナプスは、2〜3歳ごろに最も多くなります(Huttenlocher & Dabholkar, 1997)。
🔍【用語注釈】
前頭葉:判断力、計画、感情の制御などを担う脳の前方部位
側頭葉:言語理解や聴覚情報の処理に関わる脳の側面の部位
この時期のシナプスは、生まれ持った設計図(遺伝情報)だけでは完成しません。外からの刺激、とくに「意味のあることば」が与えられることで、回路が強化されるのです。
● 経験が脳の構造に直接影響する
近年の脳科学では、「子どもがどんな経験をするか」が、その子の脳の構造や機能に直接影響することが明らかになっています(Kolb & Gibb, 2011)。
特に重要なのが、「質の高い言語入力(語りかけ)」です。
一方的な音声やテレビよりも、人との対話的なやりとりのほうが、脳の言語ネットワークを活性化させることが示されています(Romeo et al., 2018)。
🔍【用語注釈】
言語ネットワーク:言語の理解や発話に関わる複数の脳領域(例:ブローカ野、ウェルニッケ野など)の連携システム
このようなやりとりは、単なる語彙力の向上だけでなく、社会性や感情の調整力にも良い影響を与えることが報告されています(Shonkoff & Phillips, 2000)。
● 「あとで取り返せばいい」は通用しない?
神経可塑性は一生続くとはいえ、0〜3歳の時期は特に“感受性”が高い時期です。これは「臨界期(critical period)」または「感受性期(sensitive period)」とも呼ばれ、この時期に受けた刺激の影響は、その後の発達に長く残ると考えられています。
もちろん、何歳になっても学習は可能です。しかし、後から取り戻すには、より多くの時間と支援が必要になることが研究からも示唆されています(Knudsen, 2004)。
文献
Huttenlocher, P. R., & Dabholkar, A. S. (1997). Regional differences in synaptogenesis in human cerebral cortex. Journal of Comparative Neurology, 387(2), 167–178.
Kolb, B., & Gibb, R. (2011). Brain plasticity and behaviour in the developing brain. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20(4), 265–276.
Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700–710.
Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. National Academy Press.
Knudsen, E. I. (2004). Sensitive periods in the development of the brain and behavior. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(8), 1412–1425.
言語入力の質と量が脳を変える
「ことばがけは大事」とよく言われますが、ではどのような言語入力が、子どもの脳にとって本当に意味があるのでしょうか?
最近の研究では、量だけでなく「質」の高いことばのやりとりが、子どもの言語発達と脳の働きに深く関係していることが明らかになってきました。
● 単なる「語数」ではなく「やりとり」が重要
1980年代に行われた有名な研究(Hart & Risley, 1995)では、家庭での語りかけの量が子どもの語彙力に大きく影響することが報告されました。
この研究では、3歳までに家庭によって語彙数に3,000万語の差があることが示され、「30ミリオン・ワード・ギャップ」として知られています。
🔍【用語注釈】
語彙力:言葉を理解し、使う力のこと。読み・聞き・話し言葉の基盤になる。
しかしその後の研究では、「語数」以上に、子どもとの間で交わされる“対話的なやりとり”の質が、言語発達と脳活動に強く関係していることが分かってきました(Romeo et al., 2018)。
● 「意味のある語りかけ」は脳を刺激する
Romeoら(2018)の研究では、4〜6歳の子どもに装着型レコーダーをつけて家庭での会話を記録し、脳のfMRI(機能的MRI)と組み合わせて解析しました。
結果、親子でのやりとり(ターン・テイキング)が多い子どもほど、左側頭葉の言語処理領域が強く活性化していることが示されました。
🔍【用語注釈】
ターン・テイキング:会話で「話す→返す→話す」と交互にやりとりすること。言語発達に不可欠。
左側頭葉:言語理解(ウェルニッケ野)などをつかさどる脳領域。
これは、子どもが「話しかけられるだけ」よりも、「返事をしてもらう」「共感される」「質問される」などのやりとりの方が、脳の神経回路をより強く刺激するということを意味しています。
● テレビやYouTubeでは代わりにならない理由
「ことばをたくさん聞かせたい」と思って、子どもにテレビ番組や動画を見せる方も多いかもしれません。
もちろん教育番組も価値はありますが、一方的な音声刺激は、双方向の対話とは異なり、脳の言語ネットワークの発達にあまり効果がないことが報告されています(Linebarger & Walker, 2005)。
特に2歳以下の子どもは、実際の人とのやりとりを通してしか、ことばの意味を深く学ぶことができないとされています(AAP, 2016)。
● 「ことばのシャワー」ではなく「ことばのキャッチボール」
ことばの発達において大切なのは、単に大量の音を浴びせるのではなく、「キャッチボール」のようなやりとりを重ねることです。
例えば、
- 子どもが指をさしたものに対して「これ見てたの?ワンワンだね!」
- 子どもが何か言葉にならない音を発したときに「そうなんだ、楽しいね」と返す
こうしたやりとりが、**子どもの脳にとってもっとも意味のある“学習の瞬間”**となります。
文献
Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700–710.
Linebarger, D. L., & Walker, D. (2005). Infants’ and toddlers’ television viewing and language outcomes. American Behavioral Scientist, 48(5), 624–645.
American Academy of Pediatrics (AAP). (2016). Media and Young Minds. Pediatrics, 138(5), e20162591.
親や支援者にできること
乳幼児期の脳は、「ことばのやりとり」によって大きく育ちます。
では、親や保育士、支援者は日々のなかでどんな関わりを意識すればよいのでしょうか?
ここでは、科学的に効果が示されている実践的なポイントをご紹介します。
● 「正しく話す」より「気持ちに応える」
ことばの数を増やしたいと思うと、「この単語を教えなきゃ」「正しい文法を使わせなきゃ」と思いがちです。
しかし、幼い子どもにとってもっと大事なのは、「気持ちをくみ取ってもらえた」という経験です。
たとえば、子どもが「あっ!」「ワン!」と叫んだら、「ほんとだ、ワンワンいたね!」と意味をくみ取って返すことで、安心感とことばの学習が同時に起こるとされています(Snow, 1999)。
🔍【用語注釈】
応答的養育(responsive parenting):子どもの発信にすぐ気づき、気持ちをくみ取って反応する育児スタイル。情緒や認知の発達を促す。
● 絵本の読み聞かせは“対話型”が効果的
読み聞かせは語彙の発達に非常に有効です。ただし、ただ読むだけでなく、**子どもとやりとりしながら読む「対話型読み聞かせ」**が特に効果的とされています。
たとえば、
- 絵を指さして「これなにかな?」と問いかける
- 子どもが答えたら「そうだね、これはバナナだね」と返す
- 子どもが興味を持っていそうな場面で少し立ち止まって話す
このように**子どもの反応に合わせた“間”と“返し”**を入れることで、脳の言語処理ネットワークがより活性化することが研究で示されています(Whitehurst et al., 1988)。
● 具体的で、感情をともなった語りかけを
「ことば」は、目に見えない抽象的な情報です。そのため、特に小さな子には、五感や感情に結びついた語りかけが脳への刺激になります。
例:
- 「わあ、冷たいお水だね〜」
- 「おいしいね、にこにこになっちゃう」
- 「トラック、どーんって音がしたね。びっくりした?」
こうしたやりとりは、言語野だけでなく感情や記憶をつかさどる脳領域も同時に活性化させ、ことばの理解と定着をうながします(Hirsh-Pasek et al., 2015)。
🔍【用語注釈】
感覚統合(sensory integration):複数の感覚情報を脳内でまとめて処理し、行動やことばに結びつける働き。
● 忙しい毎日でもできる、小さな工夫
日常のなかで実践できる小さな工夫には、以下のようなものがあります:
- オムツ替えのときに「足をぴょんってしたね〜」と実況
- ごはんの時間に「今日はごはんとおみそ汁だよ」など目の前のことを言語化
- 公園で「風がびゅーってきたね!寒いね!」と感覚を言葉にのせる
- 買い物中に「りんごさん、こんにちは」とものに声をかける
どれも、意識して語彙を教えこむ必要はありません。
「見て、感じたこと」をそのまま言葉にするだけで、子どもにとっては十分な学びになります。
文献
Snow, C. E. (1999). Social perspectives on the emergence of language. In T. B. Brazelton & S. I. Greenspan (Eds.), The irreducible needs of children: What every child must have to grow, learn, and flourish (pp. 91–105). Perseus Publishing.
Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-Menchaca, M. C., & Caulfield, M. (1988). Accelerating language development through picture book reading. Developmental Psychology, 24(4), 552–559.
Hirsh-Pasek, K., Adamson, L. B., Bakeman, R., Owen, M. T., Golinkoff, R. M., Pace, A., … & Suma, K. (2015). The contribution of early communication quality to low-income children’s language success. Psychological Science, 26(7), 1071–1083.
まとめ
「ことばをどう育てればいいのか?」
その答えは、特別な教材や訓練だけではありません。
毎日のちょっとした語りかけ、目を合わせた笑顔、
子どもと一緒に驚いたり、笑ったりすること――
それこそが、脳の神経回路を育て、語彙力の土台を築いているのです。
私たちの脳は、生まれた瞬間から完成しているわけではありません。
特に0〜3歳のあいだは、経験によって構造そのものがつくられていく時期です。
この時期に「どれだけ多く、どれだけ意味のあることばを受け取ったか」が、
その後の学びや人との関係づくりにもつながっていきます。
けれども、
「忙しくて話しかける余裕がない日もある」
「他の子と比べて不安になる」
――そんなふうに感じることも、きっとありますよね。
でも大丈夫。
ことばの発達は、“いま”この瞬間からでも変わっていく力を持っています。
脳には可塑性があり、そしてあなたには、子どもの世界を豊かにする声があります。
たった一言の「たのしかったね」
小さな「みてみて、すごいね!」
それらが、子どもの中に確かに積み重なり、語彙となり、思考となり、人生をかたちづくっていきます。
完璧な親も、完璧な語りかけも必要ありません。
大切なのは、「あなたと一緒に言葉を交わす時間」が、子どもにとっての宝物になるということ。
今日からまた、声をかけてみましょう。
あなたのその声が、きっと子どもの脳を、そして未来を、あたたかく育んでいきます。

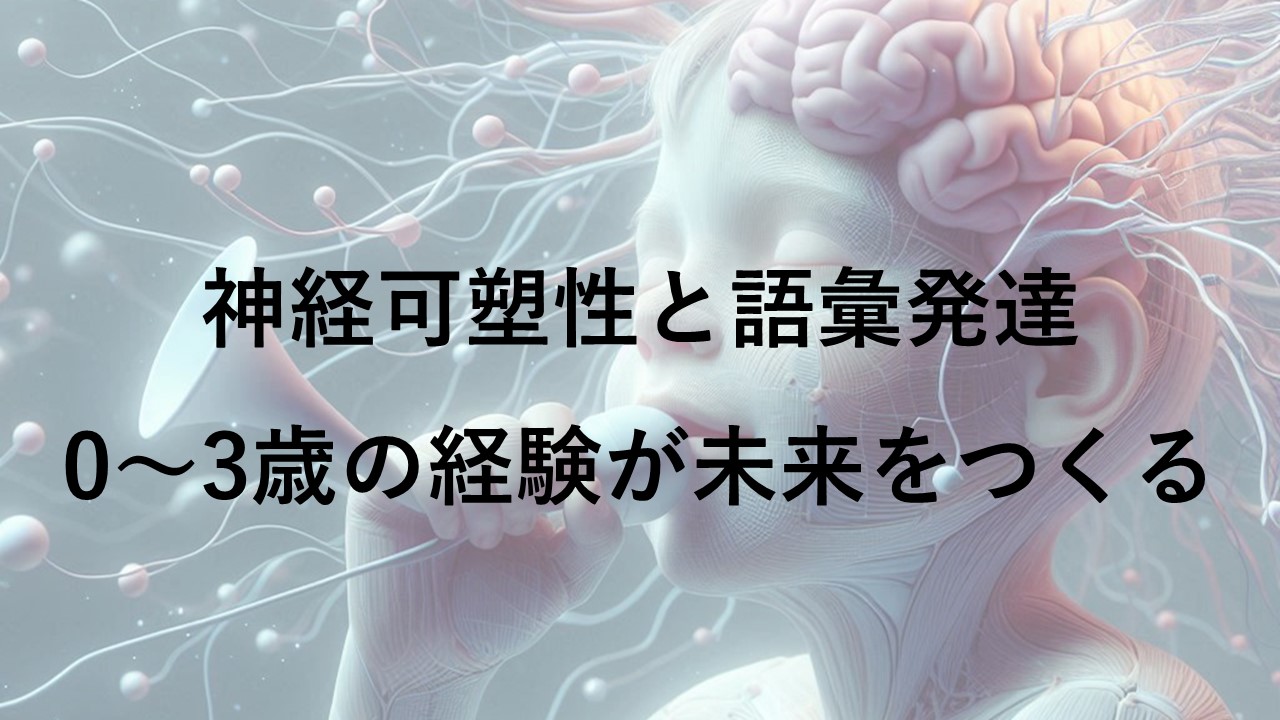


コメント