感情ラベリングとは何か

感情ラベリングの定義
「感情ラベリング(affect labeling)」とは、感じている気持ちを「ことば」で表すことを指します。
たとえば、子どもが走って遊んでいるときに「楽しいね」と言葉を添えること。あるいは、大人自身が「少し緊張しているな」と自分の感情を言語化することも感情ラベリングにあたります。
このように、感情ラベリングは「感情をただ感じる」だけでなく、「ことばで整理して認識する」プロセスを含みます。
脳科学的な背景
感情ラベリングには、脳の働きが大きく関わっています。
- 扁桃体(amygdala):不安や恐怖などの強い感情を素早くキャッチして体を反応させる場所。
- 前頭前野(prefrontal cortex):感情をコントロールしたり、理性的に判断したりする場所。
研究によると、感情を言葉にすると、扁桃体の過剰な活動が落ち着き、前頭前野の活動が高まることが分かっています。
つまり、「言葉で表す」という行為そのものが、脳内で“ブレーキ”の役割を果たし、気持ちを落ち着けるのです。
感情を言葉にすると情動が落ち着く
心理学者マシュー・リーバーマンら(Lieberman et al., 2007)の有名な研究があります。
被験者に「怒った顔」や「恐怖の顔」の写真を見せたとき、扁桃体が強く反応しました。
しかし、その顔の感情を言葉で「怒り」「恐れ」とラベリングすると、扁桃体の反応が弱まり、前頭前野の活動が高まったのです。
この研究は、単に「感じる」だけでなく「言葉にする」ことが、感情をコントロールする上で非常に効果的であることを示しました。
まとめ
感情ラベリングとは、心の中の気持ちを「言葉にして確認する」こと。
脳の仕組みから見ても、言葉にするだけで強い感情の高ぶりがやわらぎ、気持ちが整理されることが分かっています。
子どもの場合、自分の気持ちをうまく言葉にできないことが多いため、大人が代わりに「楽しいね」「ちょっとびっくりしたね」と感情を言い当てることが、心の安定につながります。
参考文献
Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science, 18(5), 421–428.
Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 9(5), 242–249.
なぜ「大人がラベリングする」ことが重要なのか
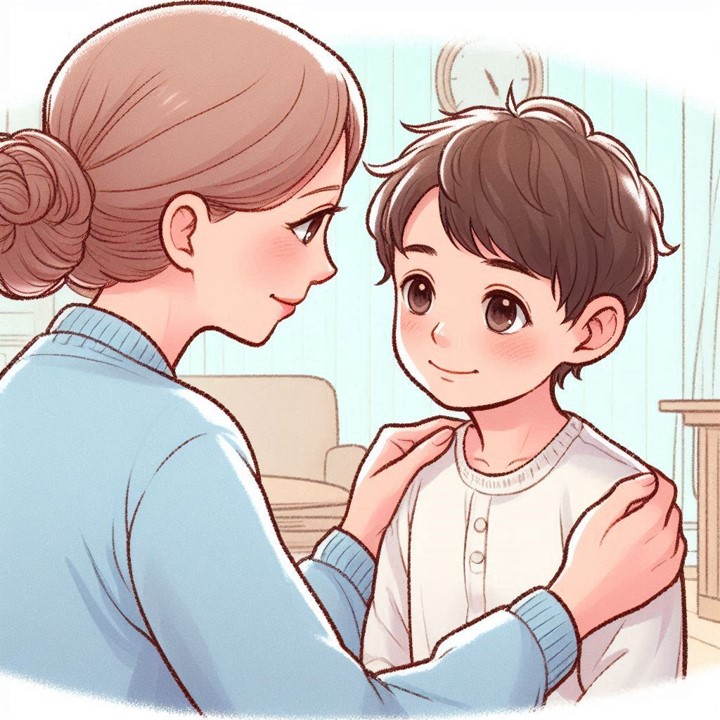
子どもはまだ感情をうまく言葉にできない
子どもは成長の過程で少しずつ感情語(「うれしい」「かなしい」「くやしい」など)を学んでいきますが、幼児期にはまだその語彙が十分ではありません。
実際、研究によると2歳前後でようやく「うれしい」「いや」といった基本的な感情表現を使い始め、学齢期までに少しずつ複雑な感情(「がっかり」「恥ずかしい」など)が理解されていきます(Ridgeway et al., 1985)。
つまり、小さな子どもに「どう感じてる?」と質問しても、言葉で正確に返すことは難しいのです。
大人が「代わりに言葉にする」ことで学習が起こる
では、どうやって子どもは感情と言葉を結びつけていくのでしょうか?
鍵になるのは、大人が子どもの気持ちを代わりに言葉にすることです。
- 子どもが楽しそうに遊んでいるとき → 「楽しいね!」
- 転んで泣いているとき → 「びっくりしたね。痛かったね」
このように、大人が状況に合わせて感情を言葉にしてあげると、子どもは「この気持ちは“楽しい”って言うんだ」「こういうときは“痛い”って表すんだ」と少しずつ学んでいきます。
心理学的には、これは「モデリング(建設的なお手本を示すこと)」と呼ばれる学習の仕組みです。
共同注意と社会的学習
発達心理学者マイケル・トマセロ(Tomasello, 1999)は、子どもがことばや社会的スキルを学ぶうえで「共同注意(joint attention)」が重要だと指摘しています。
共同注意とは、親と子が同じ対象に注意を向けて、その状況を共有すること。
たとえば、親子で犬を見て「わんわんだね!」と確認するような場面です。
感情ラベリングも同じです。
子どもが体験している感情に大人が目を向け、「今は楽しいんだね」「少しこわかったね」と言葉を添えることで、感情とことばが「共同注意」の中でリンクされていきます。
研究知見からの裏づけ
- Tomasello (1999) は、子どもが社会的スキルを獲得する過程で、他者の言語化や行動を模倣しながら発達していくことを強調しました。
- Denham et al. (2003) は、親が子どもの感情に言葉を添えること(emotion talk)が、子どもの感情理解や自己調整能力の発達に有意に関連することを示しました。
- Cole et al. (2004) も、幼児期の感情語の習得がその後の社会的適応や対人関係に影響することを報告しています。
まとめ
子どもは「自分の気持ちを自分の言葉で説明する」のがまだ難しい時期にいます。
だからこそ、大人が「今の気持ちはこういう名前なんだよ」と代わりに言葉を添えてあげることが大切です。
これは、単にことばを教えるだけでなく、
- 自分の気持ちを理解できるようになる力(自己理解)
- 相手の気持ちに気づく力(共感性)
- 感情を落ち着かせる力(情動調整)
を育てる基盤にもなります。
参考文献
Tomasello, M. (1999). The cultural origins of human cognition. Harvard University Press.
Denham, S. A., Zoller, D., & Couchoud, E. A. (2003). Socialization of preschoolers’ emotion understanding. Developmental Psychology, 30(6), 928–936.
Cole, P. M., Armstrong, L. M., & Pemberton, C. K. (2004). The role of language in the development of emotion regulation. Child Development, 75(2), 317–333.
Ridgeway, D., Waters, E., & Kuczaj, S. A. (1985). Acquisition of emotion-descriptive language: Receptive and productive vocabulary norms for ages 18 months to 6 years. Developmental Psychology, 21(5), 901–908.
ポジティブ感情に焦点を当てる意義

ネガティブ感情ラベリングの効果
これまでの研究では、主に「ネガティブ感情」に対するラベリングの効果が注目されてきました。
たとえば「こわいね」「おこってるんだね」と感情を言葉にすると、脳の扁桃体の過剰な反応がおさまり、不安や怒りが落ち着くことが分かっています(Lieberman et al., 2007)。
つまり、ネガティブ感情のラベリングは「気持ちを整理して鎮める」働きを持っているのです。
ポジティブ感情ラベリングの大切さ
一方で、日常生活の多くはポジティブな体験で満ちています。絵を描いたり、砂遊びをしたり、料理を一緒に作ったり…。こうしたときに「楽しいね」「うれしいね」「気持ちいいね」と大人が言葉を添えることが、子どもの心の発達にとても重要です。
なぜなら、ポジティブ感情を言葉で確認することは、
- 自己肯定感を育てる
- 安心感や信頼感を深める
- 「よい体験」を記憶に残りやすくする
といった効果を持つからです。
子どもにとって「楽しい」という言葉は、楽しい気持ちそのものを言語化するだけでなく、「自分は大切な存在だ」と感じる心の栄養にもなります。
ポジティブ心理学の視点
ポジティブ心理学者バーバラ・フレドリクソン(Fredrickson, 2001)は、ポジティブ感情が「心の拡張と構築(broaden-and-build)」をもたらすと提唱しました。
- 心を拡張する:喜びや安心感は、新しいことに挑戦したり、人と関わったりする意欲を高める
- 資源を構築する:ポジティブな経験は、レジリエンス(困難を乗り越える力)や社会的つながりを強める
この理論によると、ポジティブ感情を意識的に積み重ねることが、長期的に心の健康や人間関係の質を高めることにつながります。
実生活での応用
たとえば、子どもと工作をしているときに「カラフルで楽しいね!」と声をかけたり、散歩中に「風が気持ちいいね」と共感する。
こうしたちょっとした言葉の積み重ねが、子どもに「安心できる環境」「一緒に楽しめる関係」を感じさせ、自己肯定感を高めます。
特に発達に課題を抱える子どもは、不安や失敗体験が多くなりがちです。だからこそ、大人が積極的にポジティブな感情を言葉にして共有することが、支援の柱となります。
まとめ
ネガティブな気持ちを言葉にすることは、気持ちを落ち着けるのに役立ちます。
でも、それだけでなく「楽しいね」「うれしいね」とポジティブな気持ちをラベリングすることは、子どもの心を育てる栄養になります。
ポジティブな言葉を重ねることは、子どもの「安心・自己肯定感・挑戦する力」を育てる最もシンプルで効果的な方法なのです。
参考文献
Lieberman, M. D., et al. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science, 18(5), 421–428.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218–226.
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320–333.
並行活動と感情ラベリングの相性

並行活動とは?
「並行活動(parallel activity)」とは、大人と子どもが同じ空間で同じ活動をしながら、互いに向かい合うよりも横並びで自然に関わるスタイルのことを指します。
たとえば、
- 一緒に絵を描く
- 工作をする
- お菓子を作る
- ガーデニングをする
といった活動です。
このような「並行活動」には、大人と直接向き合うよりも子どもが安心して関われるという特徴があります(Roth & Worthington, 2015)。
並行活動の心理的効果
- 安心感が生まれる
子どもは正面から「どうしたの?」「今どんな気持ち?」と聞かれると緊張しやすいですが、並行活動の中ではプレッシャーが少なく、自然に心を開きやすくなります。 - リラックス効果
絵や料理のように手を動かす活動そのものが、気持ちを落ち着ける効果を持っています(Ulrich, 1991:自然や創作活動によるストレス低減研究)。 - 自然な感情共有が起こる
活動中の「楽しいね」「いい香りだね」といった言葉かけは、強制的な問いかけではなく、活動の流れの中で自然に感情を言語化できます。
感情ラベリングとの相性
並行活動は、感情ラベリングと非常に相性が良いとされています。
- 子どもは大人からの問いかけに答えるよりも、「言い当てられる」方が安心しやすい
- 大人も、活動を通して観察した子どもの表情やしぐさから感情をラベリングしやすい
- 活動中に交わされたポジティブな言葉は、その活動の記憶と一緒に残りやすい(Conway & Pleydell-Pearce, 2000:自伝的記憶の研究)
たとえば、料理のときに「いい香りだね」「ふわふわして楽しいね」と声をかけると、子どもにとって「料理=楽しく安心できる体験」として記憶に残りやすくなります。
実践例
- 絵画活動:「きれいな色だね」「夢中になって描いてるね、楽しそう!」
- 工作:「工夫して作ってるね」「ワクワクするね」
- 料理:「いい音がしてるね」「一緒にやると楽しいね」
このような小さな言葉かけが、子どものポジティブな経験を「感情+言葉」の形で定着させ、自己肯定感や安心感を育てることにつながります。
まとめ
「一緒に絵を描く」「料理をする」といった横並びの活動は、子どもが安心して心を開きやすい場になります。
その中で「楽しいね」「いい香りだね」と大人が感情を言葉にしてあげると、子どもは自然に感情と言葉を結びつけて学んでいきます。
つまり、並行活動は「感情ラベリングを実践するのに最適な舞台」なのです。
参考文献
Roth, J. L., & Worthington, E. L. (2015). The role of parallel activity in building rapport with children. Journal of Child and Family Studies, 24(6), 1802–1810.
Ulrich, R. S. (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research. Journal of Health Care Interior Design, 3(1), 97–109.
Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychological Review, 107(2), 261–288.
家庭や支援現場での活用法

日常生活でできるシンプルな実践
感情ラベリングは特別な教材や訓練を必要としません。むしろ、日常のささやかな場面にこそ取り入れやすいものです。
- 散歩中に:「気持ちいい風だね」「お花の色、きれいだね」
- 食事のときに:「おいしいね」「あったかくてほっとするね」
- 遊びの中で:「楽しいね」「ワクワクするね」
研究でも、親が日常会話の中で感情を言葉にする頻度が多いほど、子どもの感情理解や社会的スキルが高まることが報告されています(Denham et al., 1994; Taumoepeau & Ruffman, 2006)。
支援現場での工夫
発達支援や教育現場では、感情ラベリングを活動と組み合わせる工夫が有効です。
- 感覚統合遊びの中で:「ふわふわして気持ちいいね」「ぐるぐる回って楽しいね」
- 絵本の読み聞かせで:「この子はうれしそうだね」「ちょっと悲しそうだね」
- 集団活動での共有:「みんなでやると楽しいね」「協力できてうれしいね」
このように、子どもが五感を使った遊びやストーリー体験をしているときに大人が感情を言葉にすると、学習効果が高まります。
実際、社会情動的支援プログラム(Social Emotional Learning; SEL)の研究でも、活動体験+感情言語化が子どもの情動調整力を育てることが示されています(Durlak et al., 2011)。
注意点:子どもにプレッシャーを与えない
感情ラベリングは「子どもに答えさせる」ことではありません。
「どう感じる?」と問いかけられると、言葉が未発達な子どもは困惑したり、答えなければならないというプレッシャーを感じてしまうことがあります。
むしろ大切なのは、大人が先にことばで橋渡しをする姿勢です。
子どもは大人の言葉を聞きながら「そうか、これが“楽しい”ってことなんだ」と学んでいきます。
心理学者ヴィゴツキー(Vygotsky, 1978)が提唱した「最近接発達領域(ZPD)」の理論によると、子どもは大人や仲間のサポートを通じて、自分一人では難しいスキルを少しずつ身につけていきます。感情ラベリングもまさにその一例で、大人の言葉が子どもの感情理解の「足場(scaffolding)」になるのです。
まとめ
感情ラベリングは、家庭でも支援現場でも「日常のちょっとした声かけ」から始められる支援です。
- 散歩中に「気持ちいい風だね」
- 遊びの中で「楽しいね」
- 絵本を読みながら「うれしそうだね」
こうした声かけは、子どもに無理に答えさせる必要はありません。
大人が「気持ちに名前をつけてあげる」こと自体が、子どもの心を育てる大切なサポートになります。
参考文献
Denham, S. A., Zoller, D., & Couchoud, E. A. (1994). Socialization of preschoolers’ emotion understanding. Developmental Psychology, 30(6), 928–936.
Taumoepeau, M., & Ruffman, T. (2006). Mother and infant talk about mental states relates to desire language and emotion understanding. Child Development, 77(2), 465–481.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405–432.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
まとめ
感情ラベリングとは、子どもの気持ちを大人が言葉にしてあげることです。
研究によれば、感情を言語化することで脳の過剰な反応が落ち着き(Lieberman et al., 2007)、同時にことばと感情を結びつける学習にもつながります。
特にポジティブ感情のラベリング――「楽しいね」「うれしいね」「気持ちいいね」といった声かけ――は、
- 子どもの心の安定
- 自己理解の促進
- 自己肯定感やレジリエンス(回復力)の基盤づくり
に大きな役割を果たします(Fredrickson, 2001)。
さらに感情ラベリングは、家庭や学校、支援現場で手軽に取り入れられる方法です。
- 散歩中に「風が気持ちいいね」と伝える
- 絵本を読みながら「この子はうれしそうだね」と言い添える
- 一緒に遊びながら「楽しいね」と共有する
このような日常のちょっとした声かけが、子どもの情動調整力や感情理解を自然に育んでいきます。
大切なのは、子どもに「どう感じる?」と問い詰めるのではなく、大人が先にことばの橋渡しをする姿勢です。
それが、子どもの「心のことば」を育てる一番シンプルで確かな方法なのです。

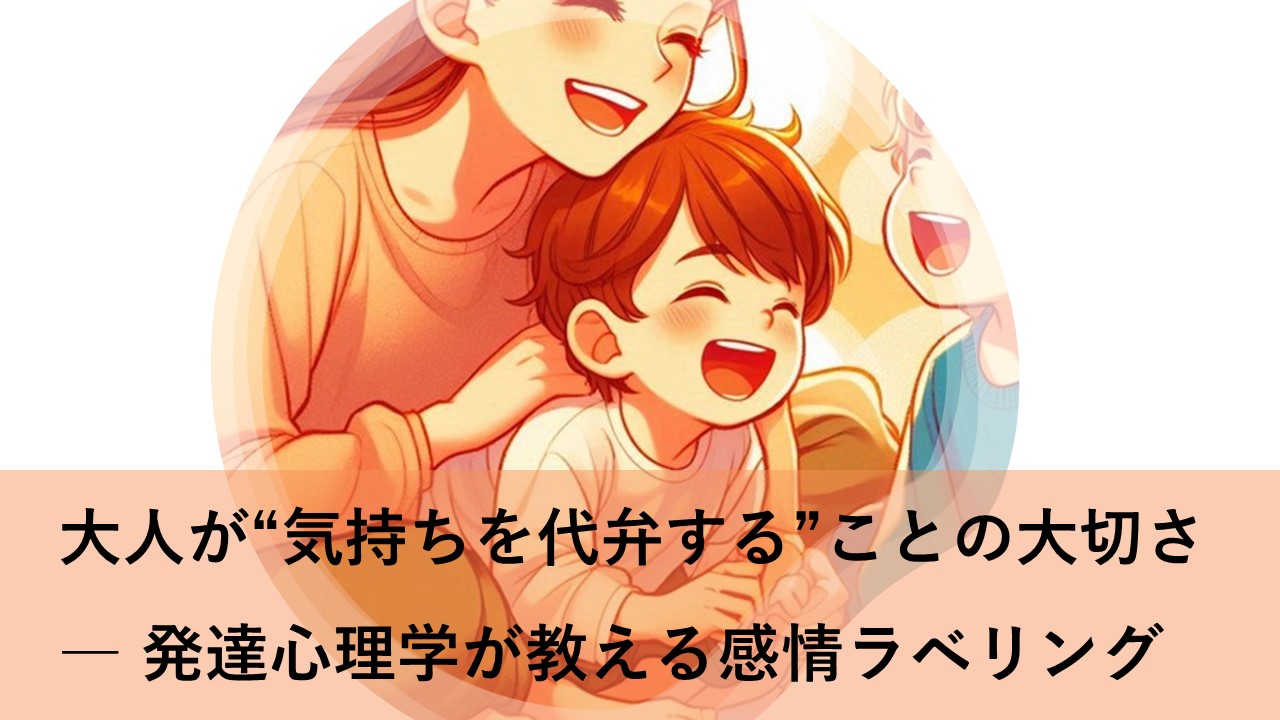

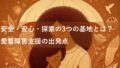
コメント