字を覚えるのに時間がかかる。
文字を読んだり、書字の練習以外にも効果的な練習方法はないだろうか?
この記事では、より効果的に文字を学習する方法として「なぞり読み」と、その効果にもとづいた知育カードを解説します。
これを読めば鉛筆で字を書くだけでない、違った練習方法のヒントになるでしょう。
特に後半の脳の仕組みは専門職向け。リハビリの専門職に知ってほしい脳科学の内容です。
「なぞり読み」とは字を指でなぞる読み方のこと

文字を読むとき、多くの人は目で見て理解します。しかし、「なぞり読み」とは、指で文字をなぞりながら読む方法を指します。
「失読」という読めない障害
この方法が特に注目されるのは、「失読」という障害を持つ人々においてです。失読とは、脳の損傷などによって文字を認識しづらくなる状態を指し、自分で書いた文字さえ読めなくなることもあります。しかし、不思議なことに、指で文字の形をなぞると読めることがあるのです。
これは、脳が文字を認識する際に、視覚だけでなく触覚などの他の感覚も活用できることを示しています。実際、文字の読み書きには前頭葉や側頭葉、頭頂葉など複数の脳領域が関わっており、それらがネットワークを形成して情報を処理しています。研究によると、文字を指でなぞることで、触覚や運動感覚を司る脳の領域が活性化し、それが視覚情報の処理を助ける可能性があると考えられています(Rapp & Caramazza, 1997)。
つまり、「なぞり読み」は、脳のもつ柔軟な情報処理の仕組みを活かした読み方のひとつなのです。文字を読むのが難しい人にとって、この方法がサポートになるかもしれません。
指でなぞるリハビリのあれこれ

この文字を指でなぞるという方法は、わたし自身もリハビリの中で行います。ボンドで文字をなぞって凹凸をつけたり、粘土で文字を作って触ってもらったり。
触覚を活用した方法
- サンドペーパー文字
- サンドペーパーで作った文字を指でなぞることで、独特のざらざらした感触が刺激になります。
- モールや毛糸で文字を作る
- 柔らかくて立体感のある素材を使うことで、指先の感覚を強化できます。
- ジェルやスライムの上で文字をなぞる
- ジップロックにジェルやスライムを入れて、その上から文字をなぞることで、視覚と触覚の両方を活用できます。
- 布やフェルトで文字を作る
- 布やフェルトを切り抜いて文字を作ると、異なる素材の感触を楽しみながら学習できます。
運動を取り入れた方法
- 空中で指や腕を使って文字を書く
- 大きな動きを取り入れることで、体の動きを通じて記憶に残りやすくなります。
- タブレットやスマホの触覚フィードバック機能を活用する
- 振動などのフィードバックを利用して、デジタル環境でも触覚の刺激を与えることができます。
- 砂やお米の上に文字を書く
- 指先で砂やお米をなぞることで、感触を楽しみながら学習できます。
- 磁石を使った文字トレース
- 磁石シートの上に鉄粉や磁石の粒を置き、ペン型の磁石でなぞると、視覚と触覚の両方を刺激できます。
これらの方法を組み合わせることで、より多様な感覚を活用しながらリハビリを進められると思います!
指でなぞって楽しく学べる!「ゆびなぞりカード ひらがな」
ひらがなの学習がうまく進まない…そんなお悩みはありませんか?
手作りもよいですが、実はこんな知育教材があるのです。
ゆびなぞりカードひらがな
KUMON(公文)
「ゆびなぞりカード ひらがな」は、指でなぞるだけで文字の形を自然に覚えられる知育教材です。
触って学ぶ!「ゆびなぞりカード ひらがな」の科学的メリット
「ゆびなぞりカード ひらがな」は、カードの表面に凹凸があり、指でなぞることでひらがなの形を覚えられる知育教材です。この触覚を活用した学習法は、脳科学的にも効果があることがわかっています。
🧠 視覚 × 触覚 × 運動で脳を刺激!
ひらがなを学ぶ際、目で形をとらえたあとに指でなぞることで、視覚情報と運動感覚が脳内で統合されます(James & Engelhardt, 2012)。さらに、文字の凹凸に触れることで指先の触覚も刺激され、形の認識がより強固になります。
✍️「書く前の準備」として最適
従来の鉛筆を使った文字学習では、視覚と運動の協調が未発達なお子さまにとって負担になることがあります。しかし、「ゆびなぞりカード」なら、鉛筆を使う前に、指の動きと文字の形を直接結びつけることができます。研究では、手指を使った感覚的な学習が、後の筆記能力向上に寄与することが示されています(Longcamp et al., 2005)。
🎯 触って覚えることで記憶に残りやすい
触覚を利用した学習は、単なる視覚的な学習よりも長期記憶に残りやすいとされています(Kiefer & Trumpp, 2012)。そのため、「ゆびなぞりカード」で形を覚えた後に鉛筆で書く練習をすると、スムーズに学習を進められます。
「目で見て、指でなぞって、しっかり定着!」
遊びながら学べる「ゆびなぞりカード ひらがな」で、お子さまの文字学習を楽しくサポートしましょう!
ゆびなぞりカードひらがな
KUMON(公文)
脳の働きを活かした「ゆびなぞり学習」のしくみ
ここからは、「なぞり読み」の脳の伝達経路についてお話します。
*用語の言い換えが難しいため、専門用語が含まれます。
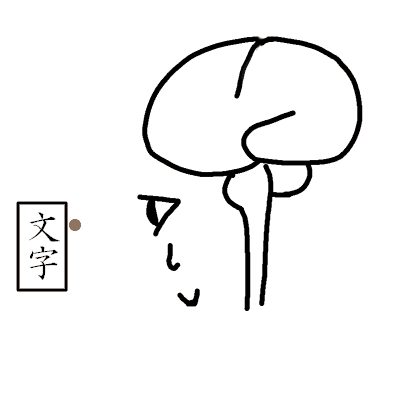
イメージしやすいように、アニメーションにしました。
ひらがなを覚えるとき、ただ目で見るだけでなく、指でなぞることで学習効果が高まることが分かっています。この方法は、脳の複数の領域を同時に活性化し、記憶に残りやすくするからです。ここでは、脳の仕組みを4つのステップに分けて解説します。
① 文字を目で見る(視覚野)
最初に、ひらがなの形を「目で見る」ことで、視覚情報が脳の後方にある**「第一次視覚野」**(後頭葉)に送られます。視覚野は、目から入った情報を処理し、形や線の違いを認識する重要な領域です(Grill-Spector & Malach, 2004)。
② 見た情報を手の運動に置き換える(運動前野・頭頂葉)
次に、目で見たひらがなの形の情報が、運動に関わる脳の領域へ送られます。特に、頭頂葉にある**「運動感覚変換領域」**が、視覚情報を手の動きへ変換する役割を担います(Andersen & Buneo, 2002)。
つまり、「この形にそって指を動かそう」と、脳がイメージする段階です。
③ 指の運動が生まれる(運動野・運動前野)
運動のイメージができたら、次に「指を動かす」命令が脳の**「運動野」や「運動前野」**(前頭葉)から出されます。
この指令が筋肉に伝わることで、実際に指が動き、ひらがなの形をなぞる動作が生まれます(Graziano, 2016)。
④ 指からの触覚が脳に戻ってくる(体性感覚野)
指が文字をなぞると、指先の皮膚が凹凸を感じ、その情報が脳に戻ります。この触覚情報は、頭頂葉にある**「体性感覚野」**に送られ、どんな感触だったかを脳が認識します(Kaas, 1993)。
さらに、この触覚情報と視覚・運動情報が統合されることで、「この形の文字をこうやって動かして書く」という理解が強化されるのです(James & Engelhardt, 2012)。
なぜ「ゆびなぞり学習」が効果的なのか?
このように、「見る」「指を動かす」「触る」という複数の感覚を同時に使うことで、脳の複数の領域が活性化し、ひらがなの形をより強く記憶できます。
研究によると、単に視覚だけを使った学習よりも、手を動かしたり触覚を使う学習のほうが、長期的な記憶に残りやすいことが示されています(Longcamp et al., 2005)。
感覚と運動がつながる仕組み ー「感覚情報と運動覚情報のマッチング」
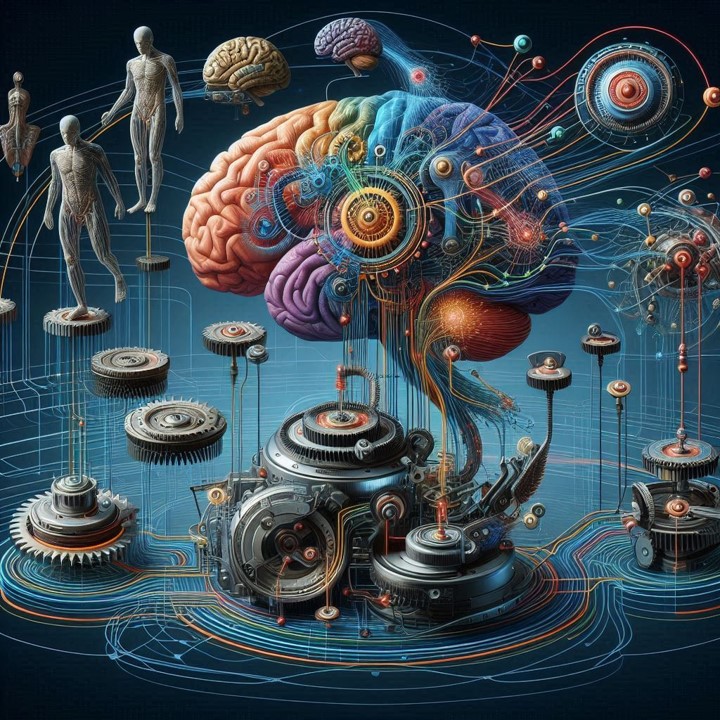
ひらがなを指でなぞると、「触る」という感覚情報と「指を動かす」という運動覚情報が脳内で統合されます。この仕組みは、私たちがスムーズに字を書いたり、道具を使ったりするためにとても重要な働きをしています。
🧠 ① 感覚の情報が脳に届く(体性感覚野)
指で文字をなぞると、皮膚の凹凸を感じる「触覚」や、関節や筋肉の動きを感じる「固有感覚(運動覚)」が生まれます。これらの感覚情報は、頭頂葉にある**「体性感覚野」**に送られ、脳が「どんな形を触ったか」を認識します(Kaas, 1993)。
✍️ ② 感覚情報と運動覚情報が統合される(頭頂葉・小脳・運動前野)
次に、受け取った感覚情報は、運動の記憶を蓄えている脳の領域(頭頂葉や小脳)に向かい、運動覚情報とマッチングされます(Miall & Wolpert, 1996)。
つまり、「この触覚=この文字の形」「この指の動き=この形を書く動作」といった情報のつながりが脳内で整理されるのです。
🎯 ③ 感覚と運動のつながりが強化される(感覚運動統合)
繰り返し文字をなぞることで、触覚と運動覚の統合がスムーズになり、最終的には「見た瞬間に手がスムーズに動く」ようになります。これは、運動前野や頭頂葉のネットワークが強化されることで起こります(James & Engelhardt, 2012)。
例えば、自転車に乗る練習をしたとき、最初は「ペダルを踏む」「バランスを取る」などを意識していたのに、何度も練習するうちに無意識でできるようになるのと同じです。
触った感覚が「文字」と「意味」に変わる仕組み
ひらがなを指でなぞると、指先の触覚や動きの情報が脳へと送られ、最終的に「この文字は〇〇という意味だ」と理解できるようになります。
これは、触覚情報が脳の「文字を認識する領域」と「意味を理解する領域」へと伝わっていくからです。
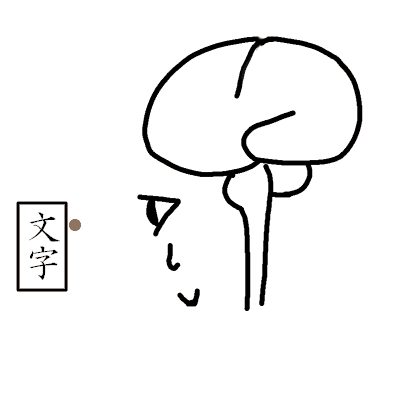
🧠 ① 触覚情報が脳に届く(体性感覚野)
指でひらがなをなぞると、皮膚や筋肉の感覚情報が頭頂葉の**「体性感覚野」**に送られます。ここで、「何かを触った」「なぞった形はこうだった」という情報が処理されます(Kaas, 1993)。
🔡 ② 触った情報が「文字」として認識される(視覚語形領域)
体性感覚野からの情報は、後頭葉・側頭葉の**「視覚語形領域(Visual Word Form Area, VWFA)」**へと伝わります。この領域は、文字の形を認識し、単語を区別する働きをします(Dehaene et al., 2005)。
通常、私たちは「目で見た文字」をこの領域で処理しますが、触覚や運動の情報からも文字を認識できることが研究で分かっています(Siok et al., 2009)。つまり、視覚だけでなく、触覚を使っても「これは ‘あ’ だな」と脳が認識できるのです。
💡 ③ 文字の意味が理解される(側頭葉・前頭葉)
視覚語形領域で「これは ‘あ’ という文字だ」と識別された情報は、さらに側頭葉や前頭葉の「意味情報」を蓄える領域へと伝わります。
ここでは、**「この文字はどういう意味か」「他の言葉とどうつながるか」**といった処理が行われます(Binder et al., 2009)。
つまり、指でなぞった感覚が、最終的に「言葉の意味の理解」へとつながっていくのです。
まとめ
✅触覚や運動を使うことで、視覚だけよりも深く文字の形を記憶できる
✅ 触った情報が視覚語形領域に伝わるため、文字を認識する力が高まる
✅ 文字の認識だけでなく、意味の理解にもつながる
このように、「目で見る」「指でなぞる」「触覚で感じる」という複数の感覚を組み合わせることで、ひらがなの学習がよりスムーズになります(James & Engelhardt, 2012)。
「ゆびなぞりカード ひらがな」は、この脳の仕組みを活かした教材です。お子さんの「文字の形を覚える力」だけでなく、「意味を理解する力」も自然に育てていくことができます。
ぜひ、ひらがなの学習に取り入れてみてください!
ゆびなぞりカードひらがな
KUMON(公文)
引用文献
・岩田誠(1992). 神経文字学の確立にむけて. 安西祐一郎 ら( 編 )認 知科 学 ハン ドブ ック. 共立 出版,pp.393-401
・櫻井 靖久:読み書き障害の 2 重回路説の進展. 神経心理学 34;2-8, 2018
・櫻井 靖久:コミュニケーション障がいとしての読み書き障害. 神経心理学 37;81-87, 2021

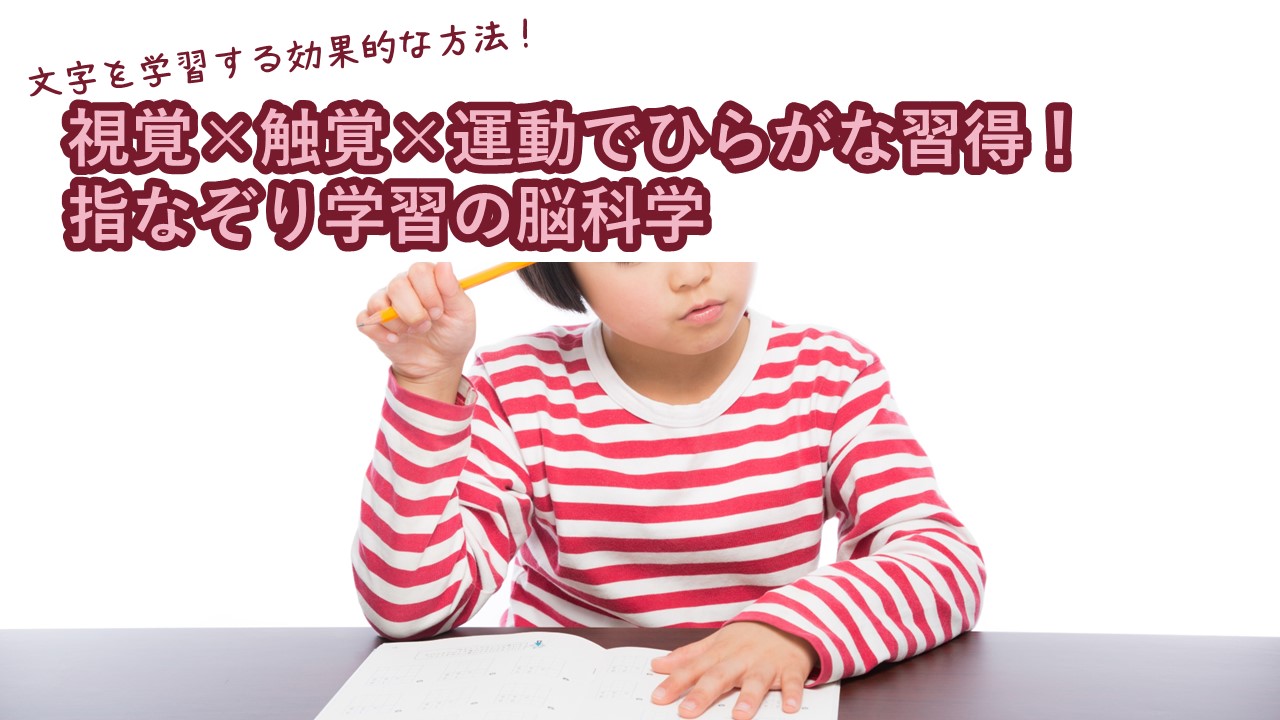
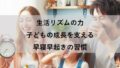
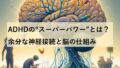
コメント