ゲームが好き。
今の子どもたちにとって、それは当たり前のことです。
だけど──
・ゲーム時間がどんどん増えている
・ちょっとしたことでイライラする
・言葉づかいが荒くなった
そんな変化、あなたは感じたことはありませんか?
最新の研究で、デジタルゲーム依存と「怒りやすさ」「攻撃性」の関係が明らかになりました。
今回は、その内容を詳しくご紹介します。
デジタルゲームと怒りや攻撃性の関係を調べる研究

最近、スマホやゲーム機で長時間ゲームをする子どもたちが増えていますよね。
「ゲームばかりしていると、怒りっぽくなるのでは?」と心配する声もよく聞かれます。
今回ご紹介する研究では、デジタルゲームに夢中になりすぎる(=ゲーム依存症)ことが、10代の若者たちの怒りや攻撃的な気持ちにどんな影響を与えているのかを詳しく調べました。
つまり、「ゲームにハマりすぎると性格や気持ちに変化が出るのか?」という、とても身近で大切なテーマについて研究したのです。
どんな方法で調べたの?

この研究では、10代の若者たちを対象に調査を行いました。
たくさんの若者にアンケートに答えてもらい、「ゲームにどれくらい依存しているか」や「どれくらい怒りっぽいか、攻撃的な傾向があるか」についてデータを集めました。
使ったアンケートには、例えばこんなものがあります。
- 生活背景をたずねる質問(年齢、性別、家族のこと、など)
- ゲーム依存度を測る質問(どれくらいゲームにのめり込んでいるか)
- 攻撃性を測る質問(怒りやすさや攻撃的な行動について)
集めたデータは、専門的な統計の方法(グループ同士の違いを比べたり、関係を探ったりする方法)を使って、しっかり分析されました。
調査でわかったことは?

この研究から、いくつか大事なことがわかりました。
まず、若者たちのゲームへの依存や、怒りやすさ・攻撃的な傾向は、平均すると中くらいのレベルでした。
また、若者たちが一番よくプレイしていたのは、戦争ゲームで、全体の**約3人に1人(35%)**が戦争ゲームを選んでいました。
さらに詳しく見ると、
- 男性
- 中〜高めの収入の家庭に育った人
- 1日に8時間以上ゲームをしている人
- 毎日欠かさずゲームをしている人
こういったグループは、ゲーム依存の度合いが特に高いことがわかりました。
また、ゲームへの依存が強い人ほど、
怒りっぽくなったり、攻撃的な行動をとりやすくなる傾向があることも確認されました。
そして、特にゲーム依存を強める要素としては、
- 男性であること
- 収入が高い家庭にいること(ただし、この影響は少し弱め)
- ゲームを長時間続けてプレイすること
- 毎日ゲームを欠かさずすること
これらが関係していることが統計的に示されました。
大人が早めに気づくことが大切

ゲームが好きなのは、子どもたちにとって自然なことです。
でも、もしこんな変化が見えたら──ちょっと気をつけたほうがいいかもしれません。
たとえば、
- 「もう寝る時間だよ」と言っても、何度も「あと5分!」を繰り返す
- 朝起きるのがつらくなり、学校に遅刻しがち
- 家族との会話が減り、ゲームばかりに集中している
- ゲームの中で負けると、すぐに怒ったり物に当たる
こんなサインがいくつか重なってきたら、ゲームへの依存が進んでいる可能性も。
でもここで大切なのは、いきなり叱ったり、ゲームを取り上げたりしないこと。
「最近疲れてない?」「なんか困ってることある?」と、子どもの気持ちに寄り添う声かけから始めましょう。
最初はそっけない返事でも、繰り返し気にかけていくことで、子どもたちも少しずつ心を開いてくれます。
看護師さんや学校の先生もサポート役に
子どもたちは、家庭だけでなく、学校という社会の中でもいろんなストレスを抱えています。
そこで重要なのが、学校の先生や看護師さんたちの存在です。
たとえば、保健室にやってくる子どもが
- 「お腹が痛い」と頻繁に訴える
- なんとなく元気がない
- スマホを手放せない様子が見える
そんなとき、単なる体調不良だけでなく、ゲームやネットに頼りすぎているサインかもしれない、と気づく目が必要です。
さらに、先生たちができるサポートとしては、
- 授業の中で「ゲームとの上手な付き合い方」をテーマに話す
- 保護者向けに「ゲーム依存に気をつけましょう」という情報を伝える
など、予防のための働きかけもとても大切になってきます。
学校と家庭がつながってサポートできると、子どもたちも「自分のことを本当に心配してくれてるんだ」と感じることができます。
家庭でもできることがある
家庭でできることも、たくさんあります。
いちばん大事なのは、ルールを押し付けないこと。
子どもと一緒に、こんなふうに話し合ってみましょう。
親:「ゲームは楽しいよね。でも、やりすぎると体も心も疲れちゃうみたいだよ。どうしたらいいと思う?」
子:「うーん、30分くらいでやめるとか?」
親:「30分ならいいね!でも、おもしろいときは時間オーバーしちゃうかも。じゃあ、オーバーしたらどうする?」
こんなふうに、子ども自身がルールを考える流れを作っていくと、納得感が全然違ってきます。
また、ゲーム以外の楽しみを一緒に見つけるのも効果的です。
たとえば、
- 近所の公園に一緒にサッカーをしに行く
- プラモデルやお菓子作りなど、家でできる趣味にチャレンジする
- 友だちと一緒にボードゲーム大会を開く
「楽しい!」という経験をゲーム以外でも積み重ねることで、自然とゲームだけに頼らない生活ができるようになります。
よくあるQ&A
Q. 子どもがゲームばかりしていても、すぐに「依存症」だと決めつけないほうがいいですか?
A. はい、まずは冷静に様子を見ましょう。
ゲームに夢中になる時期は、誰にでもあるものです。ただ、「怒りっぽくなった」「生活リズムが崩れた」など、日常生活に支障が出てきた場合は、注意が必要です。子どもを責めるのではなく、まずはやさしく話を聞くところから始めましょう。
Q. 親が「ゲームの時間を減らして」と言っても、全然聞いてくれません。どうすれば?
A. 一方的にルールを押しつけるのではなく、子どもと一緒にルール作りをしましょう。
たとえば「一日どれくらいならいいと思う?」と子どもに考えさせたり、「オーバーしそうなときはどうする?」と、対策も一緒に決めていくことが大事です。子どもが自分で決めたルールなら、守ろうとする意識も高まります。
Q. 学校の先生や看護師さんは、どんな場面で子どものゲーム依存に気づけますか?
A. 体調不良や、学校生活でのちょっとした変化がヒントになります。
たとえば、「授業中にボーっとしている」「スマホが手放せない」「昼夜逆転気味」など、小さなサインを見逃さないことが大切です。学校と家庭で情報を共有しながら、早めにサポートにつなげるのが理想です。
Q. 家でゲーム以外の楽しみを見つけるには、どうすればいい?
A. 親子で一緒に新しい体験をするのがおすすめです。
たとえば、週末に公園で体を動かしたり、家でボードゲーム大会を開いたり、簡単な料理やDIYに挑戦してみるのもいいですね。「ゲーム以外にも楽しいことがある!」と子ども自身が感じることが大切です。
最後にわかったこと(まとめ)
この研究から、こんな結論が出ました。
デジタルゲームに依存しすぎると、若者は怒りっぽくなったり、攻撃的な行動をしやすくなる可能性がある、ということです。
つまり、ゲームを長時間やりすぎることで、心のバランスが崩れてしまうことがある、ということですね。
そのため、特に医療や学校などで若者にかかわる人たち、たとえば看護師さんたちは、
「この子はゲームにハマりすぎてないかな?」と早めに気づいてあげることがとても大切だとされています。
早めに気づいてサポートすることで、怒りっぽくなるのを防いだり、心の健康を守ることができるんです。
引用文献
Akbaş, E., & Işleyen, E. K. (2024). The effect of digital game addiction on aggression and anger levels in adolescents: A cross-sectional study. Archives of Psychiatric Nursing, 52, 106–112. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2024.06.022



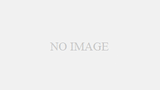
コメント