「あともう少し…!」
「次のレベルまであと少しだから…!」
気づけば、ゲームをする時間がどんどん伸びてしまうことはありませんか?
「やめようと思っていたのに、ついつい続けてしまう」—— そんな経験、子どもだけでなく、大人でもあるのではないでしょうか。
特に、最近ではスマホやゲーム機で手軽に遊べる時代。子どもが「もっとやりたい!」と主張し、大人が「そろそろやめようね」と言ってもなかなかやめられない…そんなやりとりが日常になっている家庭も多いでしょう。
「ゲームばかりやっていて大丈夫?」
「もしかして依存症なのでは?」
そんな不安を感じている方もいるかもしれません。
実は、ゲームをやめられなくなるのには 「脳の仕組み」 が関係しています。
今回は、なぜゲームがやめられないのか? 依存にならないためにどうすればいいのか? を、脳科学の視点からわかりやすく解説していきます。
ゲーム依存症とはなにか?

ゲーム依存症とは、ビデオゲームに過度に没頭し、日常生活や学業、人間関係に深刻な影響を及ぼす状態を指します。世界保健機関(WHO)は2018年にこれを「ゲーム障害」として国際疾病分類(ICD-11)に正式に追加し、精神疾患の一つとして位置づけました。
診断基準として、WHOは以下の3つの特徴を挙げています:
- ゲーム行動の制御が困難:ゲームの開始や終了、頻度、継続時間などを自分でコントロールできない状態。
- ゲームを最優先する:他の生活上の関心事や日常活動よりもゲームを優先させる。
- 否定的な結果が生じても続ける:ゲームによって生活上の重大な問題が発生しても、プレイを続けたりエスカレートさせたりする。
これらの行動パターンが12か月以上続く場合、ゲーム障害と診断される可能性があります。ただし、症状が重篤な場合は、12か月未満でも診断されることがあります。
セルフチェックしてみよう
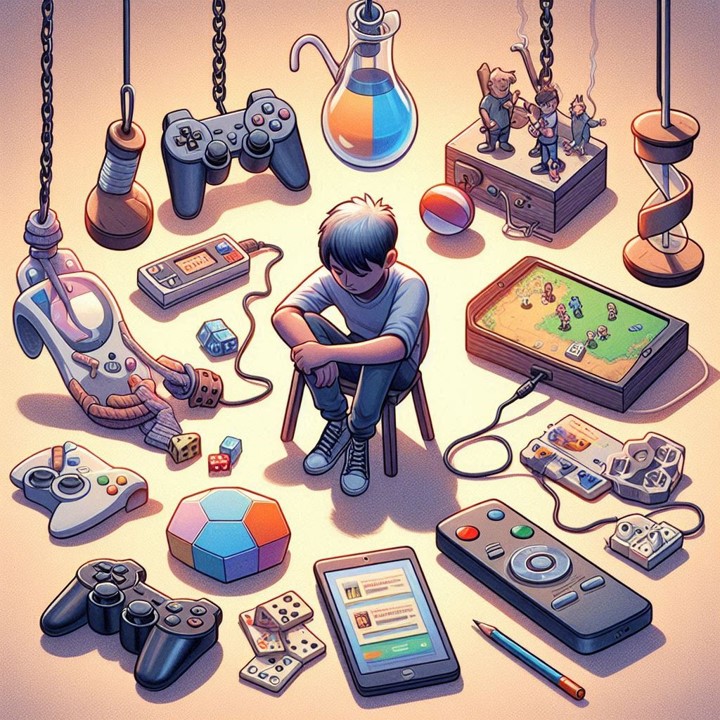
ゲーム依存症セルフチェック(簡易版)
| 質問項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| カテゴリー① ゲーム行動の制御が困難 (コントロールできない) | ||
| 1. ゲームの開始や終了を自分で決めるのが難しいと感じることがありますか? | ☐ | ☐ |
| 2. 「今日は短時間だけ」と決めても、つい長時間プレイしてしまうことがありますか? | ☐ | ☐ |
| 3. ゲームをしていると、周囲の声が聞こえなくなったり、他の予定を忘れたりすることがありますか? | ☐ | ☐ |
| カテゴリー② ゲームを最優先する (他のことよりゲームを優先してしまう) | ||
| 4. 学校や仕事、家族との時間よりもゲームを優先することが増えましたか? | ☐ | ☐ |
| 5. 食事や睡眠を犠牲にしてでもゲームを続けることがありますか? | ☐ | ☐ |
| 6. ゲームをするために、大事な約束をキャンセルしたり遅刻したりすることがありますか? | ☐ | ☐ |
| カテゴリー③ ゲームによる悪影響があっても続けてしまう | ||
| 7. ゲームのせいで、成績や仕事のパフォーマンスが低下したと感じることがありますか? | ☐ | ☐ |
| 8. 家族や友人に「ゲームのしすぎだ」と指摘されたことがありますか? | ☐ | ☐ |
| 9. ゲームをやめようとしたり、制限しようとしたときに、イライラや不安を感じることがありますか? | ☐ | ☐ |
結果の見方
- 「はい」が1~3個 → 依存傾向は低め。ただし、ゲームの影響が強くならないよう注意。
- 「はい」が4~6個 → ゲームへの依存傾向が見られます。プレイ時間を見直し、バランスの取れた生活を意識しましょう。
- 「はい」が7個以上 → ゲーム依存症の可能性が高いです。専門家(精神科医やカウンセラー)に相談することをおすすめします。
ゲーム依存症の症状が、脳の『報酬処理』の仕組みと関係しているのではないか?
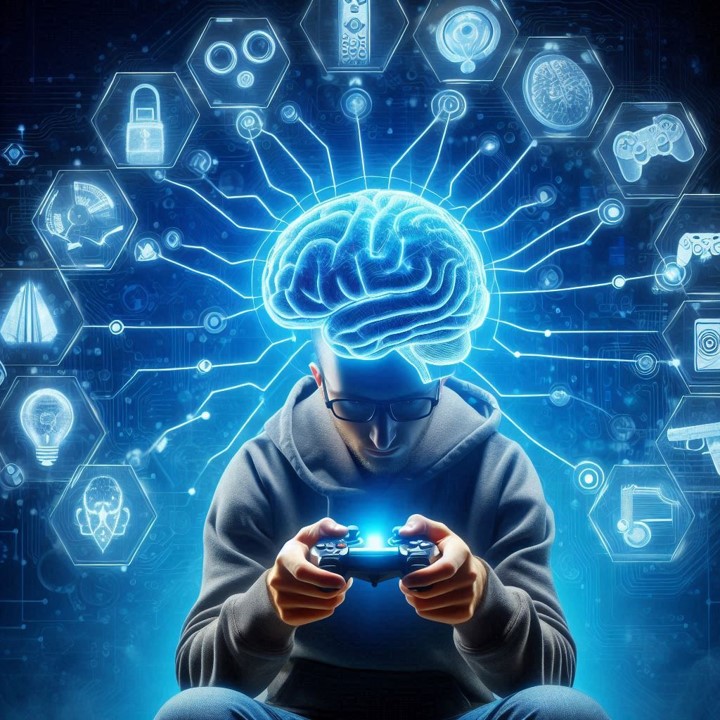
この研究では、「ゲーム依存症の症状が、脳の『報酬処理』の仕組みと関係しているのではないか?」という疑問を検証しました。
報酬処理とは? 〜「ご褒美」を感じる脳のしくみ〜
「報酬処理」とは、 「これをすると、良いことがありそう!」と期待したり、実際にご褒美(報酬)をもらったときに脳が反応するしくみ のことです。
報酬処理の身近な例
例えば、こんな経験はありませんか?
✔ お菓子をもらえると分かるとワクワクする
✔ ゲームで勝つと嬉しくなり、また挑戦したくなる
✔ SNSで「いいね!」がつくと、もっと投稿したくなる
これらはすべて「報酬処理」が関わっている行動です。
脳のどこが働くの?
報酬処理に重要なのが 「尾状核(びじょうかく)」 という脳の部分です。
尾状核は、 「この行動をすると良いことがある!」 という学習を助ける役割を持っています。
さらに、「ドーパミン」と呼ばれる神経伝達物質が関与しています。
ドーパミンが分泌されると、 「嬉しい!」「楽しい!」 という気持ちが生まれ、また同じ行動をしたくなります。
報酬処理の仕組みを簡単にまとめると…
1️⃣ 何か良いことがありそう!(期待)
2️⃣ 実際にご褒美がもらえる!(達成)
3️⃣ 脳が「これをやると良いことがある」と学習する
4️⃣ また同じ行動を繰り返したくなる
報酬処理が影響すること
- 学習やモチベーション
→ うまく活用すると、勉強や仕事のやる気がUP! - ゲームやSNSのハマりやすさ
→ 繰り返しやりたくなる仕組みがある - 依存症との関係
→ 依存症の人は、報酬処理が過剰に働くことがある
報酬処理は、 楽しみややる気を生み出す大切な仕組み ですが、時には依存を引き起こす原因にもなります。
「ゲーム依存」と脳の報酬処理の関係を調べた研究とは?
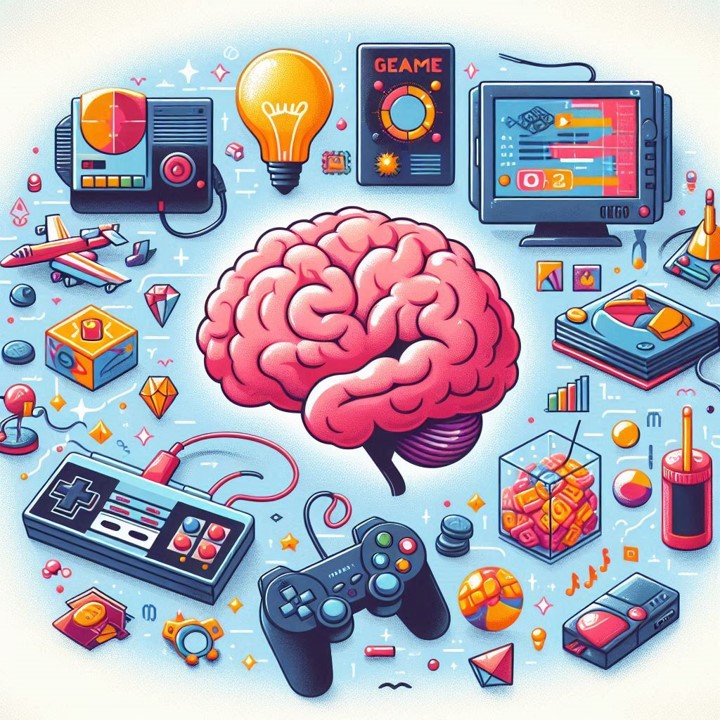
最近の研究で、 「ゲーム依存」と脳の「報酬処理」がどのように関係しているのか を詳しく調べたものがあります。この研究では、 アメリカの青少年脳認知発達(ABCD)研究 のデータを使い、 3年間にわたる追跡調査 を行いました。
どんな人が研究に参加したの?
✅ 研究には 6,143人の子どもたち が参加
✅ 研究開始時の 平均年齢は12歳
✅ 各参加者を 3年間連続で追跡(2年目、3年目、4年目のデータを分析)
✅ 合計 12,745回の観察データ を収集
このように、多くの子どもたちのデータを長期間にわたって集めることで、 ゲーム依存の変化や脳との関係 をより正確に調べることができました。
何を調べたの?
① ゲーム依存の傾向を測定
参加者は 「ビデオゲーム依存症質問票(VGAQ)」 に回答しました。
この質問票では、以下のような ゲーム依存の特徴 を評価します。
✔ ゲームをやめられないと感じるか
✔ ゲームのせいで学校や日常生活に影響が出ていないか
✔ ゲームをしないとイライラすることがあるか
この VGAQスコア(ゲーム依存の度合い)が 3年間でどのように変化するか を追跡しました。
② 脳の「報酬処理」の活動を測定
報酬処理とは、 「良いことが起きそう!」と期待することや、実際にご褒美をもらったときに脳が反応するしくみ です。
この研究では、参加者に 「金銭的インセンティブ遅延タスク」 という実験を行いました。
🔹 どんな実験?
・ 子どもたちは 機能的磁気共鳴画像(fMRI)スキャン を受けながら、特定のゲームをプレイ
・ そのゲームでは、 お金をもらえるかもしれない! という状況が用意されている
・ そのときの 脳の報酬処理の活動 を測定
この実験により、 報酬を期待したとき・実際にもらったとき に 脳のどの部分がどれくらい活動するか を調べました。
研究のポイントは?
✅ 2年目の時点での「脳の報酬処理」の活動と、その後のゲーム依存スコアの変化の関係 を調べた
✅ ベイジアン階層線形モデル という統計手法を使って、長期的な関連性を分析
この方法を使うことで、 「脳の報酬処理の特徴が、将来のゲーム依存の変化に影響を与えるか?」 をより正確に推測できるようになりました。
「ゲーム依存」と脳の報酬処理の関係 〜研究の結果をわかりやすく解説!〜
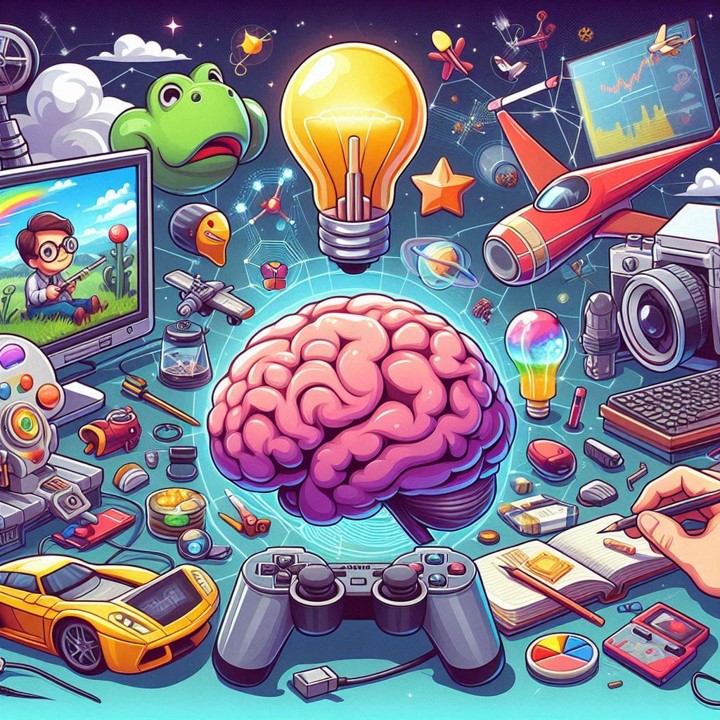
この研究では、 脳の報酬処理のしくみが、ゲーム依存の進行とどのように関係しているのか を調べました。
では、実際にどんな結果が出たのかを、できるだけわかりやすく説明していきます!
① 研究の結果:脳の報酬処理が弱いと、ゲーム依存が進む?
研究の分析の結果、以下のことがわかりました。
✅ 「大きな報酬がもらえそう!」と期待しているときに、脳の『尾状核(びじょうかく)』の活動が低い人ほど、将来的にゲーム依存の症状が悪化する傾向があった
どういうことか、具体的に説明しますね。
② 尾状核の活動とは?
尾状核(びじょうかく) は、 「良いことがありそう!」と期待するときに活発に働く脳の部位 です。
例えば、
🎁 「お菓子がもらえそう!」と期待する
🎮 「ゲームで勝てそう!」とワクワクする
💰 「お金がもらえそう!」とドキドキする
こういうとき、 尾状核が活発に動くことで「やる気」が出たり、モチベーションが高まったりします。
なぜ「尾状核の異常」がゲーム依存につながるのか?
この研究では、ゲーム依存の進行と尾状核の活動低下が関係している ことが示されました。
尾状核は、「何か良いことが起きそう!」という期待を感じるときに働く脳の部位です。
しかし…
🔹 尾状核の活動が低いと、普通の楽しみにワクワクしにくくなる
🔹 ゲームのように「簡単に強い報酬が手に入るもの」に依存しやすくなる
つまり、 普段の生活の中で喜びを感じにくい人ほど、強い刺激を求めてゲームにのめり込みやすい 可能性があるのです。
③ ゲーム依存との関係は?
研究では、子どもたちが 「お金をもらえるかもしれない!」 という場面での尾状核の活動を調べました。
その結果…
🔹 尾状核の活動が低い子ほど、将来的にゲーム依存の傾向が強くなる ことがわかりました!
具体的な数値として、
尾状核の活動が1単位増えるごとに、ゲーム依存のスコア(VGAQ)が0.87ポイント低下 することが確認されました。
(※ β = -0.87、95% CI: -1.68、-0.07 というのは、この関係が統計的に意味のあるものだということを示しています。)
つまり…
🧠 報酬に対する脳の反応が鈍いと、ゲームへの依存が進みやすい
📈 逆に、尾状核がしっかり活動する子は、ゲーム依存のリスクが低い
④ なぜ「報酬処理が鈍い」とゲーム依存になりやすいの?
尾状核の活動が低い子どもは、 「普通の報酬では満足しにくい」 可能性があります。
例えば…
🚀 ゲームは、短時間で大きな報酬(勝利、ポイント、アイテム)が手に入る
🎉 刺激が強く、すぐに「楽しい!」と感じられる
そのため、 普段の生活での小さな達成感(勉強ができた・運動を頑張った)では、満足しにくくなる ことが考えられます。
その結果、 もっと強い報酬を求めて、ゲームをやめられなくなってしまう のかもしれません。
⑤ 研究のもう一つの結果:「報酬をもらった後」の脳活動との関係は?
研究では、「報酬をもらう前の期待」だけでなく、
「実際に報酬をもらった後の脳の反応」 も調べました。
しかし、
💰 「お金をもらった後」の脳の活動と、ゲーム依存の進行には関係がなかった
という結果でした。
つまり、 「報酬を得る前のワクワク感」のほうが、ゲーム依存に関係している ということですね。
研究の意義:ゲーム依存の「脳のメカニズム」がより明確になった!
この研究によって、ゲーム依存は「ただの遊びすぎ」ではなく、脳の働きと深く関係していること が科学的に示されました。
🧠 「意志が弱いから」ではなく、脳の報酬処理のしくみが影響している!
🧩 「なぜ一部の人だけがゲームに依存しやすいのか?」の理由が脳レベルで解明されつつある!
こうした知見が、 ゲーム依存を防ぐ方法や治療法の開発に役立つ可能性がある のです。
ゲーム依存のリスクを下げるには?

この研究の結果をもとにすると、 ゲーム依存を防ぐためのヒント が見えてきます。
✅ 1. ゲーム以外の「ワクワクする経験」を増やす
ゲームは「簡単に手に入る報酬」なので、 他の活動でも達成感を感じられるようにする ことが大切です。
🔹 スポーツや習い事で「うまくなった!」という達成感
🔹 料理や工作で「作る楽しさ」を感じる
🔹 友達との遊びで「ドキドキ・ワクワク」を体験する
こうした 「小さな成功体験」 を積み重ねることで、尾状核の活動を刺激し、 ゲーム以外のことにも楽しみを感じやすくなる かもしれません。
✅ 2. ゲームの「報酬の仕組み」を意識してコントロールする
ゲームの中には、 「もっと続けたくなる仕組み」 がたくさんあります。
例えば…
🎖 レベルアップがある(「もう少しやれば強くなれる!」)
🏆 ランキングがある(「もっと上を目指したい!」)
💎 レアアイテムが出る(「次は当たるかも!」)
こうした 「報酬の期待」 をコントロールするために、
✅ ゲームの時間を決める
✅ 「時間ではなく、ステージ●つまで!」とルールを決める
✅ ゲームの前に、他の楽しい活動を取り入れる
こうした工夫をすることで、 ゲーム以外の時間も「ワクワク」を感じやすくなる かもしれません。
まとめ
✅ 「ゲーム依存」は、脳の報酬処理のしくみと関係がある
✅ 報酬を期待するときの尾状核の活動が低い子ほど、将来的にゲーム依存の症状が悪化しやすい
✅ 「ゲーム以外の活動でワクワクを増やす」ことが、ゲーム依存を防ぐカギになるかも!
この研究から、 「ゲーム依存」は単なる「意志の弱さ」ではなく、脳のしくみとも深く関係している ことがわかりました。
そのため、 ゲームだけを制限するのではなく、他の楽しい経験を増やすことも大切 ですね!
引用文献
Lopez, D. A., Foxe, J. J., van Wijngaarden, E., Thompson, W. K., & Freedman, E. G. (2024). The longitudinal association between reward processing and symptoms of video game addiction in the Adolescent Brain Cognitive Development Study. Journal of Behavioral Addictions, 13(4), 1051–1063. https://doi.org/10.1556/2006.2024.00068

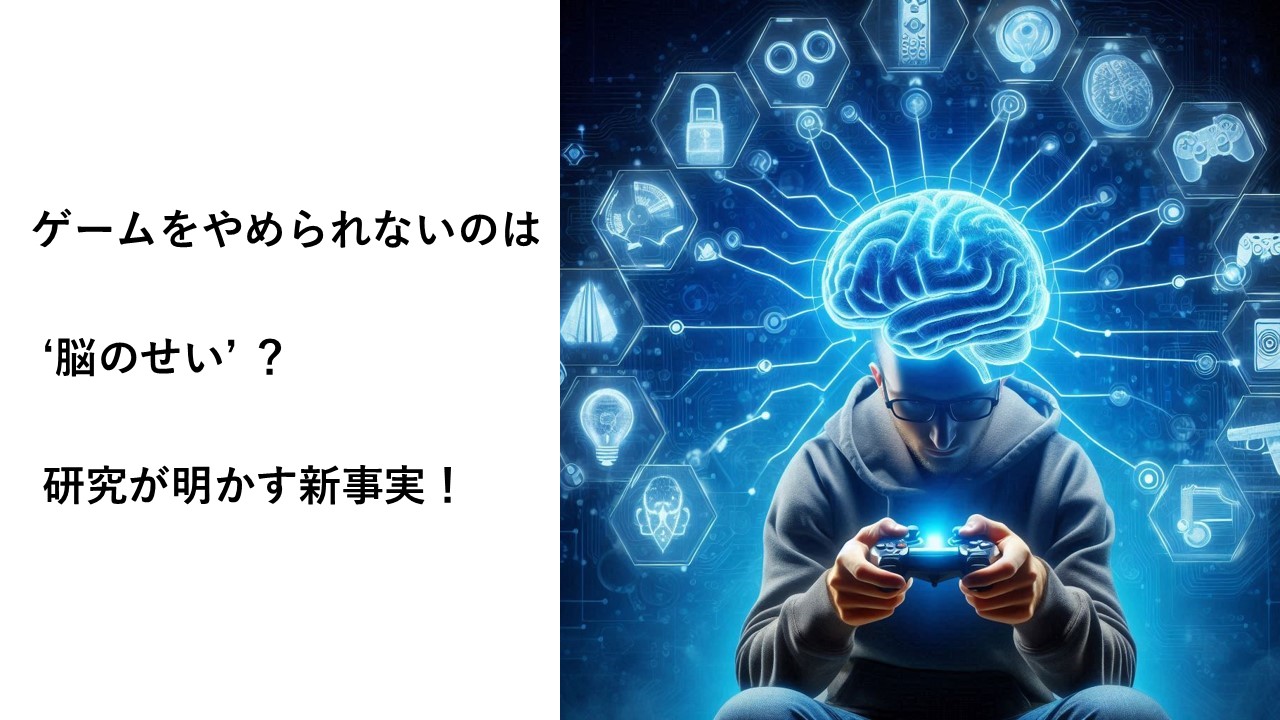
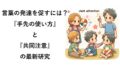
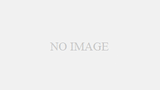
コメント