「靴ひもが結べない」「ボールを投げるのが極端に苦手」「字を書くのにとても時間がかかる」──こうした“ちょっとした不器用さ”に、周囲が気づかないまま「練習が足りないのでは?」「性格の問題かも」と受け止められてしまうことは少なくありません。
しかし、子ども自身が「一生懸命やっても、なぜかうまくいかない」と感じているとしたら、それは「発達性協調運動障害(DCD)」という神経発達の特性が背景にある可能性があります。
DCDは、年齢や知的発達に比べて運動の協調性に困難を抱え、日常生活や学習に影響を与える障害です。児童の5〜6%にみられる比較的よくある発達障害でありながら、見過ごされがちで、正しく理解されていない現状があります。
この記事では、DCDの定義や症状の特徴、他の発達障害との違い、家庭でできる具体的な支援方法について、医学的知見と最新の研究をもとにわかりやすく解説していきます。
発達性協調運動障害(DCD)とは?

DCD(Developmental Coordination Disorder)は、日本語で「発達性協調運動障害」と呼ばれる、子どもの発達に関わる障害のひとつです。
DSM-5(アメリカ精神医学会の診断基準)では、次のように定義されています。
「年齢や知的能力に見合わないほど、協調運動能力が遅れており、それによって日常生活や学業活動に著しい困難を生じている状態」
もう少しやさしく言うと、「体の動かし方が周りの子どもよりぎこちなく、生活の中でいろいろ困ることが多い状態」ということです。
子ども全体の5〜6%にみられる、けっしてまれではない障害
DCDは、小学校に通う子どもたちのおよそ20人に1人に見られるといわれており、決して珍しい障害ではありません。
- 男の子にやや多く、気づかれにくいまま成長するケースもあります。
- 注意欠如・多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)と重なってあらわれることも多く、二次的な困りごと(自信のなさ、学校への苦手意識など)につながることもあります。
DCDの子どもに見られる特徴(具体例)
DCDの子どもは、次のような運動や日常動作の不器用さを示すことがあります
- 靴ひもが結べない
- 文字を書くのが極端にゆっくりで、形も整わない
- 体育の時間が苦痛(ボールがうまく扱えない、縄跳びができない)
- よく転ぶ、ぶつかる、物を落とす
- お箸がうまく使えない、食べ物をこぼしやすい
- 服の着脱、ボタン・ファスナーが苦手
こうしたことから、「不器用な子」「のんびり屋」「運動が苦手なだけ」と見なされてしまい、本人の困りごとが気づかれないままになることもあります。
「協調運動」ってなに?
DCDという言葉に出てくる「協調運動(きょうちょううんどう)」とは、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。
📌 協調運動とは…
「目や体で感じた情報をもとに、体をスムーズに動かす力」のことです。
たとえば:
- 見たボールをよける
- 足元の段差に気づいて、タイミングよくジャンプする
- 文字を書くときに、手の動きを調整する
こうした動作には、次の3つの感覚がうまく働いている必要があります。
| 感覚 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 視覚 | 目で見て、空間や対象物を把握する力 | 距離感をつかむ、ボールの位置を見る |
| 前庭感覚 | バランスや体の傾きを感じる力 | 体をまっすぐ保つ、姿勢を変える |
| 体性感覚 | 手足の位置や力加減を感じる力 | 力を入れすぎずに鉛筆を握る、物をつかむ |
DCDの子どもは、これらの感覚を組み合わせて運動をコントロールするのが苦手なため、動作がぎこちなくなったり、極端に疲れやすくなったりするのです。
成長すればよくなる?──DCDは「努力不足」ではありません
「そのうちできるようになるよ」と言われることもありますが、DCDの子どもにとっては、**「一生懸命やっても、なぜかうまくいかない」**という悩みが根っこにあります。
そのため、本人の気持ちを大切にしながら、
- 苦手な動作を工夫して補う
- 得意な活動や小さな成功体験を重ねる
ことが支援の基本です。
「本人のせいではない」という理解が、何よりの支援の第一歩になります。
なぜ早く気づくことが大切なの?
DCDは、早期に気づいて適切な支援をすれば、本人の「できること」「やってみようとする力」を伸ばしていける障害です。
逆に、気づかれずにいると:
- 「失敗ばかりして自信をなくす」
- 「運動や人との関わりを避けるようになる」
といった二次的な問題が起きやすくなります。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| DCDとは | 協調運動が苦手で、生活に支障が出る発達障害 |
| 有病率 | 小児の5〜6%、ASDやADHDと重なることも |
| 症状 | 転ぶ、運動が苦手、文字が書けない、手先が不器用など |
| 特徴 | 感覚を統合して体を動かす力(協調運動)に困難がある |
| 支援 | 苦手さを理解し、できる工夫や自信づけが大切 |
DCDの重複・鑑別診断における留意点

──「不器用さ」の背景を見極めるために
DCD(発達性協調運動障害)は、日常生活に支障をきたす「不器用さ」の背後にある神経発達障害です。しかし、他の発達障害や神経疾患でも類似した運動の問題が見られるため、重複や鑑別診断がとても重要になります。
ここでは、特に重なりやすいADHD・ASD・知的障害・脳性麻痺との違いについて、整理しておきましょう。
1. ADHD(注意欠如・多動症)との併存と鑑別
ポイント:ADHD児の約30〜50%がDCDの特徴をもつ
- ADHDの子どもは、集中しにくく、落ち着きがない、順序立てて行動するのが苦手といった特徴があります。
- こうした注意の問題が、**「運動の不正確さ」「ぎこちなさ」**に見えることがあります。
📖 研究報告:
Kadesjö & Gillberg(1999)によれば、ADHDの子どもの約30〜50%に、運動の協調に問題が見られています。
鑑別のポイント
| 項目 | ADHDの影響 | DCDの影響 |
|---|---|---|
| 運動ミスの理由 | 注意力が途切れ、指示を聞き逃す/集中が続かない | 動きを頭で計画する力(運動計画)の弱さ |
| 特徴的な行動 | 落ち着きがなく、動きが多すぎる | 動きがぎこちない/遅い/不器用 |
| 支援の視点 | 環境の調整(刺激の少ない場所、指示の工夫) | 運動の構造化(段階づけ、手順の見える化) |
2. ASD(自閉スペクトラム症)との関連
ポイント:ASDの子の約80%に運動のぎこちなさが見られるが、DCDとは限らない
- ASDの子どもにも、「ぎこちない動き」「ボールが取れない」「ジャンプが苦手」といった症状が見られます。
- しかし、ASDでは**「人との関係」や「こだわり」など社会的な側面の困難が中心**であり、DCDとは障害の根本が異なります。
📖 研究報告:
ASDの約80%に運動機能の困難が報告されており(Green et al., 2009)、特に模倣・予測・協調性を伴う運動が苦手な傾向があります。
鑑別のポイント
| 項目 | ASDの運動障害 | DCDの運動障害 |
|---|---|---|
| 背景 | 対人関係や感覚の特異性に起因する | 運動の計画・制御そのものの困難 |
| 特徴 | 模倣や集団運動に極端な抵抗/感覚過敏が強く出やすい | 一人での作業や動作でもぎこちない・不器用 |
| 社会性 | 対人関係やコミュニケーションにも困難がある | 対人関係は比較的良好なことが多い |
3. 知的障害・脳性麻痺との違い
ポイント:DCDは知的遅れや明らかな脳の損傷がないにもかかわらず、不器用さが目立つ
- 知的障害では、学習全体に影響があり、運動だけでなく言語や社会性など広範な領域に困難が見られます。
- 脳性麻痺では、出生時や乳児期の脳の損傷により、筋緊張・姿勢・反射などに明確な神経学的異常があります。
DCDの特徴的な点
| 比較対象 | 明確な神経学的異常 | MRI所見 | 知的発達 | 運動以外の影響 |
|---|---|---|---|---|
| DCD | なし | 原則正常(軽微な異常は報告あり) | 年齢相応〜軽度の差 | 運動以外は比較的良好 |
| 知的障害 | なし〜あり | 様々な変化あり | 全般的に遅れ | 広範囲に影響 |
| 脳性麻痺 | あり(反射・筋緊張) | はっきりと異常が見られる | 状況による | 姿勢・筋緊張・協調など多領域 |
📖 Zwicker et al. (2012) の研究では、DCD児に小脳・前頭前野の構造的・機能的な軽度異常が見られ、これが運動計画の困難に関係している可能性が示唆されています。
鑑別診断で大切な視点
- 「運動の不器用さ」はさまざまな発達障害で見られることがある
- どこに主な困難があるのか?(注意?社会性?知能?運動計画?)を見極めることが重要
- 重複している場合も多いため、単一の診断名で子どもを枠にはめすぎないことが大切
まとめ
| 重複・鑑別 | 留意点 |
|---|---|
| ADHD | 注意力由来か運動計画由来かの見極め |
| ASD | 社会性や感覚特性を伴うかどうかで鑑別 |
| 知的障害 | 運動以外の全般的な発達遅れがあるか |
| 脳性麻痺 | 神経学的異常やMRIでの明確な損傷 |
家庭で使える DCDスクリーニングチェックシート
(発達性協調運動障害の可能性を早期に見つけるために)
PDFでダウンロードしたい場合は、上記の「ダウンロード」のボタンからどうぞ。
チェックしてみましょう
以下のアンケートに答えてみてください。
粗大運動の5項目、微細運動の5項目、動作の計画・段取り・感覚の項目の5項目、合計15項目で評価を行います。
評価のしかた(スコア例)
- 「はい」=2点、「ややはい」=1点、「それ以下」=0点
- 合計点で以下のように評価
| 合計点 | 判定 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 20点以上 | 高リスク | 専門機関へ相談を強く推奨 |
| 12〜19点 | 中リスク | 観察+支援・相談を推奨 |
| 0〜11点 | 低リスク | 現時点では大きな支援は不要。ただし継続観察を |
粗大運動 5項目
| No. | 質問 | はい | ややはい | ふつう | ややいいえ | いいえ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 階段を交互の足で上るのが難しい | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 走る・ジャンプする動きがぎこちない | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | ボールを投げたりキャッチするのが苦手 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 縄跳びやスキップができない/極端に遅い | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 運動中によく転んだり、つまずくことが多い | □ | □ | □ | □ | □ |
微細運動 5項目
| No. | 質問 | はい | ややはい | ふつう | ややいいえ | いいえ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 鉛筆やお箸を正しく持てない | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7 | 字が極端に大きすぎる/小さすぎる/読みにくい | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8 | ボタン・ファスナーが自分でできない | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 食べ物をよくこぼす/スプーンがうまく使えない | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 工作・ぬり絵などを好まず避けようとする | □ | □ | □ | □ | □ |
動作の計画・段取り・感覚の項目(5問)
| No. | 質問 | はい | ややはい | ふつう | ややいいえ | いいえ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 動作の順序(着替え・準備など)をよく間違える | □ | □ | □ | □ | □ |
| 12 | 自分の体の使い方をうまく把握できていないように見える(ぶつかる、ぶつける) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 13 | 動作を始めるのに時間がかかる(指示してもすぐに動けない) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 14 | 少しの運動でも疲れやすく、すぐに嫌がる | □ | □ | □ | □ | □ |
| 15 | 感覚が過敏・鈍感で、動作に支障が出ている(音・手触り・姿勢など) | □ | □ | □ | □ | □ |
注意事項と免責文
※このスクリーニングチェックシートは、医学的な診断や治療を行うものではありません。
※内容は、既存の評価ツールや論文に基づき、作者の知見をもとに独自に作成されたものであり、正式な医学的検証は行われていません。
※あくまでも「保護者が子どもの様子に気づくための参考資料」としてご使用ください。
※結果に不安がある場合は、必ず専門家(小児科医、作業療法士など)にご相談ください。
各項目の背景と医学的根拠(解説)
【A】粗大運動に関する項目(1〜5)
1. 階段を交互の足で上るのが難しい
- 根拠:粗大運動における下肢の協調性とバランス能力が必要。DCD児では空間認識と左右の交互運動の困難がみられる。
- 出典:Henderson et al. (2007) MABC-2、Wilson et al. (2013)
2. 走る・ジャンプする動きがぎこちない
- 根拠:連続運動と運動計画(motor planning)に障害があると、動きがスムーズでなくなる。
- 関連脳領域:小脳・補足運動野・運動前野
- 出典:Zwicker et al. (2012)
3. ボールを投げたりキャッチするのが苦手
- 根拠:視覚・運動のタイミング調整(視覚運動協調)に問題があることが多い。
- 出典:Brown-Lum & Zwicker (2015)、DCDQの代表項目でもある。
4. 縄跳びやスキップができない/極端に遅い
- 根拠:リズム運動や身体のタイミング操作(internal modeling)が難しいことがDCDの特徴の一つ。
- 出典:Adams et al. (2014)
5. 運動中によく転んだり、つまずくことが多い
- 根拠:バランス機能・前庭系・体性感覚の統合障害が示唆される。
- 出典:Fong et al. (2015)
【B】微細運動に関する項目(6〜10)
6. 鉛筆やお箸を正しく持てない
- 根拠:微細運動スキル、特に手指の巧緻性と姿勢安定性に課題があるDCD児は多い。
- 出典:Mandich et al. (2003)
7. 字が極端に大きすぎる/小さすぎる/読みにくい
- 根拠:視覚運動統合の困難、および筆記姿勢の保持に関連する。
- 出典:Prunty et al. (2014)
8. ボタン・ファスナーが自分でできない
- 根拠:両手の協調(bimanual coordination)や指の分化運動が難しいことが原因。
- 出典:Missiuna et al. (2008)
9. 食べ物をよくこぼす/スプーンがうまく使えない
- 根拠:スプーン操作には手の力加減、タイミング、角度調整が必要。DCDでは動作制御の予測困難が影響する。
- 出典:Schoemaker & Kalverboer (1994)
10. 工作・ぬり絵などを好まず避けようとする
- 根拠:失敗経験の積み重ねにより、自己効力感が低下して回避行動につながる。
- 出典:Rodger & Ziviani (2006)
【C】動作の計画・段取り・感覚の項目(11〜15)
11. 動作の順序(着替え・準備など)をよく間違える
- 根拠:実行機能(executive function)の一部である動作系列化の困難が影響。
- 出典:Wilson et al. (2009)
12. 自分の体の使い方をうまく把握できていないように見える(ぶつかる、ぶつける)
- 根拠:体性感覚フィードバックや空間認知の統合不全による。
- 出典:Tsai et al. (2008)
13. 動作を始めるのに時間がかかる(指示してもすぐに動けない)
- 根拠:動作の内部モデル生成が不十分で、運動イメージと運動計画に遅れがあるとされる。
- 出典:Adams et al. (2014)
14. 少しの運動でも疲れやすく、すぐに嫌がる
- 根拠:運動効率が悪いため、同じ運動でもエネルギー消費が大きいことがある。
- 出典:Cairney et al. (2005)
15. 感覚が過敏・鈍感で、動作に支障が出ている(音・手触り・姿勢など)
- 根拠:DCDは感覚処理障害(SPD)との重なりがあり、前庭感覚や固有感覚の統合困難が関係していることがある。
- 出典:Cummins et al. (2005), Piek & Dyck (2004)
ご注意
※このスクリーニングチェックシートは、医学的な診断や治療を行うものではありません。
※内容は、既存の評価ツールや論文に基づき、作者の知見をもとに独自に作成されたものであり、正式な医学的検証は行われていません。
※あくまでも「保護者が子どもの様子に気づくための参考資料」としてご使用ください。
※結果に不安がある場合は、必ず専門家(小児科医、作業療法士など)にご相談ください。
保護者のためのQ&A
~DCDスクリーニングシートをご活用いただく方へ~
Q1:チェック項目に複数当てはまったら、DCDだと確定するのでしょうか?
A:いいえ。
このシートはあくまで「気づきのための参考資料」です。DCDかどうかの診断は、医師や専門家(作業療法士など)が、標準化された評価や問診を通して総合的に行います。
Q2:子どもは運動が苦手ですが、普段の生活には問題ありません。それでも心配するべき?
A:運動が苦手なこと自体は個性の範囲かもしれません。
ただし、「本人が困っているかどうか」「周囲との比較で著しくできないことがあるか」は見極めのポイントです。気になる場合は、記録を取りながら様子を見ましょう。
Q3:このチェックシートは何歳から使えますか?
A:概ね4歳〜小学校中学年ごろを想定しています。
ただし、個人差があるため、3歳後半から様子をみて使用することも可能です。
Q4:誰に相談すればいいですか?
A:地域の小児科医、発達外来、作業療法士、保健センターの相談窓口が適しています。
園や学校の先生に相談するのも、第一歩として有効です。
Q5:DCDと診断されたら、何か治療があるのですか?
A:薬で治すというよりは、作業療法・理学療法・発達支援などで「できることを増やす」支援が中心になります。
「苦手でも、自分なりにできるようになる」ことを目指します。
実践ヒント集:家庭でできるDCDサポートの工夫
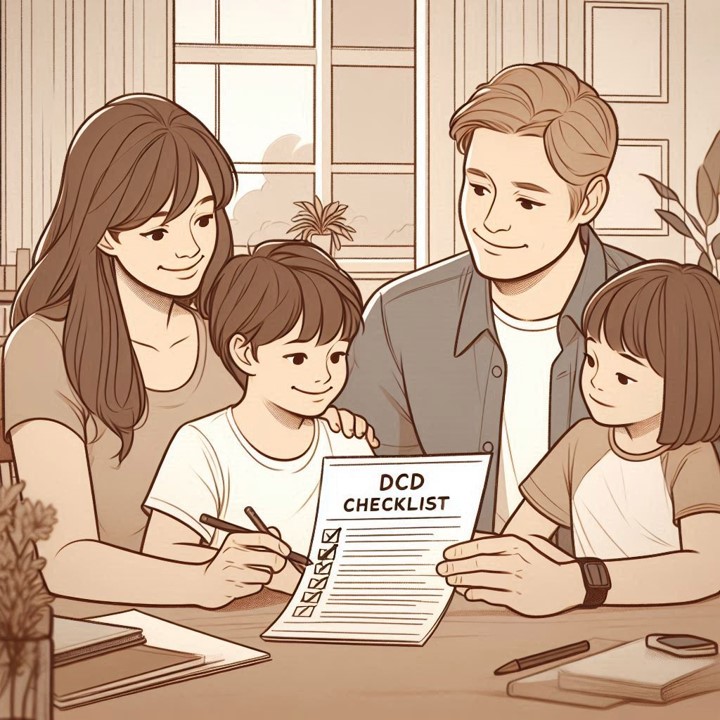
① 粗大運動の不器用さを支える
よくある困りごと
- 走る・跳ぶ・ボールを投げるなどの全身運動が苦手
- 転びやすい、姿勢が崩れる、動きがぎこちない
サポートのポイント
- 小さな動きから段階的に
- 動きを「遊び」の中で練習
- 苦手な運動を強制せず、「できた!」を重ねる
家庭でできる工夫
- 風船バレーや新聞紙ボール投げ(ゆっくり飛ぶ物で動作を調整)
- クッションの上でバランスをとる/線の上を歩く遊び(低負荷なバランス遊び)
- けんけんぱ、フープジャンプ、ゆるい縄跳び(ジャンプ動作を楽しく)
② 微細運動の不器用さへのサポート
よくある困りごと
- お箸や鉛筆の持ち方が不安定
- ぬり絵・はさみ・折り紙がうまくできない
- 食事でこぼす、ボタンができない
サポートのポイント
- 指先の感覚と動きを育てる
- 成功体験が得やすい「作業系あそび」から始める
家庭でできる工夫
- 指先を使う遊び:スライム・粘土・小さなビーズ遊び
- 「洗濯ばさみをたくさんはさむ」「ペットボトルのキャップを回す」など日常動作を遊びに
- 食事ではスプーンの先に印をつける、滑り止めのマットを敷くなどの簡単な補助も効果的
③ 動作の段取り・順序が苦手な子への工夫
よくある困りごと
- 着替えや準備がうまくできない
- 作業に時間がかかる/忘れ物が多い
サポートのポイント
- 順序を「目で見える形」にする
- 一つひとつ区切って、焦らずに進める
家庭でできる工夫
- 「着替えリスト」「朝の支度チェック表」などを絵や写真で掲示
- 「次は何するんだっけ?」と声かけして一緒に考える時間を作る
- ゲームのようにタイマーを使って「着替えタイムチャレンジ!」など、楽しみながら
④ 疲れやすさ・集中の持続が難しい子への対応
よくある困りごと
- 少しの運動や作業で「もう疲れた」と言う
- やり始めてもすぐ飽きる/集中が続かない
サポートのポイント
- 「休憩を取りながら」「短時間で達成できる工夫」を
- 疲れを責めず、本人のペースを尊重
家庭でできる工夫
- 「3分運動→1分休憩」など活動と休息を交互に
- 「5分だけ集中タイム」→「ごほうびタイム」で小さな成功体験を積み重ねる
- 疲れている時は体の位置をリセットできる「ゴロゴロ」「ハンモック」「抱っこ」もおすすめ
⑤ 自信のなさ・失敗回避行動への関わり方
よくある困りごと
- 「やらない」「できない」とすぐに諦めてしまう
- 苦手な活動を避けようとする
サポートのポイント
- 小さな「できた!」を見つけて言葉にする
- できなくても否定せず、「やってみたね」と努力を認める
家庭でできる工夫
- 「今日は1つでもやれたらすごいね!」と目標をゆるく設定
- 「お母さんも練習中だよ」と共感する姿勢で寄り添う
- お手伝い成功スタンプカードなどで達成感を可視化
まとめ:家庭でのキーワードは…
🎯 「楽しく・短く・少しずつ」
🌟 「苦手」より「できること」に目を向ける
❤️ 「その子なりの成長」を喜び合う関係づくり
まとめ

発達性協調運動障害(DCD)は、「単なる不器用さ」ではなく、脳の運動計画や協調機能に関連する発達の特性です。ADHDやASD、知的障害など他の神経発達症と重なって見えることも多く、丁寧な観察と鑑別が必要です。
しかし、DCDの子どもたちは、適切な支援や理解があれば、日常生活に必要なスキルを身につけることができ、成功体験を積み重ねることが可能です。大切なのは、「できないこと」ばかりに目を向けるのではなく、「できる方法」を一緒に探し、本人のペースで成長を支えること。
まずは、子どもの小さな「つまずき」に気づき、「もしかしたらDCDかもしれない」という視点をもつこと。それが、支援への第一歩となるのです。




コメント