「うちの子はなかなか心を開いてくれない」「抱っこを嫌がるのに、急に甘えてくることもある」――そんな戸惑いを感じたことはありませんか?
子どもとの関係が思うように築けないと、親として自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
実は、その背景には“愛着”の問題が関わっている場合があります。愛着障害と聞くと難しく感じるかもしれませんが、基本的には「人を信じて安心できる気持ちが育ちにくい状態」のこと。子どもの行動の裏側には、不安や安心を求めるサインが隠れているのです。
この記事では、愛着障害の基礎的な理解から、家庭でできる具体的な支援、そして専門家に頼る場面までを、わかりやすく整理してお伝えします。大切なのは“完璧な親になること”ではなく、“安心を届ける姿勢を続けること”。そのためのヒントを一緒に見つけていきましょう。
愛着障害とは

子どもにとって「愛着」とは、安心できる大人(主に養育者)とのあいだに築かれる信頼関係のことを指します。生後まもなくから、人は周囲の大人との関わりを通じて「守ってもらえる」「安心できる」という感覚を学び、それが情緒の安定や対人関係の基盤となります。
しかし、養育環境における不安定さ(虐待や養育者の精神的困難など)によって、安定した愛着が築かれにくい場合があります。このような状態が続くと、「愛着障害(attachment disorder)」 と呼ばれる問題が見られることがあります。
医学的には、DSM-5(米国精神医学会の診断基準)では「反応性愛着障害(Reactive Attachment Disorder; RAD)」や「脱抑制型対人交流障害(Disinhibited Social Engagement Disorder; DSED)」として分類されています。前者は「大人への安心した関わりを示さない」、後者は「見知らぬ人にも過度に近づく」など、異なる特徴を示します(American Psychiatric Association, 2013)。
ただし、日常的に「愛着障害」と言う場合は、必ずしも診断名そのものを指すのではなく、「信頼関係の形成に困難がある状態」を広く指して使われることも多いです。
研究では、愛着の安定性が子どもの社会性や感情調整に深く影響することが示されています。たとえば、愛着が安定している子どもはストレス状況でも落ち着きを取り戻しやすく、逆に愛着が不安定な場合には、不安・攻撃性・人との距離感の問題が見られやすいことが報告されています(Sroufe, 2005; Zeanah & Gleason, 2015)。
つまり愛着障害とは、「安心できるつながりの欠如や不安定さ」が、子どもの心の発達や対人関係に影響を与えている状態と理解するとわかりやすいでしょう。
参考文献
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment & Human Development, 7(4), 349–367.
Zeanah, C. H., & Gleason, M. M. (2015). Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood – clinical presentation, causes, correlates, and treatment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(3), 207–222.
家での具体的な支援

家庭での支援の柱は「敏感さ・一貫性・予測可能性・回復(修復)」の4つです。
- 敏感さ:子どもの合図(泣く・視線・体の向き・言葉)に気づき、すみやかに的確に応えること。敏感さを高める親向け介入は、子の愛着の安定化に効果があると示されています。
- 一貫性:同じ合図に、親が毎回だいたい同じ対応をすること。
- 予測可能性:生活の流れや約束を決め、先が見えるようにすること(小さな“儀式”が有効)。
- 回復(修復):親子で行き違った後に、やり直すこと。ミスは避けられませんが、短時間での「修復」が信頼感を深めます。
今日からできる具体的スキル

A.「子ども主導の10分あそび」(PCITのCDI*から)
1日10分、子どもが選び・主導する遊びに大人がつき合います。ポイントはPCITのPRIDEスキル:
- P(Praise/称賛):具体的に褒める「ブロックをゆっくり積んでるね、すてき!」
- R(Reflect/復唱):子の発言を言い換えて返す
- I(Imitate/まねる):同じ遊びをまねて関心を示す
- D (Describe/描写):していることを実況する
- E (Enthusiasm/熱意):声や表情で楽しさを伝える
この「特別な時間」は、親子のポジティブな関わりを増やし、問題行動を減らすことが再現性高く示されています。
*PCIT=Parent-Child Interaction Therapy(親子相互交流療法)
やり方の例(就学前〜小学生)
- 準備:おもちゃは子が選ぶ(ブロック・お絵描き・ミニカーなど)。タイマー10分。
- 親が言うこと:指示や質問は最小限。「すごい集中してるね」「赤と青を組み合わせたんだね」「次はどうしようか?」
- 避けること:批評・テストのような質問・コントロール(「こうしなさい」は極力しない)
B. 感情コーチング(泣き・怒り・不安に強くなる)
親が「感情の名づけ」「共感」「境界の確認」を順に行うと、子の情動調整が育ちやすくなります。感情コーチングを教えるプログラム(Tuning in to Kidsなど)は、親の対応と子の行動の改善に有効です。
5ステップ&セリフ例
- 発見:「顔がぎゅっとなってる。つらそうだね。」
- 名前をつける:「今はくやしい気持ちなんだね。」
- 共感:「その気持ちは大事だよ。ぼく(わたし)にもわかるよ。」
- 境界:「人をたたくのはダメ。安全は守るよ。」
- 次の一手:「いっしょに3回深呼吸→言葉で伝える練習をしよう。」
C. コレグレーション(荒れた時の“落ち着き方”を一緒に作る)
「先に落ち着く→ルールに戻す→終わったら修復」という順番がコツです。
- 落ち着く:低い声・ゆっくり・短い言葉。「ここにいるよ。息を合わせよう。」
- ルール:安全と他者尊重は一貫して止める(ものを投げない/人をたたかない)。
- 修復:おちついたら、短くふり返りとやり直し。「さっきはイヤだったね。次は“貸してって言う”を試そう」
頻繁な不一致は避けられませんが、修復ができれば関係は強くなります。
D. 予測可能な生活(小さな儀式を増やす)
朝・帰宅・就寝前に3つの固定ルーティンを作り、見える化(メモや絵)します。儀式は不安を下げ、適応を助けます。
例
- 朝:「ハグ→歯みがき→玄関ハイタッチ」
- 帰宅:「荷物置き→手洗い→5分おしゃべり」
- 就寝前:「読書2冊→電気を暗く→同じ一言でおやすみ」
E. 分離や登園の不安への段階づけ
短時間・予告あり・必ず迎えに戻るを繰り返して「戻ってくる体験」を積みます(はじめは数分→15分→30分…)。**合図(合言葉・小物)**を決めると安心材料になります。親は「戻る時刻」を曖昧にしないで約束を守ること。
F.「ミスの修復」を言葉にする
- 親:「さっき、声を大きくしてごめん。もう一回やり直させて。」
- 子:「うん/いやだ」→どちらでも「言ってくれてありがとう」と受け止め、短いやり直しの遊びやハグで終える。
修復の積み重ねは、不完全でも大丈夫という安心を育てます。
G. 親の“こころのメガネ”を磨く(メンタライジング/マインドマインデッドネス)
子の行動の裏にある心を想像して言葉にする力(親の反省機能・マインドマインデッドネス)は、敏感さや愛着の安定と関連します。
質問メモ(心を思い浮かべる3問)
- 今この子は何を感じている?
- 何を伝えたい?
- 私の気持ちはどう影響してる?(深呼吸→短い対応)
H.「してはいけないこと」を減らす
- 体罰・恥をかかせる叱責・長時間の無視は逆効果で、関係を傷つけるリスクが示されています。
- 罰だけに頼らず、前もって教える・褒める・短く止めるの比率を増やす。
- なお、構造化されたタイムアウトは専門家の指導下で有効に用いられることがありますが(PCITの後半ステージなど)、家庭独自の厳罰的運用は避けましょう。
I. 親自身のケア(支える人を支える)
- 親のうつ症状や強いストレスは、敏感な関わりを難しくします。つらさが続くときは早めに相談を。
- 1分の呼吸(4秒吸う→6秒吐く×5回)、週1回の自分の楽しみ、伴走者(家族・友人・支援者)に1日のハイライトを共有する…など、小さな回復を意図的に入れましょう。
よくある場面別ミニプラン
- 登園前のぐずり
- 前夜に翌朝の3コマ絵予定を一緒に描く
- 朝は「実況+称賛」を多めに(PRIDE)
- 玄関儀式(合言葉→ハイタッチ→見送りの位置までいっしょ)
- きょうだいげんか
- 安全確保→感情コーチングでそれぞれの気持ちを名づけ
- ルール再確認(手は出さない)→やり直しの提案(順番カード)
- 寝る前の不安
- 同じ絵本・同じフレーズで予測可能性
- 「心のお守り」(小さな布・写真)を用意
- 親の不在時は戻る時間を具体的に伝え、必ず守る
家庭での自己チェック(週1回/○×でOK)
- 1日10分の子ども主導あそびができた
- 今週の**儀式(朝・帰宅・就寝)**を守れた
- 荒れた後に修復の一言を伝えられた
- 自分のしんどさを誰かに共有できた
参考文献
Bakermans‐Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2003). Less is more: Sensitivity-focused interventions… JCCP, 71(2), 406–422.
Thomas, R., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2012). Parent–child interaction therapy: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 32(6), 447–465.
Lieneman, C. C., et al. (2017). Parent–Child Interaction Therapy: A comprehensive review. Clin Child Fam Psychol Rev, 20, 412–428.
Havighurst, S. S., et al. (2010). Tuning in to Kids: RCT in community settings. J Child Psychol Psychiatry, 51(12), 1342–1350.
Burkhardt, S. C. A., et al. (2024). Tuning in to Kids delivered online: RCT. Child Psychiatry & Human Development.
Bernard, K., et al. (2015). ABC intervention and cortisol regulation: RCT. JAMA Pediatrics, 169(11), 1100–1107.
Bernard, K., et al. (2017). ABC and receptive vocabulary: RCT follow-up. Child Maltreatment, 22(2), 174–179.
Roben, C. K. P., et al. (2017). Moving an evidence-based parenting program into the community (ABC). Child Dev Perspectives, 11(4), 271–276.
Tronick, E. (2007). The repair of mismatches in mother–infant interaction. In The Neurobehavioral and Social Emotional Development….
Beebe, B., & Lachmann, F. (2014). Disorganized attachment and the repair of trauma. In Infant Research and Adult Treatment.
Spagnola, M., & Fiese, B. H. (2007). Family routines and rituals: A context for development. Infant Mental Health Journal, 28(4), 409–428.
Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. Attachment & Human Development, 7(3), 269–281.
Ordway, M. R., et al. (2015). Parental reflective functioning. Infant Mental Health Journal, 36(6), 624–635.
Meins, E., et al. (2002). Maternal mind-mindedness and attachment security… Child Development, 73, 1715–1726.
Lovejoy, M. C., et al. (2000). Maternal depression and parenting behavior: Meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 20(5), 561–592.
American Academy of Pediatrics. (2018). Effective Discipline to Raise Healthy Children. Pediatrics, 142(6), e20183112.
専門家による支援

愛着障害の子どもを支えるうえで、家庭での工夫は非常に大切ですが、場合によっては専門家の関与が不可欠になります。特に、子どもの行動が強く日常生活に影響している場合や、親自身が大きなストレスや孤独感を抱えているときには、専門的な支援を受けることで改善が期待できます。
心理療法的アプローチ
■ 親子相互交流療法(Parent-Child Interaction Therapy; PCIT)
PCITは、親と子が一緒に取り組む心理療法で、専門家がリアルタイムで親の関わり方をサポートします。研究では、PCITによって親子の関係性が改善し、子どもの問題行動が減少することが示されています(Thomas & Zimmer-Gembeck, 2012)。
■ 親子関係改善プログラム(Attachment and Biobehavioral Catch-up; ABC)
ABCは特に養育リスクの高い家庭に有効で、親が子どものサインに「敏感に応える」ことを学びます。介入を受けた家庭では、子どものストレスホルモン(コルチゾール)の調整が改善され、情緒の安定につながったことが報告されています(Bernard et al., 2015)。
■ 感情コーチング・プログラム(Tuning in to Kids)
親が子どもの感情に気づき、共感し、適切に対応するスキルを学ぶプログラムです。ランダム化比較試験では、親の対応の改善だけでなく、子どもの不安や攻撃性の減少が認められました(Havighurst et al., 2010)。
医学的アプローチ
愛着障害そのものを直接「薬で治す」方法はありません。ただし、強い不安・抑うつ・ADHD症状などが合併している場合、薬物療法が用いられることがあります(Zeanah & Gleason, 2015)。これは、子どもの生活や療育がスムーズになるための補助的な役割と考えられます。
家族へのサポート
愛着障害の子どもを育てる親は、孤立感や自責感を抱えやすいことが知られています。支援グループやペアレントトレーニングに参加することで、「一人で抱え込まなくてもいい」と感じられるようになります(Dozier et al., 2002)。
また、親自身が過去のトラウマやストレスを抱えている場合には、**親への心理的支援(カウンセリングやメンタルヘルスケア)**が子どもへの関わりの質を高める助けになります。
支援のゴール
専門家による支援の最終的な目標は、「完璧な親子関係」を作ることではありません。むしろ、
- 親が子どものサインに気づきやすくなる
- 子どもが「安心して戻れる場所がある」と感じられる
- 行き違いがあっても修復できる関係を積み重ねる
このような状態を目指すことが、長期的に子どもの発達を支える基盤になります。
参考文献
Thomas, R., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2012). Parent–child interaction therapy: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 32(6), 447–465.
Bernard, K., et al. (2015). ABC intervention and cortisol regulation: A randomized controlled trial. JAMA Pediatrics, 169(11), 1100–1107.
Havighurst, S. S., et al. (2010). Tuning in to Kids: An emotion-focused parenting program—randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(12), 1342–1350.
Zeanah, C. H., & Gleason, M. M. (2015). Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(3), 207–222.
Dozier, M., et al. (2002). Attachment and biobehavioral catch-up: An intervention for parents at risk. Infant Mental Health Journal, 23(5), 459–480.
まとめ
愛着障害は、幼少期の親子関係や生活環境の影響を強く受ける発達上の課題です。しかし、愛着の形成は一度失われたら終わりというものではなく、日常の中での「安心できる関わり」や「予測可能な日常」を積み重ねることで、子どもの心の安全感は回復していきます。家庭での小さな工夫と、必要に応じた専門家の支援を組み合わせることで、子どもは少しずつ人との関係を信じられるようになり、自分自身を大切にできる力を育てていくことができます。
愛着障害に直面する親や支援者にとって大切なのは、「完全であること」ではなく、「安心を届け続ける姿勢」を持ち続けることです。その積み重ねが、子どもの未来を大きく支える力となります。


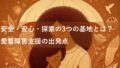

コメント