「どうしてこの子は、人との関わりを避けてしまうのだろう」
「なぜ、安心して過ごせるはずの場面で強い不安を訴えるのだろう」
こうした子どもの姿の背景には、愛着の課題が隠れていることがあります。愛着は、子どもが養育者との関わりを通じて「安心」や「信頼」を育む心の基盤です。その形成が不安定になると、対人関係や情緒発達に影響が生じ、いわゆる「愛着障害」と呼ばれる状態になることがあります。
今回は、愛着障害支援の立場から重要とされる「3つの基地機能」に注目し、安心できる関係づくりの第一歩について考えていきます。
愛着と支援の出発点

子どもが安心して成長していくためには、「愛着」という土台が欠かせません。愛着とは、子どもが特定の大人との関わりを通して育んでいく「心のつながり」のことを指します。心理学者ジョン・ボウルビィ(Bowlby, 1969)は、愛着を「子どもが安心を求めて養育者に近づこうとする行動と、その情緒的な絆」と定義しました。
たとえば、赤ちゃんが泣いたときに抱きしめてもらうと落ち着いたり、怖い夢を見たときに親のそばで安心して眠れるようになるのは、この「愛着」のはたらきによるものです。子どもにとって養育者は、ただ生活を支えてくれる人ではなく、「心を守ってくれる存在」でもあるのです。
愛着がしっかりと形成されると、子どもは次のような力を得ます。
- 信頼:「自分は大切にされている」という確信
- 安心:不安や恐怖をやわらげ、心を落ち着かせる力
- 挑戦する勇気:守ってくれる人がいるからこそ、新しいことに挑戦できる力
逆に、虐待やネグレクト、不安定な養育環境が続くと、愛着の形成が妨げられ、「人を信じることが難しい」「気持ちをうまくコントロールできない」といった困難につながることがあります(Zeanah & Smyke, 2008)。こうした状態は「愛着障害」と呼ばれ、子どもの人間関係や情緒の発達に影響を及ぼします。ただし、愛着障害の詳細については別の記事で解説していますので、ここでは触れる程度にとどめます。
本記事では、愛着形成を支える大切な要素として知られている「3つの基地機能」に焦点を当てます。
- 恐怖や不安から守ってくれる 安全基地
- 一緒にいて落ち着きや楽しさを感じられる 安心基地
- 外の世界を探索し、体験を持ち帰って受け止めてもらえる 探索基地
これらの基地があるからこそ、子どもは人を信頼し、安心しながら成長し、挑戦を通して自分の力を広げていくことができます。次のセクションでは、それぞれの基地機能について具体的に見ていきましょう。
参考文献
Bowlby J. Attachment and Loss. Basic Books, 1969.
Zeanah CH, Smyke AT. Disorders of Attachment. In: Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, 2008.
安全基地 ― ネガティブ感情から守る拠点

子どもが成長する過程では、恐怖や不安、怒りや悲しみといったネガティブな感情に直面することが多々あります。そのときに必要なのが「安全基地」です。安全基地とは、子どもが困難な感情に押しつぶされそうになったときに「ここにいれば守られる」「大丈夫」と感じられる拠点のことです。
心理学者ジョン・ボウルビィ(Bowlby, 1969)の愛着理論によれば、子どもは養育者が一貫して応答してくれる経験を通して、「この人は必ず自分を助けてくれる」という基本的信頼感を獲得していきます。この信頼があるからこそ、子どもは安心して養育者に助けを求められるようになります。
たとえば、
- 夜中に怖い夢を見て泣き出したとき、すぐに抱きしめてもらえる
- 転んでけがをしたときに、ただ「我慢しなさい」と言われるのではなく、痛みを理解され、すぐに手当てしてもらえる
こうした日常の積み重ねが、子どもに「自分は守られている」という感覚を育てていくのです。
一方で、子どもが「助けて」とサインを出しているときに無視されたり、拒絶されたりするとどうなるでしょうか。次第に「どうせ助けてもらえない」「自分の気持ちはわかってもらえない」という学習が起こり、基本的信頼感が揺らいでしまいます。その結果、人間関係に対して不信感を持ちやすくなったり、感情をうまく表現できなくなったりすることがあります。
支援の現場では、まず子どものサインに敏感に気づくことが大切です。泣き声や表情、行動の変化は、子どもからの大事なメッセージです。そのサインに応じて「大丈夫だよ」「ここにいるよ」と示すことで、子どもは安心を得て、心の安全基地を確立していきます。
安全基地は、愛着形成の基盤となる最初のステップです。ここでしっかりと「守られている感覚」が育まれてこそ、その後に「安心基地」や「探索基地」といった機能が発揮されていきます。
参考文献
Bowlby J. Attachment and Loss. Basic Books, 1969.
安心基地 ― ポジティブ感情を育む拠点

子どもが心の安定を得るためには、「守られている」という感覚だけでは不十分です。そこに加えて、「一緒にいると落ち着く」「楽しい」「安心する」といったポジティブな感情を経験することが欠かせません。この役割を担うのが「安心基地」です。
安心基地は、子どもが日常生活の中で心地よさや喜びを感じられる場所や人を指します。たとえば、親と一緒に遊びながら笑い合う時間や、寝る前に本を読んでもらい安心して眠れる習慣などがこれにあたります。こうした体験は、子どもの心を落ち着かせ、「自分は受け入れられている」という感覚を強めていきます。
医学的な観点からも、安心感のある関わりは脳に良い影響を与えることが知られています。楽しい体験や安心できる交流の中では、オキシトシンやドーパミンといったホルモンが分泌されます。これらは親子の絆を強めるだけでなく、子どもの情緒の安定や学習意欲を高める効果もあると報告されています(Schore, 2015)。
愛着障害の支援においては、米澤(2022)が指摘するように、「安全基地」よりもまず「安心基地」を築くことが最優先です。なぜなら、安全に守られていても、その関係に「楽しさ」や「心地よさ」がなければ、子どもは大人との関係を積極的に求めようとはしないからです。安心基地を通じて「この人と一緒にいると楽しい」と感じることが、信頼関係を深める第一歩となります。
支援の実際では、特別なことをする必要はありません。子どもと一緒に遊ぶ、小さな成功を一緒に喜ぶ、安心できる日課をつくる——そうしたシンプルな関わりの積み重ねが、子どもにとって大きな意味を持ちます。
安心基地は、子どもの「心の居場所」としての役割を果たし、やがては挑戦や探索を可能にする土台となっていきます。
参考文献
Schore AN. Affect Regulation and the Origin of the Self. Routledge, 2015.
米澤 好史. 愛着の視点からの発達支援―愛着障害支援の立場から―. 発達支援学研究, 2(2), 59-69, 2022.
探索基地 ― 挑戦と成長を支える拠点

子どもは成長の過程で、「自分でやってみたい」「知らない世界をのぞいてみたい」という気持ちを自然に持つようになります。そのとき必要になるのが「探索基地」です。
探索基地とは、子どもが安心できる大人の存在を拠点にしながら、外の世界に出て経験を積み、その経験を持ち帰って受け止めてもらえる場所や人のことを指します。ここで大切なのは、子どもが基地を離れて挑戦し、また戻ってきて安心できるという「往復の動き」がある点です。
たとえば、幼稚園で「初めてのお絵描き発表」を終えた子どもが家に帰ってきて、嬉しそうにその体験を話すとき。大人が「すごいね」「がんばったね」と受け止めることで、子どもの喜びはさらに大きくなります。逆に、挑戦の中で失敗や不安があったときも、「大丈夫だった?」「よくがんばったね」と共感してもらえることで、つらい気持ちが和らぎ、安心につながります。
心理学的研究によれば、このような「経験を共有し、感情を調整してもらう」プロセスを通じて、子どもは自己肯定感を高め、失敗を恐れず挑戦できるようになります(Waters & Cummings, 2000)。探索基地は、単に「挑戦を見守る場所」ではなく、子どもが体験した感情を整理し、成長へとつなげる大切な役割を担っているのです。
支援の現場では、子どもの「報告」をしっかり受け止めることがポイントです。話を途中で遮らず、否定せず、「そうだったんだね」と共感的に耳を傾ける。それだけで、子どもは「また挑戦してみよう」と思えるようになります。
探索基地は、安全基地や安心基地があってこそ機能します。守られている感覚(安全基地)と、心地よさや楽しさ(安心基地)が確立されたうえで、子どもは外の世界へ自信を持って踏み出すことができるのです。
参考文献
Waters E, Cummings EM. A secure base from which to explore close relationships. Child Development, 71(1), 164–172, 2000.
3つの基地の相互関係と支援の実際

これまで見てきた「安全基地」「安心基地」「探索基地」は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に影響し合いながら子どもの発達を支えています。
基地の相互作用
- 安全基地は、恐怖や不安から守られている感覚を子どもに与えます。ここで「守られている」という安心感が芽生えることで、情緒の安定が可能になります。
- 安心基地は、人と一緒にいることの心地よさや楽しさを体験させてくれます。この基地があることで、子どもは大人との関わりを積極的に求めるようになります。
- 探索基地は、守られ、安心できる関係を拠点として外の世界に挑戦し、体験を持ち帰って受け止めてもらえる場です。挑戦と安心の「往復運動」を通じて、子どもは自信と自己肯定感を育てます。
このように3つの基地は連続的に作用し、子どもに「守られている安心感」「人と一緒にいる心地よさ」「挑戦しても帰れる場所」という発達の基盤を提供しています。
「安心基地」を最優先に
米澤(2022)は、愛着障害支援の現場において「安全基地」よりも、まず「安心基地」の構築が最重要であると指摘しています。
なぜなら、守られている感覚があっても、関わりに「楽しさ」や「心地よさ」がなければ、子どもはその関係に自発的に近づこうとしません。逆に「安心基地」が先に確立されると、子どもは大人との関係をポジティブに感じ、そこから「安全基地」や「探索基地」の機能が発揮されやすくなるのです。
家庭でできること
家庭での支援は、特別なことではなく日々の積み重ねが大切です。
- 遊びやスキンシップを通じて、安心できる時間を持つ
- 子どもの小さな成功を一緒に喜び、ポジティブな感情を共有する
- 失敗や不安のときも否定せずに受け止める
こうした関わりは、家庭を「安心基地」として機能させる最も基本的な方法です。
専門的支援の役割
一方で、家庭だけでは十分に支えきれない場合もあります。その際には専門的支援が重要です。
- 心理療法(遊戯療法、親子関係療法など)は、子どもが安心できる環境で気持ちを表現し、養育者との関係を修復・強化する場となります。
- 養育者支援も欠かせません。養育者自身が強いストレスを抱えていると「安心基地」として機能しにくくなるため、保護者支援や相談機関とのつながりが必要です。
支援の最終的な目標は、子どもが信頼できる大人との間に「守られ、安心し、挑戦できる関係性」を築くことです。そしてその第一歩は、何よりも 「安心基地」を整えること にあります。
参考文献
Bowlby J. Attachment and Loss. Basic Books, 1969.
Waters E, Cummings EM. A secure base from which to explore close relationships. Child Development, 71(1), 164–172, 2000.
Zeanah CH, Smyke AT. Disorders of Attachment. In: Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, 2008.
まとめ

愛着の形成には、「安全基地」「安心基地」「探索基地」という3つの基地機能が欠かせません。
- 安全基地は、恐怖や不安から守られているという感覚を与え、心の安定を支えます。
- 安心基地は、人と一緒にいる楽しさや心地よさを育み、対人関係を積極的に求める力につながります。
- 探索基地は、挑戦と安心を往復する体験を通じて、子どもに自信と自己肯定感を育てます。
これらの基地は相互に作用しながら子どもの発達を支えていますが、愛着障害の支援においては「安全基地」よりもまず「安心基地」を築くことが最も重要 です。守られている感覚だけでは不十分で、「この人と一緒にいると楽しい」と思える経験があってこそ、子どもは大人との関係を積極的に求め、信頼関係を深めていくことができます。
家庭でできることは、遊びやスキンシップ、小さな成功を一緒に喜ぶといった日常的な関わりです。さらに必要に応じて、心理療法や養育者支援といった専門的なサポートを取り入れることで、子どもの心の居場所をより確かなものにしていくことができます。
支援のゴールは、子どもが「守られ、安心し、挑戦できる関係性」を持てるようにすることです。その第一歩は、日常の中で安心感を積み重ね、「安心基地」を確立することにあります。

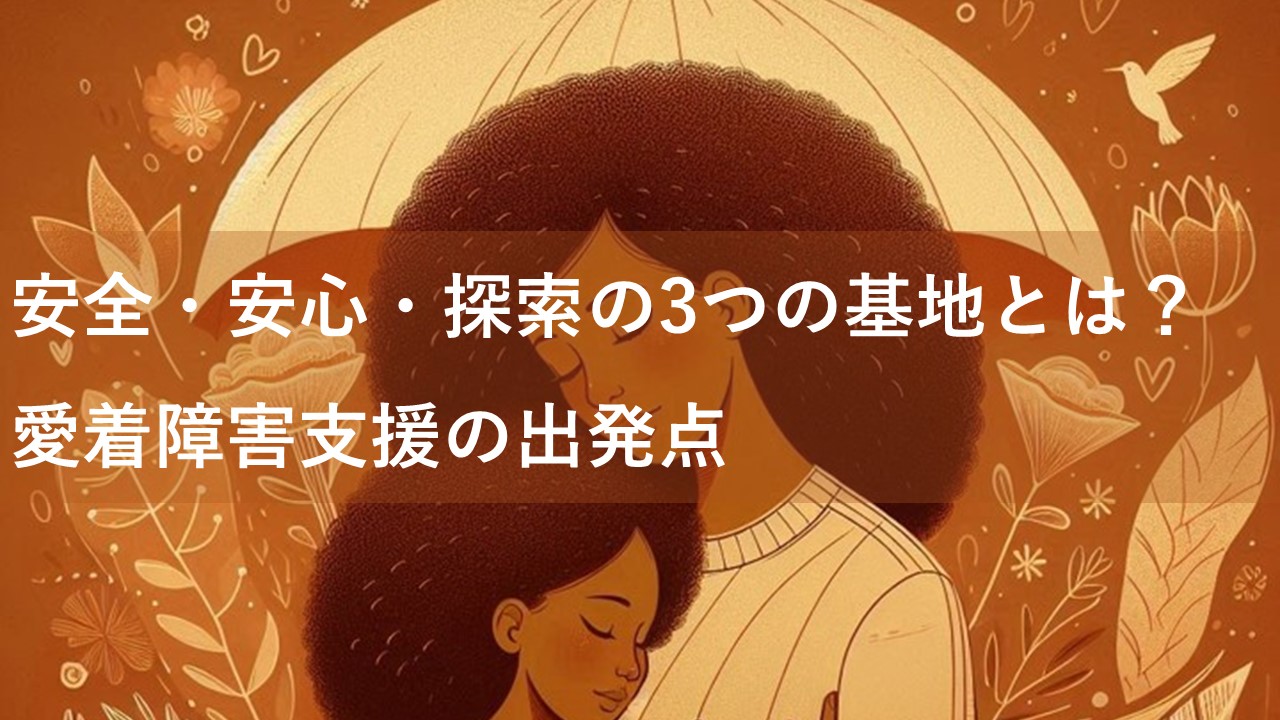


コメント