子どもの「運動の発達」は、ひとつずつの動きを重ねながら、全身の協調やバランス感覚を育てていく大切なプロセスです。
「いつ歩くの?」「走るのが遅いのは大丈夫?」と心配する保護者も多いですが、発達には個人差があります。
この記事では、12か月(1歳)から84か月(7歳)までの運動発達の目安を、わかりやすく月齢別に紹介します。
1. 1歳ごろ(12〜15か月):立つ・歩くのはじまり

この時期の子どもは、立ち上がる・歩き出すという大きな一歩を踏み出します。
- 手をついて立ち上がる
- 2〜3歩ひとりで歩く
- しゃがむことができる
ハイハイから歩行への移行期で、まだ不安定ですが、「立って歩く喜び」を感じる時期です。
※このころは、転んでもすぐ立ち上がれるようになります。
神経生理学的・発達学的背景
この時期の変化は、筋力の増加・姿勢制御の獲得・感覚情報の統合が同時に進むことによります。
- 体幹と下肢筋力の発達:大腿四頭筋や臀筋、腸腰筋などの筋力が増し、立位を保持できる時間が延びます。これにより立ち上がりや短い自立歩行が可能になります。
- 姿勢制御(ポストural control)の獲得:身体の重心(Center of Mass)と支持基底面(Base of Support)を調節する能力が向上し、よちよちでも重心移動を制御できるようになります。
- 感覚統合:前庭(平衡)、固有受容(筋・関節からの位置情報)、視覚が協調して働き、姿勢保持と歩行の安定化を支えます。
- 神経回路の成熟:皮質脊髄路の発達・ミエリン化や脳幹・小脳の協調が進み、筋の協調的な収縮パターン(歩行パターン)が安定してきます。
- 経験依存的学習:自発的な探索行動(つかまって立つ、歩こうとする)を繰り返すことで、運動学習が促進される(シナプス可塑性の強化)。
要するに:筋力・バランス感覚・脳の運動系が同時に育ち、立つこと→歩くことへと自然に移行していきます。
支援・関わりのポイント
保護者や保育者が日常でできる具体的な関わり方です。
安全で挑戦しやすい環境を整える
- 家の床は滑りにくくし、角は保護する。転倒時に受け身がとれるよう柔らかいマットやカーペットも有効。
- 低めの家具や安定した台を置き、つかまり立ちや「つかまって伝い歩き」ができるようにする。
自発的な動きを尊重する
- 無理に立たせて教えるよりも、子どもが自ら立ち上がる機会(興味を引くおもちゃを少しだけ遠くに置くなど)を作る。
- 押し車や大きな箱などを押して歩く遊びは、支持面が安定しない状態でのバランス練習に良い。
感覚入力と筋力を同時に促す
- 裸足での床歩行を増やす(足底感覚が発達を助ける)。
- 屋外で砂や芝など様々な感触の上を歩かせると固有受容感覚が刺激される。
- 日常の抱っこや抱き上げで体幹の保持感覚を育てる。
成功体験を重ねる
- 立てた・歩けた瞬間に笑顔で応援し、達成感を強化する。達成しやすい小さな目標を設定する。
観察すべきサイン
以下が持続して見られる場合は小児科や発達評価の専門家に相談を検討してください。
- 15か月を過ぎても自力で立てない・歩けない。
- 両側に偏った動き(著しい片側の不使用)や筋緊張の極端な偏り(過度の硬さや弛緩)がある。
- 体幹が極端に不安定で座位保持が難しい。
- 常時のつま先歩きや、手の動き・視線が極端に乏しいなど他の発達領域で目立つ遅れが疑われる場合。
(注:個人差は大きく、上記は目安です。気になる場合は早めの相談が安心です。)
すぐに使える家庭での活動例
- つかまり立ち遊び:低いテーブルや丈夫な箱に手をついて立ち上がらせる。
- 押し歩き遊び:押し車や丈夫な箱を押して歩かせる(保護者は近くで安全確認)。
- 段差の昇降体験:低い一段(椅子の高さ程度)に両足で上がり、ゆっくり降りる体験を保護者と一緒に行う。
- 裸足の感触遊び:家の中や園庭で裸足で歩く時間を設ける(安全に配慮)。
- 模倣遊び:親が手を挙げたりしゃがんだりして、子どもに真似させる(模倣運動が発達を促す)。
よくある質問
- Q. 「歩き始めが遅いと心配?」 → A. 個人差が大きいですが、15か月を過ぎても自力歩行が見られない場合は相談を。
- Q. 「靴はいつから?」 → A. 室内は裸足で感覚を育て、屋外では柔らかく支持のある靴を使うと良い。
- Q. 「転びやすいのですが?」 → A. よちよち歩きでは普通です。安全な場所で練習を繰り返すことが重要です。
専門家からのひと言
12〜15か月は「二足歩行への第一歩」を踏み出す重要な時期です。筋力、感覚、脳の運動回路が連携して成長することで、立ち上がりやよちよち歩きが出現します。大切なのは安全で挑戦しやすい環境を用意し、失敗を受け止めながら成功体験を重ねさせること。明らかな心配があると感じたら、早めに専門家に相談しましょう。
2. 1歳半〜2歳(18〜24か月):歩くから走るへ

- 20分ほど歩けるようになる
- 走る、リズムに合わせて体を動かす
- 手すりを使って階段を上る
- 両足でピョンピョンと跳ぶ
体幹や下肢の筋力が育ち、リズム運動や模倣動作が増えるのが特徴です。
神経生理学的・発達学的背景
この時期の変化は、筋力・感覚・中枢神経系の急速な協調発達によって引き起こされます。
- 筋力と体幹の安定化:下肢の筋力(大腿四頭筋、腸腰筋、下腿三頭筋など)と体幹筋が増強され、立位や連続歩行が持続的に行えるようになります。
- 感覚統合の向上:前庭(平衡)・固有受容(筋・関節の位置感覚)・視覚情報が統合され、歩行中の姿勢調整がより精密になります。
- 小脳の役割:小脳は運動の微調整に関与し、リズムに合わせた運動やスムーズな脚運びの習得を助けます。
- 皮質脊髄路と運動野の発達:大脳皮質から脊髄への運動経路(皮質脊髄路)の成熟とミエリン化が進み、より精密な筋収縮が可能になります。ただし、運動の「計画(前頭前野)」や高度な制御はこれから成熟します。
- 運動学習(経験依存性可塑性):同じ動作の反復と成功体験が神経回路を強化します。遊びの中で何度も歩く・走る経験をすることが、神経回路の安定化につながります。
(要するに:筋肉と感覚、そして脳の複数部位が同時に育ち、歩行 → 走行 → リズム運動へとスムーズに移行します。)
支援・関わりのポイント
保護者や支援者が日常で実践できる具体策を科学的に裏付けつつ示します。
安全で刺激的な環境を用意する
- 転倒しても安全な床やマット、角の丸い家具を用意する。
- 屋外散歩を増やし、20分程度の継続的歩行や段差のある道(危険でない範囲)での歩行経験を提供する。
運動経験を“自然な遊び”で増やす
- 押し車や大きめの箱を押して歩く遊び(抵抗があることで筋力とバランスを鍛える)。
- 音楽に合わせて体を動かす(リズム遊び、簡単な体操の模倣)。
- 低めの段差での昇降(手を支える)を繰り返す練習。
運動学習を促す工夫
- 成功体験を重視(達成したら褒める、達成しやすい課題設定)。
- 片側に偏らないよう両側の動作を促す(左右均等に誘導するおもちゃ配置など)。
観察すべきサイン(受診の目安)
以下が継続して見られる場合は専門家(小児科・発達外来・理学療法士)に相談を検討:
- 18か月を過ぎても自力で歩けない、著しい左右差がある。
- 持続的な極端なつま先歩き(常態化している)。
- 動きに著しいぎこちなさ・鉛直性の偏り・ある特定の動作を全くしない(例:走らない、ジャンプしない)など。
具体的な家庭での活動例
頻度と目安を示します(医学的助言の代替ではありません)。
- 毎日:屋外を含む自由遊び(15〜30分) — 歩行や走行の機会を確保。
- 週に数回:リズム遊び(音楽に合わせて手足を動かす、短時間でOK) — 模倣とタイミング学習に有効。
- 日常の中で:階段昇降の練習(手をつなぐ・手すり使用で安全に) — 筋力と段差感覚の訓練。
- 遊具遊び:押し車、坂道をゆっくり下りる(保護者付き)、小さな障害物をまたぐ遊びなど。
よくある質問
- Q. 「走り出したら止められない」 → A. まだブレーキ(減速・方向変換)が未熟なので、安全な場所で練習を。
- Q. 「ジャンプはいつ?」 → A. 両足でピョンピョン跳ぶのは24か月前後に現れることが多い(個人差あり)。
- Q. 「靴はどうする?」 → A. 屋内では裸足で感覚入力を、屋外では適切なサポートのある柔軟な靴を推奨。
専門家からの一言
1歳半〜2歳は「歩く」から「走る」へ、動きの幅が急速に拡大する重要期です。遊びを通じた繰り返しの経験が神経回路を強化し、バランス・筋力・感覚統合を育てます。過度に心配する前に、安全で挑戦しやすい環境を整えて、子どもの自発的な動きを支援しましょう。気になる点があれば、早めに専門家に相談するのが安心です。
3. 2歳半〜3歳(30〜36か月):全身のバランスが整う

- 滑り台や三輪車を使う
- 階段を交互の足で上る
- 合図に合わせて走り出す
遊具を使った遊びが増え、体のバランス感覚とリズム感が急速に発達します。
遊びながら「順番」「ルール」を学び始める時期でもあります。
神経生理学的・発達学的背景
この時期は「走る・止まる・跳ぶ」といった運動の制御機能が急激に発達します。
背景には、大脳・小脳・基底核・感覚統合機能の成熟が関係しています。
- 小脳と前庭系の発達
→ バランス調整と動作のリズム形成がさらに安定し、走行時の軸のブレが少なくなります。 - 基底核の機能向上
→ 運動の開始・停止・切り替えを担う部位が成熟し、急停止や方向転換など「運動の切り替え」が可能になります。 - 前頭葉(運動前野)の関与
→ 動作の「見通し」や「順序立て」ができるようになり、段差を降りる・タイミングを合わせてジャンプするなどの複合動作が増えます。 - 感覚統合の精度の向上
→ 視覚・前庭・固有受容の統合がスムーズになり、「今、体がどこにあるか」という身体図式(ボディイメージ)が育ちます。
(要するに:この時期は“動きの速さ”ではなく、“動きを止めたり、切り替えたりできる”ようになることが大きな発達です。)
支援・関わりのポイント
「止まる」「変える」を経験できる遊びを
- 走るだけでなく、止まる・方向を変えるなどの“運動のコントロール”を遊びの中に取り入れる。
- 例:「よーいドン」で走り出し、「ストップ」で止まる遊び。鬼ごっこ(簡易版)も有効。
ジャンプ・バランス系遊びを少しずつ
- 低い段差から両足でジャンプする経験を繰り返す。
- バランス感覚を高めるため、マットの上や柔らかい芝生などで安全に練習。
- 小さな平均台・一本線の上を歩く遊びも有効。
感覚統合の発達を促す工夫
- 足裏感覚を多様な素材で刺激(芝生・砂・マット・木の床など)。
- リズム遊び(手拍子+足踏みなど)を取り入れると、小脳・基底核系の協調を促進。
観察すべきサイン
- 走るときに極端に転倒が多い・左右差が強い。
- ジャンプが出現しない、または一貫してつま先立ち歩行が続く。
- 歩行・走行時に身体の軸が大きく左右に揺れる場合は専門家相談を検討。
具体的な家庭での活動例
- 走って止まる遊び:「よーいドン → ピタッ」で止まる。タイミング合わせの遊び。
- 低段差ジャンプ:5〜10cm程度の段差から両足ジャンプ。マットなど安全な場所で。
- バランス遊び:地面に線を引き、その上を歩く/クッションの上を歩く。
- リズムステップ:音楽に合わせて足踏みをする。止まる・進むの切り替え練習にもなる。
よくある質問
- Q. 「うちの子、止まれないんです…」 → A. 方向転換・急停止はこの時期に育つ能力。安全な環境で“止まる遊び”を多く取り入れていきましょう。
- Q. 「片足立ちはいつできる?」 → A. 安定した片足立ちは3歳後半〜4歳ごろ。今は両足のジャンプと走行制御が中心です。
- Q. 「転びやすいのは心配?」 → A. 個人差はありますが、極端な転倒や一方向の偏りがある場合は早めの相談をおすすめします。
専門家からの一言
2歳半〜3歳は「走る」だけでなく、「止まる」「変える」「ジャンプする」など、動きの制御が育つ重要なステージです。神経系の成熟と感覚統合の精度向上がこの発達を支えています。焦らず、子どもが楽しめる遊びの中で自然に動きのバリエーションを増やしていくことが最も効果的です。
4. 3歳半〜4歳(42〜48か月):跳躍・回転の動きが登場

- 階段から飛びおりる
- ケンケンやでんぐり返しをする
このころになると、脚力や空間感覚がぐっと高まります。
「自分の体を思い通りに動かす」ことができ始め、運動遊びが楽しくなります。
神経生理学的・発達学的背景
この時期の運動発達は、粗大運動から巧緻な制御運動へと移行していく重要な転換期です。
- 🧠 小脳と前庭感覚のさらなる成熟
→ バランス制御と身体回転中の空間認知が向上。でんぐり返しなどの回転運動が可能になる。 - 🧠 基底核と運動前野の協調
→ ケンケン跳びのような“リズム+力の制御”を伴う複合運動が可能になる。 - 🧠 感覚統合(特に前庭感覚と固有受容感覚)の発達
→ 空間内で身体がどのように回転・移動しているかを把握し、自分で修正できるようになる。 - 🧠 前頭葉の機能発達
→ 動きの「順序立て」や「見通し」がさらに強化され、1つの動作の中で複数の要素を組み合わせられる。
例:走って → 跳ぶ → 着地して止まる、など。
支援・関わりのポイント
🔸 安全な環境で大胆に動く体験を
- 2〜3段からのジャンプや軽い回転運動を楽しめる環境を整える。
- 高さを少しずつ上げながら、恐怖感ではなく「できた!」の感覚を育てる。
- 転倒・着地失敗も発達の一部。柔らかい地面やマットが有効。
🔸 リズムと方向性を育てる
- ジャンプや回転を音楽・リズム遊びに組み込み、タイミングを合わせる練習を取り入れる。
- ケンケン跳びは「片足バランス+リズム」の複合スキルなので、無理に教えるより、遊びの中で自然に出現させるのが◎。
🔸 感覚統合を意識した関わり
- 回転(でんぐり返し)やブランコなどで、前庭感覚の刺激を十分に経験させる。
- 片足立ち・ジャンプ・回転といった動きは、空間認知と姿勢制御を育てる上で非常に重要。
具体的な家庭・園での活動例
- 2〜3段からのジャンプ遊び:段差や踏み台を活用し、両足でジャンプして着地。
- ケンケンごっこ:片足でピョンピョン跳ねる遊び。転倒しても安全な場所で。
- でんぐり返し:マットの上で前転。頭を守りながら勢いを楽しむ。
- リズムジャンプ:音楽や歌に合わせてジャンプやステップを繰り返す。
観察すべきサイン
- 高い段差からのジャンプを極端に怖がる、または不安定さが強い。
- ケンケン跳び・回転動作が長期間出現しない。
- バランス保持が弱く、姿勢制御が難しい。
- 激しい動きへの過敏(感覚過敏)または過剰な追求(感覚探求)が強い。
→ これらは感覚統合や神経運動制御の発達と関連するため、必要に応じて専門家の評価を検討します。
専門家からの一言
3歳半〜4歳は、“動きに勢いと方向性”が生まれる時期です。
ジャンプ・回転・片足跳びといったダイナミックな動きは、前庭感覚や空間認知の発達を促す重要な経験です。
大人が過剰に介入するよりも、安全な環境を整え、子ども自身の「やってみたい!」を支えることが何より大切です。
5. 4歳半〜5歳(54〜60か月):リズム運動と全身協調

- スキップをする
- ブランコを自分でこぐ
- ジャングルジムに登る
複雑な動きを組み合わせることができるようになり、運動の持続力と協調性が育ちます。
遊びの幅も広がり、「挑戦」が楽しい時期です。
神経生理学的・発達学的背景
この時期は、粗大運動と感覚統合のさらなる成熟が見られ、全身の協調運動が安定します。
- 🧠 小脳の協調運動機能の発達
→ 片足跳びやスキップ、ブランコの立ち漕ぎなど、リズムとバランスを同時に使う運動が可能になる。 - 🧠 前庭・固有受容感覚の統合
→ 身体の傾きや回転、上下動の情報を正確に把握できるため、遊具の上での動きやジャンプ・回転が安定。 - 🧠 前頭葉・運動前野の発達
→ 複数の動作を順序立てて計画する能力が向上。
→ 「登る → 渡る → 滑る」などの複合動作がスムーズにできる。 - 🧠 感覚統合の精度向上
→ 視覚・前庭・体性感覚が統合されることで、複雑な動きでもバランスを崩しにくくなる。
支援・関わりのポイント
🔹 スキップやリズム運動を楽しむ
- 音楽に合わせたステップ・ジャンプ遊びを取り入れる。
- スキップはリズム感と全身協調性を育む重要な運動。
🔹 全身を使った遊具遊び
- ブランコで立ち漕ぎ、ジャングルジムで登る・渡る遊び。
- 手足・体幹を統合した運動を経験させる。
- 安全な場所で高低差や傾斜を体験させることで、姿勢制御・バランス感覚が向上。
🔹 複合動作の練習
- 「登る → 渡る → ジャンプして降りる」など、動作の連続性を楽しめる遊び。
- 「止まる」「方向を変える」「リズムに合わせる」を同時に行う課題が発達を促す。
具体的な家庭・園での活動例
- 音楽に合わせてスキップやステップをする
- 立ったままブランコを漕ぐ遊び
- ジャングルジムや平均台を使った移動遊び
- 複数の運動を組み合わせたゲーム(登る・渡る・ジャンプ)
観察すべきサイン
- スキップや複合動作ができない・極端に不安定
- 遊具での全身運動が極端に苦手
- 動作がぎこちない・左右差が大きい
→ 必要に応じて、運動発達や感覚統合の専門家に相談を検討。
専門家からの一言
4歳半〜5歳は、全身の協調性が大きく向上する時期です。
スキップ、ブランコの立ち漕ぎ、遊具での複合動作など、全身を統合して使う運動を経験することが、運動技能だけでなく、空間認知やバランス感覚の発達にも直結します。
安全に配慮しつつ、子ども自身が「やってみたい!」と思える遊びをたくさん提供することが大切です。
6. 6歳ごろ(72か月):集団あそびへの発展

- ブランコを立ってこぐ
- 自転車(補助輪付き)に乗る
- リレーで走る
運動能力が安定し、集団でのルールあそびが可能になります。
仲間と息を合わせる経験が、社会性の発達にもつながります。
神経生理学的・発達学的背景
6歳ごろの子どもは、運動技能だけでなく社会性と運動の統合が進む時期です。
- 🧠 小脳の成熟による運動精度向上
→ ジャンプ、方向転換、タイミング調整などの運動が滑らかになる。 - 🧠 基底核と前頭前野の協調による計画運動
→ 走る・止まる・投げる・蹴るなどの複数動作を同時に組み合わせられる。
→ 集団遊びでの役割分担やルールの理解に対応可能。 - 🧠 前庭感覚と固有受容感覚の統合の安定化
→ ブランコや自転車のバランス操作が安定。
→ 仲間と向かい合って揺れたり、道具操作のタイミングを合わせることが可能。 - 🧠 社会性と運動認知の統合
→ 友達とタイミングを合わせる、順番を守る、ルールを理解するなど、認知・社会性と運動の結合が進む。
支援・関わりのポイント
🔹 集団あそびで協調性を育てる
- 簡単なルールのリレーやボール遊びを取り入れる。
- 仲間と一緒に動くことで、タイミング調整能力と社会性を同時に育てる。
🔹 道具操作と全身運動を統合
- 補助輪つき自転車でペダル・ハンドル・バランスを統合する運動。
- ブランコやジャングルジムで、仲間と遊びながらタイミングやバランスを取る練習。
🔹 遊びを通した運動認知の向上
- 「順番を守る」「合図で動く」「仲間と位置を合わせる」といった遊びを取り入れる。
- 速度や力加減、方向を仲間に合わせる経験を多く積むことで協調性が向上。
具体的な家庭・園での活動例
- リレーごっこ(2〜3人〜数人のグループ)
- 補助輪つき自転車でのレースや移動遊び
- ブランコでの向かい合い漕ぎ
- チームでのボール遊び(蹴る・投げる・パスする)
- 数人での鬼ごっこやかけっこ
観察すべきサイン
- 仲間とタイミングを合わせられない
- 道具操作(自転車、ブランコ)が極端に不安定
- 集団あそびで極端に消極的・拒否的
→ これらが見られる場合は、運動協調性や感覚統合、社会性の発達の観点で注意深く観察することが推奨されます。
専門家からの一言
6歳ごろは、運動スキルと社会性が結びつく時期です。
集団遊びや道具を使った活動を通して、タイミング調整・バランス・全身協調性・ルール理解・仲間との協調性が同時に発達します。
大人は安全に配慮しながらも、自由に楽しめる環境を提供することで、身体能力と社会性の両方を育むことが可能です。
7. 6歳半〜7歳(78〜84か月):巧緻性とスポーツ的要素の発達

- なわとび、ボールつき、鉄棒などの複雑な運動
- チーム遊びや模倣ゲームを楽しむ
このころには、巧みな運動制御が可能となり、学校体育への準備段階に入ります。
身体の成長だけでなく、ルール理解や協調性も発達のカギです。
神経生理学的・発達学的背景
6歳半〜7歳では、運動の質・精度・計画性が大きく向上します。
- 🧠 小脳・基底核の成熟による巧緻運動の向上
→ 縄跳び、ボール操作、鉄棒・平均台の動作で、タイミング・筋力・リズムを統合。 - 🧠 前頭前野と運動前野の協調による複合動作制御
→ 「走る→投げる→受け取る」などの連続動作や、ルールの理解と運動の同時遂行が可能。 - 🧠 感覚統合の安定化
→ 前庭・体性感覚・視覚情報を統合し、空間把握・姿勢制御・力加減の調整が可能。
→ 高度なバランス運動(平均台、ぶら下がり、ブランコ立ち漕ぎ)が安定する。 - 🧠 社会性と運動認知の統合
→ 仲間とルールを共有しながら遊ぶことで、協調性・役割理解・チームワーク能力が発達。
支援・関わりのポイント
🔹 巧緻性を楽しむ活動
- 縄跳びやボール操作を遊びに取り入れる
- 平均台や低鉄棒での動作を「挑戦・成功体験」として経験させる
🔹 スポーツ的・協力遊びの導入
- 長縄での大縄跳び、チームリレー、簡単なボールゲーム
- ルールを理解し、仲間と動きを合わせる遊びを通して協調性を育む
🔹 運動+認知・社会性の統合
- 動作の順序・タイミング・仲間との関係を同時に意識する遊びを取り入れる
- 「順番を守る」「タイミングを合わせる」「声をかける」など、社会性の学びも同時に獲得
具体的な家庭・園での活動例
- 縄跳びの個人練習・二人以上での大縄跳び
- ボールを使ったパスゲームやドリブル
- 平均台で落ちないように渡るゲーム
- 低鉄棒で前まわり、うんてい、太鼓橋でのぶら下がり遊び
- ルールのあるリレーやチーム競技
観察すべきサイン
- 縄跳びやボール遊びで動作がぎこちない、極端に苦手
- 協調運動(平均台、鉄棒、ぶら下がり)が安定しない
- 集団遊びでルール理解が難しい、仲間と協調できない
→ 必要に応じて、運動協調性・感覚統合・社会性の発達の観点で評価。
専門家からの一言
6歳半〜7歳は、巧緻性とスポーツ的要素を同時に獲得する時期です。
縄跳び、ボール操作、鉄棒や平均台などの運動は、運動神経だけでなく、感覚統合、協調性、社会性の発達にも直結します。
遊びの中で成功体験を積ませ、ルールや仲間との関わりを楽しめる環境づくりが大切です。
🧭 子どもの運動発達 早見表(12〜84か月)
| 月齢 | 主な発達の動き | できるようになること(例) | 発達のポイント(専門家コメント) |
|---|---|---|---|
| 12か月 | 立つ・歩きはじめ | 手をついて立ち上がる、2〜3歩歩く | 下肢の筋力とバランス機能が発達し始める |
| 15か月 | 歩行の安定 | しきいをまたぐ、ちょこちょこ歩く | 転倒を繰り返しながらバランス調整を学ぶ |
| 18か月 | 歩行の持久性 | 20分ほど歩ける、走る、階段をのぼる | 小脳と運動野の協調が進む |
| 21か月 | 高さへの挑戦 | つま先歩き、高い所からジャンプ | 前庭感覚の発達が活発 |
| 24か月 | 跳ぶ・ぶら下がる | 両足ジャンプ、ぶら下がる | 下肢の筋力と体幹の安定性が向上 |
| 30か月 | 遊具遊び | 滑り台、階段の昇降(三輪車を押す) | バランス感覚と動作の模倣力が育つ |
| 36か月 | バランスとスピード | 三輪車に乗る、階段交互上がり | 感覚統合が進み、スムーズな運動が可能に |
| 42か月 | 高さと距離の感覚 | 2〜3段の階段からジャンプ | 空間認知の精度が高まる |
| 48か月 | 複雑な動作 | ケンケン、でんぐり返し | 運動の多様性が広がる |
| 54か月 | リズム・協調性 | スキップ、仰向け滑り台 | 両側の協調と運動プランニング |
| 60か月 | 自立的な遊び | ブランコをこぐ、ジャングルジム | 前頭前野と運動野の連携が高まる |
| 72か月 | 集団あそび | リレー、自転車、ぶらんこ立ちこぎ | 協調運動と社会性が発達 |
| 78か月 | 巧緻性・スピード | なわとび、ボールつき、鉄棒 | タイミング制御と筋力持久力が向上 |
| 84か月 | チームスポーツ的運動 | 野球ごっこ、長縄、鉄棒逆さ | 感覚運動統合と戦略的行動が可能に |
まとめ
1歳半から7歳ごろにかけて、子どもの運動は「歩く・走る」から「跳ぶ・回る」「道具を使った協調運動」「集団遊びや巧緻性の発達」へと段階的に進みます。
この期間は、筋力やバランスだけでなく、感覚統合・空間認知・リズム感・協調性・社会性といったさまざまな能力が複合的に育つ重要な時期です。
遊びや運動を通じて、子どもは自分の体を自在に使う喜びを学ぶだけでなく、仲間との関わり方やルールを守る力も自然に身につけます。
大切なのは、「安全で楽しい環境」と「肯定的な声かけ」です。失敗しても挑戦できる経験を重ねることで、運動能力だけでなく自信や自己肯定感も育まれます。
これからも、子どもの発達段階に合った運動遊びを意識し、全身を使った遊びや集団遊びの機会をたくさん提供してあげましょう。
小さな一歩一歩の成長が、将来の運動能力や生活スキルにつながる大切な土台になります。

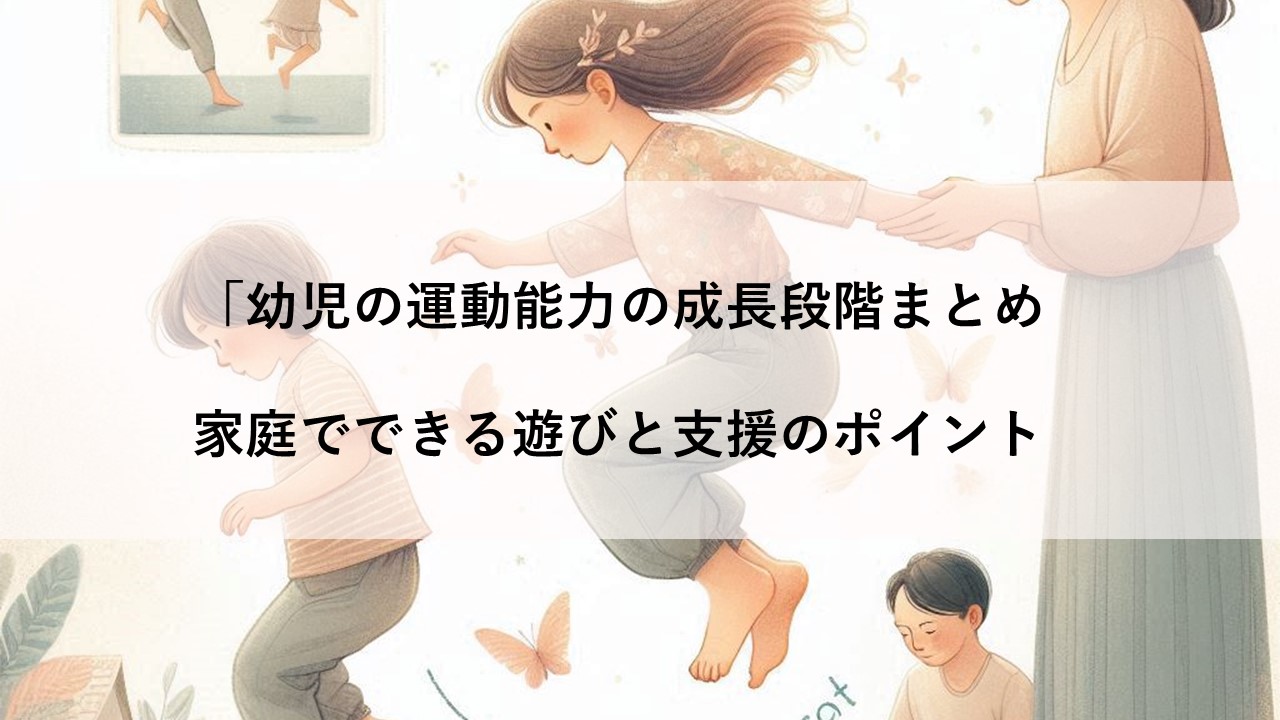
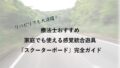

コメント