子どもの心の発達を理解するうえで欠かせないのが「愛着理論」です。
愛着とは、子どもが「この人と一緒なら安心できる」「困ったときはここに戻れる」と感じられる特別なつながりのこと。これは、心の発達の土台となる大切な仕組みです。
ただし、現場ではよく「発達障害の支援」と「愛着障害の支援」が混同されがちです。発達障害の場合は環境の工夫や対応を統一することで効果が出やすい一方、愛着障害ではそれだけではうまくいかないことがあります。なぜなら、支援や関わりが「心に入りにくい」「受け取ってもエネルギーとして貯められない」という特徴があるからです。
この特徴をわかりやすく説明するのが、「愛情の器モデル」です。子どもの心を「器」にたとえ、入口が狭ければ支援が入りにくく、底に穴があれば安心感がたまらない。そんなイメージで、愛着障害の子どもの理解と支援の道しるべとなっています。
この記事では、この「愛情の器モデル」と「3つの基地機能」をもとに、愛着障害の支援について、わかりやすく整理していきます。
愛着理論と愛着障害の基礎

愛着理論の出発点
イギリスの精神科医ジョン・ボウルビィは、子どもが特定の養育者を「ここに戻れば大丈夫」と感じる**安全基地(secure base)**を築くことが、心の発達の土台だと述べました。エインズワースの観察研究(ストレンジ・シチュエーション)では、この安全基地がどのように機能しているかが実証的に示されています。ポイントは3つだけ覚えておけばOKです。
- つながりは「生き延びるための適応的な仕組み」
- 安心できる関係は、探索意欲や感情の自分調整を育てる
- 不安定な関係は、脳のストレス反応を過敏にしやすい
愛着障害で起こりやすい現象
現場でよく聞くのが、
- 「関わっても受け止められない(その場で拒否・逸脱が起きやすい)」
- 「受け止めても貯められない(次の活動の元気=エネルギーに変わらない)」
という2つの壁です。
背景には、脳の**脅威検知(扁桃体)**が過敏になっていたり、ストレス応答(HPA軸)が揺れやすかったり、“人は信頼できる”という内的モデルが育ちにくいことが関係します。結果として、支援の言葉や優しさが「危険かもしれない」「今だけかも」と誤検知され、心の中に定着(記憶の上書き)しにくいのです。だから、支援が積み上がらないように見えます。
誤解しやすいポイント
- 不安定な“愛着スタイル”(日常のゆらぎ)と、臨床的な“愛着障害”(RAD/DSED等)は別物です。診断が必要なケースは、医療・福祉・教育の専門機関と連携して評価します。
- 発達障害(ASD/ADHDなど)では、環境調整の統一だけで改善する場面が多い一方、愛着障害では**「安心の体験」自体を丁寧に積み重ねて**、受け止めやすく・貯めやすくする工程が必要です。
次につなげる視点:愛情の器と3つの基地
この“受け止め・貯め”の難しさを、臨床で共有しやすくしたのが米澤好史先生の**「愛情の器モデル」です。器の入口が狭い**(受け入れにくい)、底に穴がある(貯めにくい)という比喩で、支援のどこを整えるかを可視化します。さらに、安心基地 → 安全基地 → 探索基地の順で土台を作ると、器の入口が広がり、底の穴もふさがりやすくなります。
詳細な分類や評価法は別記事に譲り、ここでは「なぜ支援が入らず、なぜ貯まらないのか」を理解する地図として押さえておけば十分です。
参考文献
Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment. Lawrence Erlbaum.
Zeanah, C. H., & Gleason, M. M. (2015). Annual Research Review: Attachment disorders in early childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(3), 207–225.
Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 145–173
Hostinar, C. E., Sullivan, R. M., & Gunnar, M. R. (2014). Psychobiological mechanisms of social buffering of the HPA axis. Social Neuroscience, 9(5), 512–523.
Tottenham, N. (2012). Human amygdala development in the absence of expected caregiving. Developmental Psychobiology, 54(6), 598–611.
米澤 好史(2022)「愛着の視点からの発達支援—愛着障害支援の立場から—」『発達支援学研究』2(2), 59–69.
米澤 好史『「愛情の器」モデルに基づく愛情修復プログラム—発達障害・愛着障害現場で正しくこどもを理解し、こどもに合った支援をする』福村出版.
「愛情の器モデル」とは

ポイント
- 子どもの心は、愛情・支援を**受け止めて貯めていく「器」**として理解できる。
- 入口が狭いと、せっかくの関わりが入りにくい。
- 底に穴があると、その場で生まれた安心や嬉しさが貯まらない。
- 目的は、入口を広げ、底の穴をふさぎ、愛情を蓄えられる状態をつくること(米澤)。
なぜ「器」にたとえるのか
現場でしばしば起こるのが、
- 「関わっても受け止められない」
- 「受け止めても次の元気(エネルギー)に変わらない」
という二つの壁です。
これは“性格の問題”ではなく、心の受け止め装置がうまく働きにくい状態だと考えると、支援の打ち手が見えてきます。「愛情の器モデル」は、この受け止め装置の状態を入口と底というシンプルなイメージで共有できるようにしたものです。
科学的にみると「入口」と「底」はこう対応する
- 入口が狭い(入りにくい)
予測不能さや警戒心が強いと、脳の扁桃体(脅威検知)が過敏になり、ストレス応答(HPA軸)が揺れやすくなります。すると、相手の優しささえ「本当に大丈夫?」と曇って見えやすく、支援の言葉や関わりが心に入る前に跳ね返されやすい(回避・反発・フリーズなど)ことがあります。
→ 安心の体験(予測できる関わり・温かな同調・社会的な“緩衝”)は、この過敏さを和らげることが研究で示されています。 - 底に穴がある(貯まりにくい)
慢性的なストレスは、安心や喜びの記憶を長持ちさせにくい方向に働くことがあります。安心の出来事があっても、すぐに不安が上書きしてしまい、ポジティブ感情が次の行動のエネルギーに変わりにくい。
→ くり返しの安心体験と共同での感情の言語化(ラベリング)は、前頭前野による感情調整を助け、ポジティブ経験の“定着”を後押しします。 - 広がる・ふさがる手がかり
オキシトシンなどの社会的結びつきに関わるシステムは、温かい相互作用の積み重ねで高まり、扁桃体反応の抑制や対人安心感の向上に関与することが示唆されています。これは、入口を広げ、底の穴をふさぐ生物学的な土台にあたります。
モデルを現場でどう使うか
- 入口を広げる
- 予測可能性:声かけ・ルーティン・約束の順序を一定に。
- 同方向の活動:並んでお絵描き・工作・料理など、「向き合う」より横に並ぶ関わりから。
- 先手の支援:要求が出る前に、キーパーソンが安心を“先回り”で提供(主導権=安全感)。
- 底の穴をふさぐ
- 感情のラベリング:大人が「いま楽しいね、落ち着くね」と言い当てる(問い詰めはしない)。
- 短く・頻回に・成功で終える:ポジティブ体験を小分けに貯める設計。
- 記録と共有:同じ良い体験を再現しやすいようにメモや写真で可視化。
- 注ぐ人(キーパーソン)を決める
- 愛着障害では、**特定の人(キーパーソン)**を中心に「支援はその人から始まり、その人に戻る」流れをつくることが重要。
- これにより、愛情の“つまみ食い”(その場限りの関わりの渡り歩き)を防ぎ、器の入口・底を安定して整えられます。
※「安全より先に安心基地」を整えることが、結局は安全を高め、やがて探索基地(自立に向けた挑戦)の機能を引き出します。モデルの実践は安心 → 安全 → 探索の順が原則です。
参考文献
米澤 好史『「愛情の器」モデルに基づく愛情修復プログラム—発達障害・愛着障害現場で正しくこどもを理解し、こどもに合った支援をする』福村出版.
米澤 好史(2022)「愛着の視点からの発達支援—愛着障害支援の立場から—」『発達支援学研究』2(2), 59–69.
Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment. Lawrence Erlbaum.
Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 145–173.
Hostinar, C. E., Sullivan, R. M., & Gunnar, M. R. (2014). Psychobiological mechanisms underlying social buffering of the HPA axis. Social Neuroscience, 9(5), 512–523.
Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. Hormones and Behavior, 61(3), 380–391.
Tottenham, N. (2012). Human amygdala development in the absence of species-expected caregiving. Developmental Psychobiology, 54(6), 598–611.
3つの基地機能

愛着形成には次の3つの基地機能が必要です(米澤 2022)。
① 安全基地
恐怖、不安、怒り、悲しみなどのネガティブな感情から守ってくれる存在。困ったときに「ここに戻れば守られる」「助けてもらえる」と感じられる拠り所です。
② 安心基地
落ち着く、ほっとする、楽しくなるなどポジティブな感情を生じさせる存在。一緒にいることで心が安らぎ、良い感情が生まれる場を指します。
③ 探索基地
基地から離れて外で経験したことを基地に戻って報告すると、その経験から生じたポジティブな感情をさらに増やしてくれ(もっと嬉しくなる)、逆にネガティブな感情を減らしてくれる(なくしてくれる)存在です。体験を持ち帰って共有することで学びと安心が増幅されます。
支援の順序:「安心 → 安全 → 探索」
米澤(2022)が強調しているのは、支援には順序があるということです。
まず安心基地をつくり、次に安全基地、そして最終的に探索基地へとつなげていく流れが大切です。
現場で「支援をしても積み上がらない」「その場は受け止めても次につながらない」と感じることがありますが、多くの場合、安心基地の欠如が関係しています。安心がなければ、支援は子どもの心に届かず、積み上がらないのです。
科学的背景
繰り返しの安心的な関わりは、脳と身体のストレス反応(HPA軸)を落ち着け、扁桃体の過敏な警戒を和らげると報告されています。こうして「人とつながっても安全だ」という感覚が育ちやすくなります。
逆に安心が得られないと、支援や好意が心に入りにくい「跳ね返し」の状態が続きます。安心の経験を言葉で整理・共有(ラベリング)したり、同じ方向での活動を繰り返したりすることは、ポジティブ体験を記憶として残し、探索に向かうエネルギーへとつながっていきます。
参考文献
米澤 好史. 愛着の視点からの発達支援―愛着障害支援の立場から―. 発達支援学研究. 第2巻 第2号, 59–69, 2022.
米澤 好史. 『「愛情の器」モデルに基づく愛情修復プログラム—発達障害・愛着障害現場で正しくこどもを理解し、こどもに合った支援をする』. 福村出版.
Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment. Lawrence Erlbaum.
Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 145–173.
Hostinar, C. E., Sullivan, R. M., & Gunnar, M. R. (2014). Psychobiological mechanisms underlying social buffering of the HPA axis. Social Neuroscience, 9(5), 512–523.
実践的な支援のポイント

愛着障害の支援では、単に関わるだけでは不十分です。ここでは、支援を積み上げるために重要なポイントを整理します。
キーパーソンの設定
愛着障害の子どもには、特定の愛着対象となる人物、いわゆるキーパーソンを決めることが必須です。
支援は、キーパーソンを中心に始まり、キーパーソンに戻る流れで行うことで、子どもが関わりたい人だけを選んで一時的に愛情を受け取る「愛情のつまみ食い現象」を防ぐことができます。
先手の支援
子どもが要求する前に、キーパーソンが積極的に愛情や安心を提供することが大切です。
後から応える「後手の支援」では、子どもの要求がエスカレートしやすくなる「愛情欲求エスカレート現象」が起きやすくなります。
感情のラベリング支援
子どもと一緒に活動する際、ポジティブな感情を言葉で確認する支援が有効です。
重要なのは、子どもに感情を自分で答えさせるのではなく、大人が感情を言い当てること。
たとえば、お絵描きや工作、料理などの一緒に行う並行活動で、「楽しいね」「落ち着くね」と声をかけながらポジティブ感情を確認します。
安心基地づくりを優先
愛着障害支援では、ネガティブ感情を守る「安全基地」から始めるよりも、まずポジティブな感情を確認できる場(安心基地)を整えることが重要です。
安心基地の構築が、次の安全基地や探索基地につながる土台となります。
関係性の橋渡し
定型発達の子どもでは、愛着対象が一人いれば自然に周囲との関係も広がります。
しかし愛着障害の子どもでは、キーパーソンを軸にして、他者との関係を意図的に支援する必要があります。
キーパーソンが中心となって、他者とのつながりを橋渡しすることで、子どもが安全に人間関係を広げていけるのです。
参考文献
米澤 好史. 『「愛情の器」モデルに基づく愛情修復プログラム―発達障害・愛着障害現場で正しくこどもを理解し、こどもに合った支援をする』. 福村出版.
米澤 好史. 愛着の視点からの発達支援―愛着障害支援の立場から―. 発達支援学研究. 第2巻 第2号, 59–69, 2022.
科学的に見た「器」と「基地」

「愛情の器」=脳の発達・ストレス耐性のメタファー
子どもが安心して成長するためには、「愛情の器」が十分に育まれることが重要です。この「器」は、子どもの脳の発達やストレス耐性を支える内的資源を象徴しています。具体的には以下の脳機能と関連します。
- HPA軸の調整:ストレスに対する反応をコントロールし、適応的な行動を支える
- 扁桃体・前頭前野の発達:感情の認識や制御、判断力に関わる領域の成熟
- オキシトシンの分泌:安心感や社会的な結びつきを促進するホルモンの分泌
これらは子どもの内面の「器」として、外的環境からの刺激や支援に対して柔軟に反応できる力を育てます。
「基地機能」=養育環境の働きを神経発達に対応させた理解
「基地」とは、子どもが安心して外の世界に挑戦できるための養育環境のことです。この基地は、神経発達の観点から見ると次のような役割を持っています。
- 安全な環境の提供によるストレスの軽減
- 適切な愛着関係を通じた情緒の安定
- 学習や社会的経験のサポート
器と基地の相互作用
「愛情の器(内的資源)」と「基地(外的支援)」は切っても切れない関係にあります。十分に育まれた器は、基地からのサポートをより有効に活用でき、逆に安定した基地は器の発達を促進します。この相互作用によって、子どもは情緒的に安定し、ストレスに強く、社会的に適応する力を育むことができます。
まとめ

実践の核心となるのは、まず子どもにとっての「安心基地」をつくり、そこから「安全基地」「探索基地」へとつなげていくことです。その際、キーパーソンを中心にしたチーム支援を構築し、支援が子どもにとって一貫性のある流れになるよう工夫することが大切です。
また、「先手の支援」によって子どもが安心を先取りできるようにし、活動の中で感情をラベリングしながら「楽しい」「落ち着く」といったポジティブな体験を積み重ねていくことが重要です。
愛着障害支援は簡単ではありませんが、「器」と「基地機能」という見取り図を持つことで、支援者自身が子どもと一緒に前向きに歩む力を得ることができます。そしてその過程こそが、子どもにとっての安心と信頼の基盤を育て、未来へとつながる希望となるのです。
参考文献
Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
米澤 好史(2022)「愛着の視点からの発達支援—愛着障害支援の立場から—」『発達支援学研究』2(2), 59–69.
米澤 好史『「愛情の器」モデルに基づく愛情修復プログラム』福村出版.

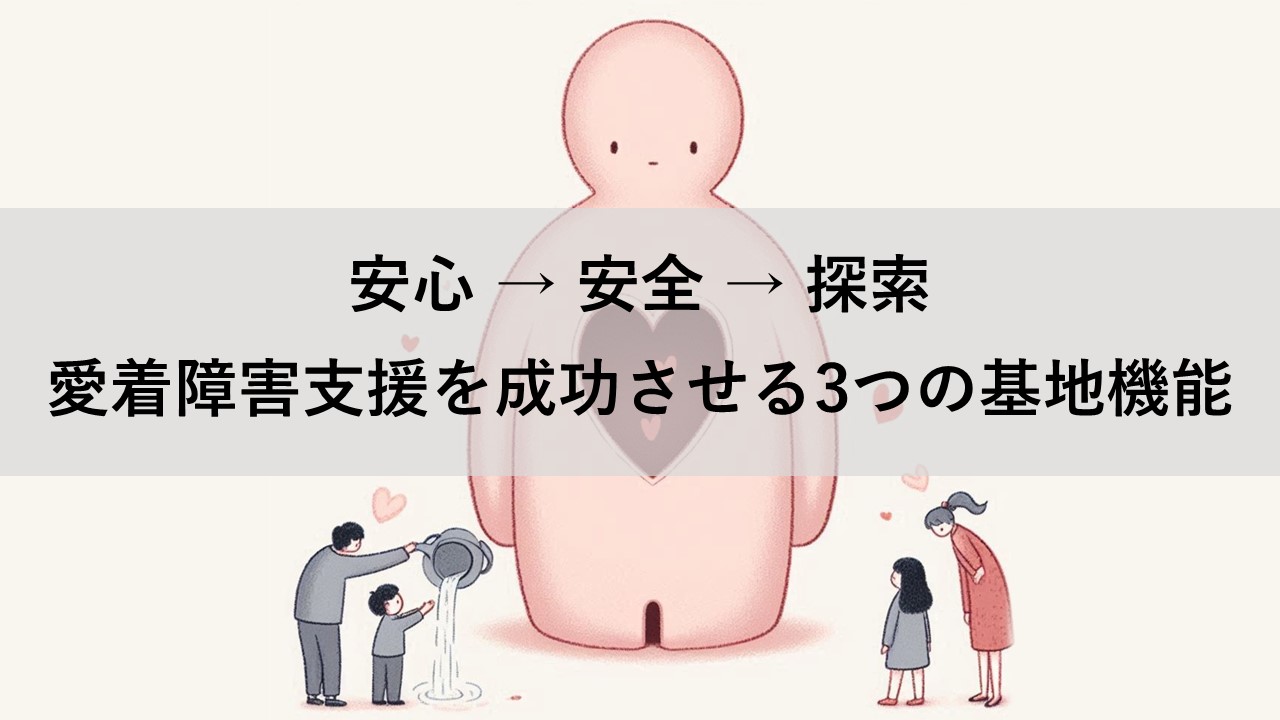


コメント