子どもが安心して笑い、泣き、甘えられる場所――それが「家庭」や「信頼できる大人との関係」です。
しかし、現実にはすべての子どもがその環境を与えられているわけではありません。
親の病気や経済的な困難、予期せぬ別離、そして虐待やネグレクト…。
そうした状況の中で、心の中に「人は信頼できる」という感覚を築けないまま成長すると、情緒や行動の発達に影響が及ぶことがあります。
それが、愛着障害です。
愛着障害は「しつけの仕方が悪かった」「親子仲が少し悪い」という単純な話ではありません。
家庭環境や社会的背景、子どもの特性などが複雑に絡み合って生じる、科学的にも根拠のある発達の課題です。
この記事では、愛着障害の原因やリスク因子を、医学的研究に基づきながら、できるだけわかりやすく解説します。
お子さんや家族、そして自分自身を理解するためのヒントとして、最後まで読んでいただければと思います。
愛着障害とは何か — 原因を考える前の基礎知識

赤ちゃんは生まれた瞬間から、周囲の人とのつながりを求めています。おむつを替えてくれる、抱っこしてくれる、泣いたらあやしてくれる──こうした日常のやり取りを通じて、赤ちゃんは「この人は自分を守ってくれる」という安心感を学びます。
この安心感の土台となるのが**愛着(attachment)**です。
医学的な定義
愛着障害(Attachment Disorder)は、乳幼児期に養育者(主に親や保護者)との安定した愛着関係が築けなかったことによって、情緒や行動の発達にさまざまな影響が生じる状態を指します。
米国精神医学会の診断基準(DSM-5)では、愛着障害は次の2つの型に分類されます。
- 反応性アタッチメント障害(Reactive Attachment Disorder: RAD)
- 他者との関係を築くことが極端に難しい
- 慰められても安心できない、感情表現が乏しい
- 脱抑制型対人交流障害(Disinhibited Social Engagement Disorder: DSED)
- 初対面の人にも警戒せず過度に接近する
- 境界線がなく、誰にでも甘えたりついて行ったりする
これらは単なる性格の違いではなく、初期の養育環境や人間関係の経験が脳や心の発達に影響した結果として現れます。
愛着形成の重要性
心理学者ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)の愛着理論や、その後の神経科学的研究(Schore, 2001; Gunnar & Quevedo, 2007)では、愛着は単なる感情的なつながりではなく、脳の発達とストレス調整機能の基盤であることが示されています。
特に、生後0〜3歳は脳の発達が急速で、前頭前野(感情や行動のコントロール)、扁桃体(恐怖や不安の処理)、視床下部-下垂体系(ストレス反応)が形づくられる時期です。
安定した愛着はこの時期の脳発達を支え、将来の人間関係や自己肯定感にも影響を及ぼします。
なぜ「原因を知る前に愛着形成を理解する必要がある」のか
愛着障害の原因やリスク因子は、養育環境や親子関係だけでなく、社会的・生物学的な要素も関わります。しかし、そのすべてを理解するためには、まず「愛着とは何か」「なぜ愛着が人の発達にとって欠かせないのか」を知っておく必要があります。
この基礎理解があることで、原因やリスク因子が「単なる不適切な環境」ではなく、脳と心の発達に深く関わる現象であることが見えてきます。
📚 参考文献
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).
- Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1-2), 7–66.
- Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 145–173.
愛着形成の脳科学的背景

赤ちゃんが「この人は自分を守ってくれる」と感じられるようになるまでには、単なる感情のやり取りだけでなく、脳の中で複雑な神経ネットワークが育っています。愛着は、生後数か月から3歳ごろまでの間に、親や養育者との安定した関係を通して形づくられます。この時期は、脳の発達が特にめざましい時期です。
発達の中心となる脳の領域
- 前頭前野(ぜんとうぜんや)
- 位置:おでこの裏あたり
- 働き:感情や行動をコントロールし、相手の気持ちを想像する機能
- 安定した愛着関係があると、ストレス下でも冷静に判断する力や、他者との良好な関係を築く力が育ちやすくなります(Schore, 2001)。
- 扁桃体(へんとうたい)
- 位置:こめかみの奥あたり
- 働き:恐怖や不安などの感情を処理
- 幼少期に安心感を得られると、扁桃体の過剰な反応が抑えられ、不安や恐怖に対して過敏になりにくくなります(Tottenham et al., 2010)。
- 視床下部–下垂体系(ストレス反応系)
- 働き:体のストレス反応をコントロール
- 安定した養育環境は、このシステムの働きを健全に保ち、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を適切に調整します(Gunnar & Quevedo, 2007)。
オキシトシンの役割
愛着形成には「愛情ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンが深く関わります。
オキシトシンは、抱っこやスキンシップ、笑顔でのやり取りなどのポジティブな関わりによって分泌され、親子双方の安心感を高めます。このホルモンはストレス反応を和らげ、心の安定に寄与します(Feldman, 2012)。
不安定な養育環境が与える影響
反対に、慢性的なストレスや養育者との関係が不安定な場合、これらの神経回路の発達に悪影響が及ぶことが分かっています。
例えば、虐待やネグレクトを受けた子どもは、扁桃体が過敏に反応しやすく、感情の調整が難しくなる傾向があります(McCrory et al., 2011)。また、ストレスホルモンが長期間高い状態が続くと、前頭前野や海馬(記憶に関わる部位)の発達にも影響を及ぼします。
📚 参考文献
- Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1-2), 7–66.
- Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 145–173.
- Tottenham, N., et al. (2010). Prolonged institutional rearing is associated with atypically large amygdala volume and difficulties in emotion regulation. Developmental Science, 13(1), 46–61.
- Feldman, R. (2012). Oxytocin and social affiliation in humans. Hormones and Behavior, 61(3), 380–391.
- McCrory, E., De Brito, S. A., & Viding, E. (2011). The impact of childhood maltreatment: A review of neurobiological and genetic factors. Frontiers in Psychiatry, 2, 48.
主要な原因とそのメカニズム
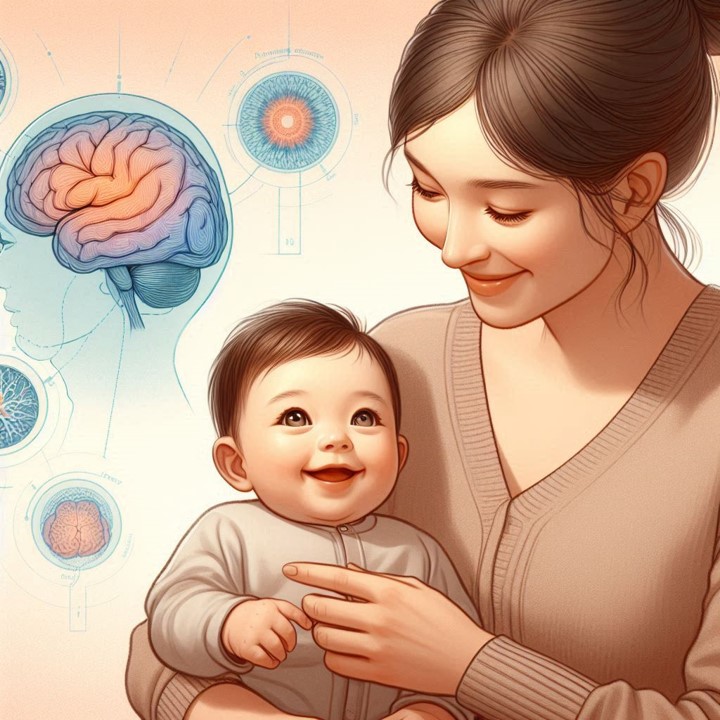
愛着障害の背景には、単に「親子関係がうまくいかなかった」という以上に、脳の発達や情緒の安定に直結する環境的な要因があります。ここでは代表的な原因と、それがどのように愛着形成に影響を与えるのかを解説します。
1. 養育の欠如・不安定な養育
- 例:親の長期不在、頻繁な養育者の交代、施設での集団養育
- 愛着理論(Bowlby, 1969)では、子どもは養育者を「安全基地(secure base)」として探索や学びを広げます。
- 養育者が頻繁に変わったり不在だったりすると、この安全基地が安定せず、脳の中で「人は信頼できる存在」という前提が築かれにくくなります。
- 研究では、施設での長期養育を経験した子どもは、扁桃体の過敏反応や社会的スキルの遅れが見られることが報告されています(Tottenham et al., 2010)。
2. 虐待(身体的・心理的・性的)
- 影響:恐怖や不信感が強まり、養育者を安心の源として感じられなくなる
- 虐待を受けた子どもは、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が慢性的に高まり、情緒の安定を司る前頭前野や海馬の発達に悪影響が及びます(McCrory et al., 2011)。
- 心理的虐待や性的虐待も、身体的虐待と同等かそれ以上に、長期的な精神的影響を与えることが知られています。
3. ネグレクト(養育放棄)
- 例:食事を与えない、衣服や衛生管理を怠る、話しかけない・抱かない
- ネグレクトは「物理的なケア不足」だけでなく、「情緒的関わりの欠如」も含まれます。
- 情緒的な無反応が続くと、オキシトシン分泌が低下し、人との関わりそのものが快いと感じにくくなります(Strathearn et al., 2009)。
4. 養育者の精神疾患や依存症
- 例:うつ病、統合失調症、アルコール・薬物依存
- 養育者が精神的に不安定な場合、一貫したケアが難しく、子どもは予測可能な関わりを得られません。
- 特にうつ病の親は、表情や声の抑揚が乏しくなり、乳児が情緒的反応を学ぶ機会が減少します(Field, 2010)。
5. 乳児期の長期入院や隔離
- 背景:重い病気や早産による長期入院
- 医療的に必要な処置であっても、母子分離が長く続くと、スキンシップや表情のやり取りが不足します。
- 研究では、母子の身体的接触(カンガルーケアなど)が愛着形成とストレス低減に重要であることが示されています(Feldman et al., 2002)。
原因の背後にある共通点
これらの原因は異なるように見えますが、共通しているのは**「子どもが安心できる一貫した関わりを得られない」**という点です。
脳科学的に見ると、安定した養育は脳のストレス応答系と情緒調整システムを健やかに育てます。反対に、予測不能で不安定な環境は、警戒・恐怖を優先する神経回路を強化してしまい、これが後の社会性や感情表現の難しさにつながります。
📚 参考文献
- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.
- Tottenham, N., et al. (2010). Prolonged institutional rearing is associated with atypically large amygdala volume and difficulties in emotion regulation. Developmental Science, 13(1), 46–61.
- McCrory, E., De Brito, S. A., & Viding, E. (2011). The impact of childhood maltreatment: A review of neurobiological and genetic factors. Frontiers in Psychiatry, 2, 48.
- Strathearn, L., et al. (2009). Adult attachment predicts maternal brain and oxytocin response to infant cues. Neuropsychopharmacology, 34(13), 2655–2666.
- Field, T. (2010). Postpartum depression effects on early interactions, parenting, and safety practices: A review. Infant Behavior and Development, 33(1), 1–6.
- Feldman, R., et al. (2002). Mother-infant skin-to-skin contact after delivery: Effects on mother and infant. Birth, 29(4), 247–252.
リスク因子(発症しやすくなる背景)

愛着障害は、誰にでも起こり得るわけではありません。
同じように困難な環境に置かれても、発症しやすい子とそうでない子がいます。
この「差」を生み出すのが**リスク因子(vulnerability factors)**です。
リスク因子は大きく分けて「子ども側の要因」「家庭環境の要因」「社会的要因」があります。
1. 子ども側の要因
早産や低出生体重児
- 早産や低体重で生まれた赤ちゃんは、NICU(新生児集中治療室)での長期入院が必要になることが多く、母子分離の期間が長くなります。
- また、脳の発達が未熟なため、刺激への反応や感情調整の機能が育ちにくく、愛着形成が難しくなる可能性があります(Korja et al., 2012)。
発達障害や重度身体疾患
- 自閉スペクトラム症や知的発達症など、コミュニケーションの発達に特性がある場合、養育者が反応を読み取りにくく、相互作用が減少することがあります。
- 慢性疾患や身体的障害も、長期入院や医療的処置の頻度増加を通して愛着形成に影響します(Atkinson et al., 1999)。
気質(敏感・反応が強いなど)
- 生まれつき刺激に敏感で泣きやすい子、逆に無反応で表情が乏しい子は、養育者が関わり方を迷いやすくなります。
- 気質と環境の相互作用によって、愛着の安定性が左右されることが示されています(Pluess & Belsky, 2010)。
2. 家庭環境の要因
貧困や社会的孤立
- 経済的困難は住居の不安定さ、食事・医療の不足、親の精神的ストレス増加につながります。
- 社会的孤立(親が支援を受けられない状況)は、養育ストレスを増やし、一貫性のある関わりを難しくします(Evans, 2004)。
家庭内暴力(DV)
- DVは直接的な身体的危害だけでなく、子どもが常に恐怖や緊張を感じる環境を作ります。
- 観察研究では、DV環境で育った子どもは、不安定型愛着の割合が有意に高いことが示されています(Levendosky et al., 2003)。
親の育児スキル不足や教育不足
- 親が適切な子育て方法を知らない、または経験が少ない場合、愛着を促進する関わり(抱く、声をかける、反応する)が不足します。
- 教育や育児支援プログラムは、このリスクを減らす効果が確認されています(Olds et al., 1997)。
3. 社会的要因
社会福祉制度の不足
- 児童相談所や福祉サービスの人員不足、アクセスの困難さは、危機的な家庭状況が放置される一因になります。
- 適切な介入が遅れるほど、愛着形成への影響は大きくなります。
戦争・災害・避難生活による親子分離
- 紛争や大規模災害では、家族が離ればなれになったり、避難所生活でプライバシーや安心感を確保できなくなることがあります。
- 研究では、戦争による親子分離がPTSDだけでなく愛着の不安定化にも関与することが報告されています(Punamäki et al., 2011)。
リスク因子の重なりに注意
1つのリスク因子だけで愛着障害になるとは限りませんが、複数の要因が重なると発症リスクは急激に高まります。
逆に、養育者や社会からのサポートが早期に入ることで、たとえリスクがあっても健康な愛着が形成されるケースも多くあります。
📚 参考文献
- Korja, R., et al. (2012). The development of mother–infant interaction and infant social competence from preterm birth to term age. Infant Behavior and Development, 35(3), 715–725.
- Atkinson, L., et al. (1999). Attachment security: A meta-analysis of maternal mental health correlates. Clinical Psychology Review, 19(2), 207–220.
- Pluess, M., & Belsky, J. (2010). Differential susceptibility to parenting and quality child care. Developmental Psychology, 46(2), 379–390.
- Evans, G. W. (2004). The environment of childhood poverty. American Psychologist, 59(2), 77–92.
- Levendosky, A. A., et al. (2003). The impact of domestic violence on the maternal–child relationship and preschool-age children’s functioning. Journal of Family Psychology, 17(3), 275–287.
- Olds, D. L., et al. (1997). Long-term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect. JAMA, 278(8), 637–643.
- Punamäki, R. L., et al. (2011). War and children’s wellbeing: The protective role of mental health and social resources. International Journal of Behavioral Development, 35(6), 502–509.
原因とリスク因子の複合的作用

愛着障害は、ほとんどの場合1つの原因だけで発症するわけではありません。
多くは、複数のリスク因子が同時に存在し、その相互作用によって発症リスクが高まります。
リスク因子の「足し算」ではなく「掛け算」
研究では、複数の困難が重なると影響は単純に足し合わされるのではなく、相互に増幅し合うことが示されています(Rutter, 2012)。
例えば、次のようなケースがあります。
- 親のうつ病(情緒的応答の低下)
- 経済的困難(生活の不安定化)
- 子どもの早産(医療的ケアの多さ、母子分離期間の延長)
これらが同時に起こると、養育者の心身的余裕が減り、安定した関わりが難しくなります。
さらに、早産児は刺激への反応が繊細なため、養育者が「どう接すればよいか分からない」状態になりやすく、愛着形成が阻害されます(Belsky & Fearon, 2002)。
乳幼児期は特に影響を受けやすい
乳幼児期(特に0〜3歳)は脳の発達スピードが非常に速く、「可塑性(変化しやすさ)」が高い時期です。
この時期に慢性的ストレスが続くと、以下の神経系の発達に影響します。
- 前頭前野:感情コントロールや意思決定を担う
- 扁桃体:恐怖や不安の処理
- 視床下部-下垂体系(ストレス反応系):ホルモンバランスと情緒安定に関与
慢性的な不安や恐怖は、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌パターンを変化させ、長期的な情緒・行動の発達に影響を与えます(Gunnar & Quevedo, 2007)。
早期介入の重要性
良いニュースとして、脳の可塑性が高い時期は、適切な支援があれば回復の可能性も高いということです。
家庭訪問型支援、親子遊びを通じた相互作用改善、養育者への心理的サポートなどは、愛着の安定化に有効であると報告されています(Bakermans-Kranenburg et al., 2003)。
まとめ
- 愛着障害は「単一の原因」よりも「複合的なリスク因子」の積み重ねで発症することが多い
- 乳幼児期は脳が発達途上で影響を受けやすいが、その分回復力もある
- 早期発見と介入が予後改善の鍵となる
📚 参考文献
- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 24(2), 335–344.
- Belsky, J., & Fearon, R. M. (2002). Early attachment security, subsequent maternal sensitivity, and later child development. Child Development, 73(1), 165–183.
- Gunnar, M. R., & Quevedo, K. (2007). The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology, 58, 145–173.
- Bakermans-Kranenburg, M. J., et al. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129(2), 195–215.
まとめ

愛着障害は、「親子関係の質」だけに原因があるわけではありません。
家庭環境の安定度、社会的背景、そして子ども自身の特性など、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。
これらの原因やリスク因子を正しく理解することは、予防や早期支援の第一歩です。
科学的研究によれば、乳幼児期からの安定した人間関係づくりは、愛着障害の予防に非常に効果的であることが示されています。
つまり、「愛着は生まれつき決まるものではなく、日々の関わりによって育まれるもの」。
家庭だけでなく、地域や社会全体で子どもと養育者を支える仕組みが、健やかな発達のために欠かせません。




コメント