「言葉を覚えさせるには、どうしたらいいんだろう?」
子どもがなかなか言葉を話さないと、不安になりますよね。
自閉症スペクトラム障害(ASD)を持つ子どもの約30%は、言葉をほとんど話しません。しかし、言葉の発達が遅れているすべての子どもが、成長してもずっと話せないわけではありません。では、どんな要因が「言葉を話せるようになるかどうか」を左右するのでしょうか? 最新の研究が、この疑問に答えようとしています。
これまでは、「知能(IQ)が高いほど言葉が伸びやすい」と考えられていましたが、最新の研究では 「手先の器用さ」や「人と一緒に物を見る・やる力(共同注意)」が重要 であることがわかってきました。つまり、知能よりも 遊びの中でどれだけ指先を動かし、人と関わるかが、言葉の発達を大きく左右する 可能性があるのです。では、具体的にどんな遊びや関わり方が子どもの言葉を伸ばすのでしょうか?
研究の目的

この研究では、言葉の発達が遅れている幼児が学齢期(小学生・中学生)や青年期(高校生・大学生)にかけて、どのように言葉を使えるようになるのかを追跡調査しました。特に、どのような要因が言葉の発達を予測できるのか に注目しました。
どんな子どもが調査されたの?
✔ 3歳の時点で、単語をほとんど話せない(1語以下)ASDの子どもたち
✔ 19歳まで追跡調査(別のグループでは10.5歳まで追跡)
✔ 言葉の発達に影響を与える可能性がある要因をチェック
わかったこと①:言葉の発達を予測するのは「微細運動能力」

この研究で最も重要な発見は、手先の器用さ(微細運動能力)が低い子どもは、将来的にも言葉の発達が遅れやすい ということです。
例えば、次のような動作が難しい子どもは、言葉を話せるようになるのも難しい傾向がありました。
✔ ビーズを糸に通す
✔ 小さなボタンを留める
✔ クレヨンで細かい線を描く
「微細運動能力」と「言葉の発達」の関係をさらに詳しく解説!
この研究で明らかになった「微細運動能力と言語発達の関係」について、もう少し深掘りして説明します。なぜ手先の器用さが言葉の発達に影響するのか、具体的な理由やメカニズムを紹介します。
1. そもそも「微細運動能力」とは?
「微細運動能力(fine motor skills)」とは、手や指を使った細かい動きを調整する能力のことです。
✔ 指先を使って小さなものをつかむ
✔ 物をつまんだり動かしたりする
✔ 道具を使って書いたり切ったりする
こうした動きは、目と手を協調させる「視覚・運動統合(visual-motor integration)」の働きによってコントロールされます。
2. どうして「微細運動能力」が「言葉の発達」に関係するの?
(1) 口や舌の動き(口腔運動)と密接に関連しているから
手先の動きと口の動きは、脳の中で密接につながっています。
✔ 手先を使う能力が低い子どもは、口や舌を動かす力も弱いことが多い
✔ 口の筋肉をうまくコントロールできないと、発音が難しくなる
実際に、言葉の遅れがある子どもの中には「食事中に飲み込むのが苦手」「噛む力が弱い」といった特徴を持つ子もいます。これは、手や口の運動をコントロールする脳の領域が共通しているためと考えられます。
(2) 脳の発達に影響するから
手や指を細かく動かすことは、脳の前頭葉を活性化させます。前頭葉は、「計画する」「考える」「話す」などの高度な機能を司る部分です。
✔ 微細運動能力が発達すると、脳の前頭葉も活性化しやすくなる
✔ 言葉を組み立てる能力(構文の理解や文章を作る力)が育つ
つまり、「手をよく使うこと」が「言葉を学ぶ脳の発達」にもつながるのです。
(3) コミュニケーションの基礎となる動作だから
手先を使う動作は、言葉を使う前の「非言語コミュニケーション」の一部でもあります。
✔ 指差し:言葉を話せない子どもでも、興味のあるものを指差して伝える
✔ 物のやりとり:大人に物を渡して「これ見て!」と伝えようとする
✔ 身振り:バイバイの手振り、手を伸ばす仕草など
これらのスキルが弱いと、人とのやりとりが少なくなり、言葉を覚える機会が減ってしまう可能性があります。
3. 「微細運動能力」を高めることで、言葉の発達を促せる?
「手先を使う遊びやトレーニングをすると、言葉の発達にも良い影響がある」という研究も増えています。
家庭でできるサポート
✅ 手指を使う遊び
🔹 積み木、ブロック、ビーズ遊び
🔹 ねんど、折り紙、シール貼り
✅ 日常生活の中で手先を使う練習
🔹 小さなボタンやファスナーの練習
🔹 食事のときにスプーンやフォークを使う
✅ 指先を鍛えるエクササイズ
🔹 指をグーパーする運動
🔹 指でピアノを弾くような動き
これらの活動は、「手先の動き」だけでなく、「脳の発達」と「言葉を学ぶ力」にも良い影響を与える可能性があります。
4. まとめ
✔ 手先を使う能力が低い子どもは、将来的に言葉の発達が遅れやすい
✔ 手や指の動きと口の動きは、脳の中で密接に関係している
✔ 微細運動を鍛えることで、言葉の発達をサポートできる可能性がある
「言葉がなかなか増えない」と感じる子どもには、言葉のトレーニングだけでなく、「手を使う遊び」を取り入れることが重要かもしれません。
わかったこと②:共同注意(他者との関わり)も影響する

また、共同注意(IJA:Initiating Joint Attention)と呼ばれるスキルも影響することがわかりました。
✔ 「大人が指差したものを見る」
✔ 「興味のあるものを大人に見せる」
✔ 「一緒に何かを見る・やる」
こうしたスキルが低い子どもは、言葉の発達がゆっくりになる可能性が高かったのです。
研究によると、「共同注意(IJA:Initiating Joint Attention)」のスキルが低い子どもは、言葉の発達が遅れやすいことがわかっています。では、なぜ共同注意が重要なのか?どのように関わるのか?を詳しく説明します。
1. そもそも「共同注意」とは?
共同注意(Joint Attention)とは、「他者と一緒に何かに注意を向けることができる能力」のことを指します。
特に、**自発的な共同注意(IJA:Initiating Joint Attention)**は、「自分から大人を巻き込んで、一緒に注意を向ける」スキルを意味します。
✅ 共同注意の具体例
✔ 「大人が指差したものを見る」
✔ 「興味のあるものを大人に見せる」
✔ 「大人と一緒に何かを見る・やる」
例えば、赤ちゃんが「おもちゃの車」を見つけて、それを大人に見せようとする。
→ こうしたやりとりが、共同注意のスキルです。
2. なぜ「共同注意」が「言葉の発達」に関係するの?
共同注意が言葉の発達に影響する理由は、大きく3つあります。
(1) 言葉を学ぶ機会が増える
赤ちゃんや幼児は、「言葉を聞く回数」が多いほど、言葉の発達が進みます。
しかし、共同注意が少ないと、大人と視線を合わせたり、興味を共有する機会が減ります。
✔ 大人が「これは車だよ」と教えても、子どもが車を見ていなければ、言葉の学習につながらない
✔ 逆に、共同注意ができる子は「車を見て、大人の言葉を聞く」経験が増え、言葉を覚えやすくなる
つまり、「共同注意がある=言葉を学ぶチャンスが増える」ということになります。
(2) 「他者と関わる力」が育つ
言葉は「コミュニケーションのツール」です。
しかし、共同注意が低い子どもは、「人と関わること」自体が少なくなることがあります。
✔ 人と関わるのが少ない → 言葉を使う機会も少ない
✔ 人と一緒に何かを楽しむ経験が少ない → 会話のキャッチボールが難しくなる
結果として、「言葉を話すモチベーション」も低くなりやすいのです。
(3) 脳の発達にも関係する
共同注意は、脳の「社会性」や「言語」に関わる領域を活性化させる重要なスキルです。
✔ 共同注意が多い子どもは、前頭葉(コミュニケーション・注意力を司る)が活性化しやすい
✔ 共同注意のスキルが弱いと、人の視線や言葉の意味を理解する力が発達しにくい
つまり、共同注意の発達が、言葉を学ぶための「脳の準備」を作るとも言えます。
3. 共同注意を伸ばすためにできること
もし、お子さんが共同注意をあまり示さない場合、どのようにサポートできるでしょうか?
以下のような遊びや関わり方が、共同注意を育むのに役立ちます。
✅ (1) 指差しを引き出す遊び
✔ 風船やシャボン玉を使い、「どこに行った?」と指差して注目を促す
✔ 本や絵本を一緒に見ながら、「○○はどこ?」と聞いて指をさせる
ポイント:「子どもが興味を持っているもの」に大人が関心を示すこと!
✅ (2)「見せる・渡す」遊び
✔ 子どもが好きなオモチャを持っているとき、「見せて!」と手を出す
✔ 子どもが自然に大人にオモチャを渡せるように促す
ポイント:「楽しいから、ママ・パパと共有しよう」と思える関わりを作ること!
✅ (3)「一緒に楽しむ」遊び
✔ ボールを転がし合う
✔ お人形を動かして「○○ちゃん、お出かけしよう!」とストーリーを作る
✔ 鏡を使って一緒に変顔遊び
ポイント:「自分と他者が同じことを楽しんでいる」という経験を増やすこと!
4. まとめ
✔ 共同注意(IJA)は、言葉の発達に大きく関わるスキル
✔ 共同注意が高いと、言葉を学ぶ機会が増え、人と関わる力も育つ
✔ 共同注意を促すために、指差し遊び・「見せる・渡す」遊び・一緒に楽しむ遊びが有効
共同注意は、言葉を学ぶ「土台」となる大切なスキルです。
もし、お子さんの言葉の発達が気になる場合は、「まずは一緒に興味を共有する」ことから始めるのがおすすめです!
結論:微細運動の発達がカギ!

✔ これまで言葉の発達には「知能(IQ)」が重要だと考えられていましたが、今回の研究では 手先の器用さ(微細運動能力)や社会的なやりとり(共同注意)が重要 だと示されました。
✔ つまり、言葉を増やすためには、手先を使う遊びや、他者との関わりを増やすことが効果的かもしれない ということです。
まとめ

この研究から、言葉の発達が遅れている子どもに対して、次のようなサポートが有効かもしれません。
✅ 手先を使う遊び(おもちゃのブロック、折り紙、ねんど遊び)
✅ 一緒に何かを見る・やる体験(絵本を読む、おもちゃを使って「これなに?」と話しかける)
✅ 指差しや視線を使う練習(おもちゃを指差して「これ好き?」と聞く)
これらの取り組みが、言葉の発達をサポートする大きなヒントになるかもしれません。
引用文献
Bal, V. H., Fok, M., Lord, C., Smith, I. M., Mirenda, P., Szatmari, P., Vaillancourt, T., et al. (2019). Predictors of longer-term development of expressive language in two independent longitudinal cohorts of language-delayed preschoolers with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(9), 1028–1038. https://doi.org/10.1111/jcpp.13117


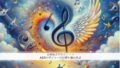

コメント