「ことばの発達を促したい、、、」
「楽しくことばを育てる方法は、ないかな?」
言葉の発達は、子どものリハビリ現場でも多く聞かれる要望の一つです。親やケアギバーが子供の言語能力を向上させるためには、楽しみながら学べる方法が必要です。ことば遊びはその一つであり、子供が言葉を楽しんで学ぶ手段として非常に有効です。
今回は、ことば遊びの効果についていくつかの方法をピックアップし、詳しく解説します。
「しりとり」の効果ってなんですか?
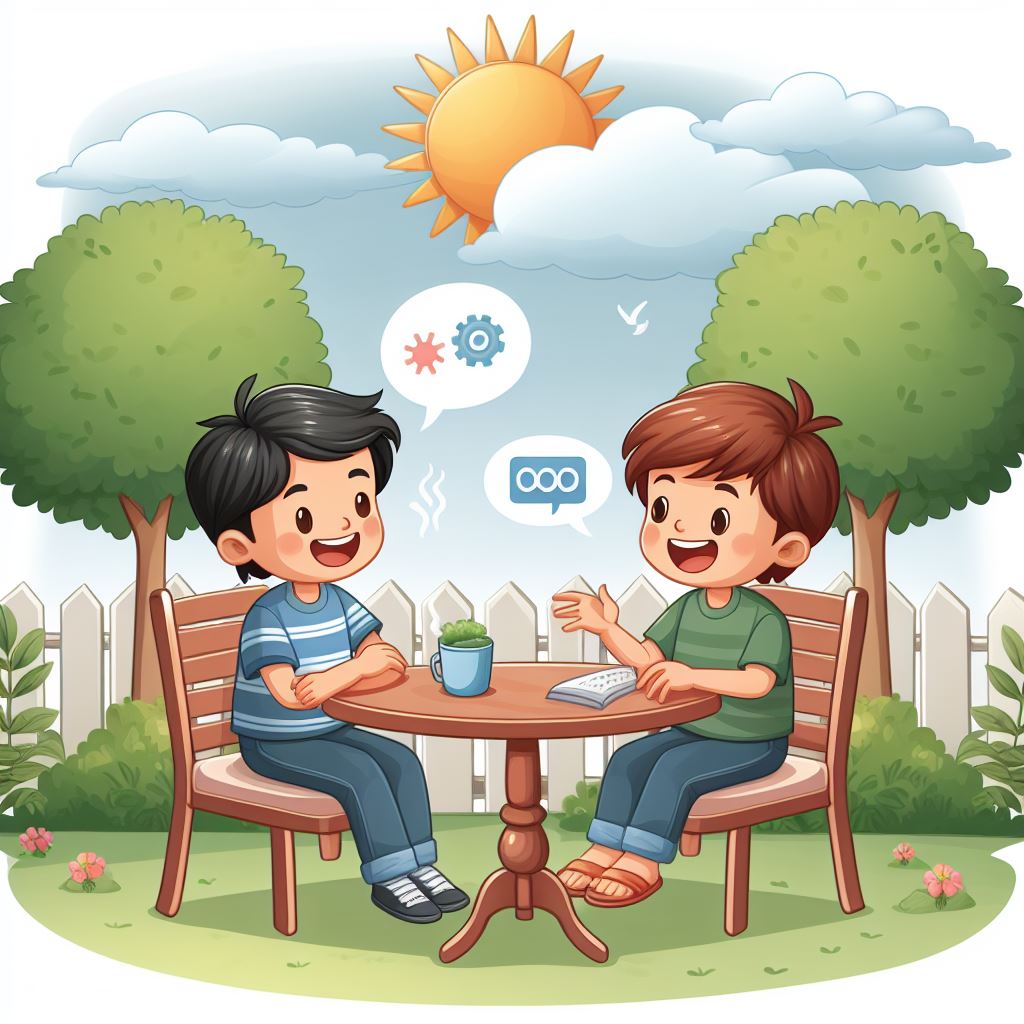
言葉遊びは、子供たちにとって言語能力を楽しみながら向上させる素晴らしい手段です。代表的な言葉遊びとしては、皆さんご存知の「しりとり」とか「逆さ言葉」が挙げられます。これらの遊びは、子供が言葉の音や構造に意識を向けることで、言語能力の発達を促進します。
「しりとり」は、言葉の発達に多くの良い影響を与えます。以下に、その効果をいくつか挙げてみます
・語彙の増加
「しりとり」を通じて、子供たちは新しい単語を学びます。ゲーム中に出てくる様々な言葉を通じて、彼らの語彙が豊かになります。
・言葉の音韻意識の向上
「しりとり」では、次の単語を選択する際にその単語の語頭音を意識する必要があります。このことで、子供たちの音韻意識が向上し、言語の音の特徴に敏感になります。
・言葉の検索能力の向上
「しりとり」では、与えられた単語の語頭音を持つ単語を見つける必要があります。これによって、子供たちは自分の語彙の中から適切な言葉を探し出す能力を養います。
・コミュニケーション能力の向上
「しりとり」はグループで楽しむことができるゲームであり、他の参加者とのコミュニケーションを促進します。言葉を交換し合うことで、言語の理解や表現能力が向上します。
・創造性の促進
途中で思いついた単語を使うことで、子供たちは自分の創造性を発揮し、新しいアイデアや言葉遊びを生み出すことができます。
特に、「しりとり」は音韻に意識を向ける言葉遊びです。
しかし、さらに重要な要素があります。それは、「単語を語頭音で検索できるよう心的な辞書を再編成することを意味する」という点です。
つまり、子供たちは一文字だけを使って、自分の頭の中にある言葉の辞書から適切な単語を引き出す、あるいは検索する能力を養うのです。
この能力は語彙を増やすだけでなく、言葉を検索する力も読みや会話にとって必要不可欠です。例えば、「しりとり」を通じてこの能力を鍛えることで、子供たちは瞬時に適切な単語を見つけ出すスキルを身につけます。そして、この能力は学習やコミュニケーション全般に役立ちます。
要するに、「しりとり」は単なる遊びではなく、言語能力の向上や認知能力の発達に寄与する重要な教育的な活動と言えます。そのため、子供たちにことば遊びを通じてこのような能力を育む機会を提供することは、教育上非常に有益です。
音韻(おんいん)とは、言語学の用語で、言葉を構成する音の最小単位のことを指します。音韻は、言語の音素(phoneme)という音の種類をさらに細分化したものであり、その言語の音声システムにおける基本的な音の要素です。言語によって異なる音韻体系がありますが、例えば英語の場合、/p/や/t/、/k/などの個々の音は音韻を構成する要素として認識されます。音韻は言語の発音や聞き取りにおいて重要な役割を果たし、言語の理解や習得においても重要な概念です。
言葉をみる力を養う「ことばのかくれんぼ」

言葉のかくれんぼゲームは、文字情報から言葉を読み取る力を鍛えるための楽しい遊びです。このゲームでは、与えられた単語から、さらに隠れている言葉を見つけ出す必要があります。例えば、「キリギリス」から「キリ」と「リス」を見つけるような感じです。
「キリギリス」➡ 「キリ」 「リス」
「カブトムシ」➡ 「カブ」 「カシ」 「ブシ」
「クリスマス」➡ 「クリ」 「リス」 「クマ」
このゲームを楽しむには、「視覚性語彙」という能力が求められます。視覚性語彙とは、見た文字情報を言葉の読み情報に置き換える能力のことです。これは、ひらがなを流暢に読む能力と関連しています。そして、ひらがなの読みを流暢に行うためには、「長音表記知識」という特殊な発音の理解も必要です。
長音表記は、単語の特定の部分を伸ばして読むことを指します。
例えば、「かあさん」や「にいさん」のように、母音を長く伸ばして読むことです。このような特殊な読み方を理解することで、言葉のかくれんぼゲームを楽しむ際に、より効果的に隠れた言葉を見つけ出すことができます。
言葉のかくれんぼゲームは、言葉を分解したり、合成したり、バラバラの文字を一つのまとまりにすることで、文字の読み取り能力を向上させます。
このゲームを通じて、子供たちは文字を操る楽しみを覚え、読みの流暢性や特殊な発音、文字の表記への理解を深めることができます。
ほかにもたくさんある、ことばあそび

ことばを育てるための言葉遊びはさまざまあります。以下に、いくつか代表的なものを挙げてみます。
・しりとり
すでに触れた通り、しりとりは音韻意識を高め、語彙を増やすのに役立ちます。
・言葉のかくれんぼ
文章や言葉の中から、隠れている言葉を探すゲームです。これは視覚性語彙や長音表記知識を養うのに効果的です。
・言葉ジェンガ
ジェンガのようなブロックを使って、言葉を構成するゲームです。一つの単語を追加するごとに、新しい言葉を作り出すことができます。
・言葉あみだくじ
あみだくじのような形式で、言葉の中から関連する言葉を結びつけるゲームです。これによって語彙を増やし、言葉の関連性を理解する力を養います。
・言葉パズル
クロスワードパズルやワードサーチなど、言葉を使ったパズルゲームは言葉遊びとして非常に効果的です。これによって語彙を増やし、言葉のスペルや意味を理解する力を高めることができます。
・ストーリーテリング
子供たちにストーリーを作り、語彙や文法を使って物語を表現させる活動です。これによって創造性や表現力を伸ばすことができます。
これらの言葉遊びは、子供たちが楽しみながら言語能力を向上させるのに役立ちます。親や保護者、教師が子供たちと一緒に楽しんで取り組むことで、言葉の発達を促進することができます。
-補足-
ストーリーテリングは、子供たちが想像力を駆使して物語を作り出し、それを口頭で表現する活動です。以下に、ストーリーテリングを実践する際の具体的な手順やポイントを示します
・テーマの選定
まずはストーリーのテーマを選びます。子供たちが興味を持ちやすいテーマや、教育的な要素を含んだテーマを選ぶと良いでしょう。例えば、友情、冒険、勇気、家族などがあります。
・キャラクターの設定
ストーリーに登場するキャラクターを設定します。主人公やその仲間、敵対するキャラクターなど、物語を進める上で重要な役割を担うキャラクターを考えます。
・設定の決定
物語が展開する舞台となる設定を決定します。時間や場所を設定し、物語の背景を描き出します。
・プロットの作成
物語の構成や流れを考えます。序盤、中盤、結末など、物語を分かりやすく整理しましょう。また、どのような出来事が起こるか、どのような問題が発生するかを考えます。
・物語の展開
キャラクターや設定、プロットを元に、物語を口頭で語り始めます。子供たちにストーリーを聞かせながら、彼らの想像力を刺激し、物語を展開させていきます。
・参加の促進
子供たちが物語に参加しやすいように、質問を投げかけたり、意見を求めたりします。彼らのアイデアや感想を取り入れながら、物語を共に作り上げていきます。
・結末の付け方
物語の結末を決定します。問題が解決されるか、キャラクターが成長するか、など、物語の目的に合った結末を考えます。
ストーリーテリングを通じて、子供たちは創造性や表現力を伸ばすだけでなく、言語能力やコミュニケーション能力も向上させることができます。
まとめ
こういった言葉遊びは、ほんとうに手軽にできる遊びです。
それが言葉の発達とどのように関係があるのかを知ることで、普段の遊びに意味や価値を与えることができます。大人がこのことを知ることで、子どもと遊んでみようというきっかけになればと思います。
そしていつも言いますが、子どもは今自分にとって必要なことを遊びとして楽しむんです。
子ども自ら発見し、それを楽しむ。そこに親子で一緒に楽しむ!これが、大切です。
お読みくださってありがとうございました。
引用文献
・高橋登:ことば遊びの発達:“しりとり”を可能にする条件の分析.発達心理学研究.8(1).pp42-pp52.1997
・横山萌他:年長児におけることば遊びとひらがな単語読字の流暢性との関連.岡山大学教師教育開発センター紀要.第10号.pp.27pp37.2020




コメント