私は毎晩、子どもを寝かしつけるときにハグをしながら、その日楽しかったことを話しかけています。
「今日、一緒にやったゲーム、楽しかったね。また一緒にやろうね」
「○○のYouTube動画、おもしろかったね。また一緒に観ようね」
こうして、楽しかった時間を振り返りながら、一緒に感じることを大切にしています。
実は、これにはある漫画のワンシーンが影響しています。
とても厳しい医師がいました。彼は幼い頃、母親から虐待を受け、離れて暮らすことを余儀なくされました。母を見返すために努力を重ね、やがて医師となった彼は、20年ぶりに母親と再会します。しかし、そのとき母はすでに寝たきりの植物状態でした。
それから5年後、彼は知人の医師(漫画の主人公)に、母親の意識を取り戻す手術を依頼します。手術は成功し、一瞬の意識を取り戻した母。彼の耳元で、母はこうささやきました。
「今日のブランコ……楽しかったね。また……明日も……乗ろうね……」
母の最期の言葉は、彼の心に深く刻まれました。長い間、憎しみを抱えていた彼でしたが、その瞬間、幼い頃のやさしい母との思い出がよみがえります。手術をした医師に、彼は静かに言いました。
「母親に会えてよかったよ」
このエピソードは、『Dr.コトー診療所』第11巻に収録されています。読んだとき、言葉では表せない感情が胸に込み上げてきました。
だからこそ、私は子どもたちと楽しかったことを共有し、その記憶を大切にしたいと思うのです。
興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
さて、今回は子どもへの声掛けについてのお話です。
お子さんの中には、感受性が豊かで、空を見ては何かに例えたり、美しいものに素直に「きれいだね」と言える子がいます。そんな純粋な感性は、とても素敵ですよね。
そして、お母さんとお話ししていると、不思議なことに、お母さん自身も表現が豊かで感性にあふれていることに気づきます。どうやら、ここにはちょっとした秘密がありそうです。
そこで今回は、脳科学の視点から、この感受性の秘密を紐解いていきましょう。
認識の発達とは?——他者との関わりから生まれる世界の理解

周りの人たちが知っている仕方で自分も世界を知ってゆき、周りの人たちと認識世界を共有してくのが認識の発達にほかなりません。
滝川一廣:「こころ」の本質とは何か:統合失調症・自閉症・不登校の不思議.筑摩書房.2004
これは、ある児童精神科医の言葉です。この考え方をより深く理解するために、発達心理学や神経科学の視点から説明していきます。
1. ヴィゴツキーの発達理論:「精神間作用から精神内機能へ」
発達神経学者レフ・ヴィゴツキーは、「子どもの発達は、まず他者との関わりの中で生じ、その後に個人の内面に取り込まれる」と提唱しました。これを 「精神間作用から精神内機能へ」 という発達の流れとして説明しています。
簡単に言うと、子どもは最初から自分ひとりで考えたり学んだりするのではなく、周囲の大人や他の人々とのやりとりを通じて知識や考え方を身につけます。そして、その経験が繰り返されることで、徐々に自分の中に定着し、自分自身の理解となっていくのです。
2. 脳の発達と「借りた認識」の統合
子どもの脳は、生まれたときから完成しているわけではなく、環境との相互作用を通じて発達します。
- 未熟な脳を補う「大人のフィルター」
子どもはまだ経験が少なく、脳の発達も途中段階です。そのため、自分だけの視点で世界を理解することは難しく、最初は周囲の大人の目や耳、感覚を借りながら世界を知っていきます。たとえば、親が「この花、きれいだね」と言えば、子どもは「花はきれいなものなんだ」と学びます。 - 神経科学的視点:ミラーニューロンの役割
脳には、他者の行動や感情を自分ごとのように感じる「ミラーニューロン」という神経細胞があります。例えば、親が驚いた表情をすると、子どもの脳内でも驚きに関連する神経活動が起こります。こうした脳の仕組みが、他者を通じた学びを可能にしているのです。 - 「借りた認識」がやがて「自分の認識」に
幼い頃は、親の言葉や行動をそのまま真似することが多いですが、成長するにつれ、子ども自身の経験や考え方が加わり、独自の認識が形成されます。脳の前頭前野(思考や判断を担う領域)が発達することで、自分なりの解釈を持つようになるのです。
3. 認識の発達を支えるために大人ができること
子どもが健やかに世界を理解し、自分なりの視点を持てるようになるためには、大人の関わり方がとても重要です。
- 多様な視点を提供する
子どもが「この絵、変なの」と言ったとき、「そう思うんだね。でも、ここが面白いところだよ」と別の視点を伝えることで、子どもは世界の捉え方がひとつではないことを学びます。 - 共感を示しながら言葉をかける
例えば、子どもが「怖い!」と言ったときに、「大丈夫」と否定するのではなく、「怖く感じたんだね」と受け止めることで、子どもは自分の感覚を信じ、自己理解を深めることができます。 - 経験を共有し、一緒に考える
本を読んだり、自然を観察したりしながら、「この雲、何に見える?」と問いかけることで、子どもは自分の感覚を言葉にする力を育みます。
ここまでのまとめ
子どもは最初、周囲の大人の認識を借りながら世界を理解し、経験を積みます。そして、脳の発達とともに、それを自分のものとして統合し、自分の感覚で世界をとらえられるようになっていきます。
この過程を支えるために、大人は子どもの感じ方や考え方に寄り添い、多様な視点を伝えることが大切です。子どもがどのように世界を見ているのかを知り、一緒に考えることこそが、認識の発達を豊かにする鍵となるのです。
感覚情報の統合と情動の関連性——脳科学と心理学の視点から

私たちは日々、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚・前庭覚・固有受容覚といった 多様な感覚情報 を受け取り、それを 脳内で統合 しながら世界を認識しています。しかし、それらの感覚情報は単なる物理的な刺激ではなく、 情動(心の動き) を生じさせ、さらに 記憶と結びつくことで個別の意味や価値を持つ ようになります。
たとえば、青空を見たときの反応は、人それぞれ異なります。
- Aさん(科学的な視点):「空は青いなぁ。この青というのは光の性質によって青色に見えるんだなぁ。」
- Bさん(感情的な視点):「わぁ、とてもきれいな青空!お母さん、青空好きって言ってたな。写真を撮ってお母さんに送ろう!」
これは、 感覚情報が過去の経験や記憶と統合されることで、それぞれの人にとって異なる意味を持つ ことを示しています。では、このプロセスがどのように脳内で起こるのか、医学的な視点から詳しく見ていきましょう。
1. 感覚情報の統合を担う脳の仕組み
感覚情報は、それぞれの感覚器官(目・耳・皮膚・鼻・舌など)を通じて脳へ送られ、 大脳皮質 を中心としたネットワークで処理されます。特に以下の脳領域が重要な役割を果たします。
① 視床(Thalamus)——感覚情報の中継地点
視床は すべての感覚情報(嗅覚を除く)を統合し、大脳皮質へと送る 役割を担っています。視覚、聴覚、触覚、味覚、前庭覚などの情報がここを通過し、必要な処理がなされます。
② 感覚野(Sensory Cortex)——各感覚情報の処理
- 視覚情報 → 後頭葉の視覚野
- 聴覚情報 → 側頭葉の聴覚野
- 体性感覚情報(触覚・温度・痛みなど) → 頭頂葉の体性感覚野
ここで処理された情報は、 高次脳領域へと送られ、他の感覚情報や記憶と統合されます。
③ 側頭葉(Temporal Lobe)——記憶との結びつき
側頭葉には 海馬(Hippocampus) があり、 感覚情報が過去の経験や記憶と結びつくプロセス が行われます。たとえば、青空を見たときに「お母さんが好きだったな」と思い出すのは、この領域の働きによるものです。
④ 扁桃体(Amygdala)——情動の付与
扁桃体は、感覚情報に 情動(喜び・恐怖・悲しみなど)を付与する 役割を果たします。
- 美しい青空を見て「癒される」と感じる
- 雷の音を聞いて「怖い」と思う
このような反応は、扁桃体が感覚情報に対して「ポジティブ」「ネガティブ」といった情動的な価値を与えるために起こります。
⑤ 前頭前野(Prefrontal Cortex)——思考と行動の決定
最後に、感覚情報と情動が統合された結果、 前頭前野が「次にどう行動するか」を決定 します。
- 理系の男性(Aさん)は、空の青さについて学び直そうとする
- お母さん思いの女性(Bさん)は、写真を撮って送るという行動をとる
こうして、 感覚情報 → 記憶との統合 → 情動の付与 → 行動の選択 というプロセスが脳内で進行していきます。
2. 記憶と感覚統合の関係——「エピソード記憶」と「手続き記憶」
感覚情報と過去の経験が結びつくことで、記憶は 「エピソード記憶」 として蓄積されます。
- エピソード記憶(Episodic Memory)
→ 「お母さんが青空を好きだった」「小さい頃、青空を見ながらピクニックをした」
→ 個人的な出来事と感情が結びついた記憶 - 手続き記憶(Procedural Memory)
→ 「青色は光の散乱によって見える」「写真を撮って送るという行動パターン」
→ 繰り返しの経験によって身につく記憶
これらの記憶が新たな感覚情報と統合され、未来の行動に影響を与えます。つまり、 「過去の記憶」+「今の感覚情報」=「未来の行動」 という関係が成り立つのです。
3. 医学的研究と感覚統合の実証
脳科学や心理学の研究によって、感覚統合と記憶・情動の関係が明らかになっています。
(1) 感覚統合と記憶の関連(Murray et al., 2016)
研究では、 感覚情報が記憶と統合される際に、側頭葉(海馬)と前頭前野が協調して働く ことが示されています。このプロセスがスムーズに行われることで、記憶はより強固になり、新たな行動に結びつきます。
(2) 扁桃体の情動処理(LeDoux, 2000)
LeDouxの研究によると、 扁桃体が強く活動することで、感覚情報に対する感情的な記憶が形成されやすくなる ことが分かっています。たとえば、青空に対して「心が落ち着く」と感じるのは、過去に青空を見てポジティブな経験をしたことと関連しています。
感覚情報が未来の行動をつくる
- 感覚情報は脳内で統合され、記憶や情動と結びつく
- 海馬が記憶を整理し、扁桃体が情動を付与する
- 統合された情報が前頭前野で処理され、新たな行動を生み出す
- 今の経験が未来の記憶となり、次の行動に影響を与える
このように、私たちが日々受け取る感覚情報は、単なる情報ではなく 「記憶と感情を伴う、未来を形作る要素」 なのです。
感覚の統合とは、単に脳の仕組みの問題ではなく、 「個人のストーリーをつくるプロセス」 そのものなのです。
まとめ:お母さんの声掛けが未来を作っていく

ここまでの話をまとめますと、
・子どもは、身近なお母さんやお父さんのフィルターを借りて、世界を知っていく
・過去の経験や記憶が未来を作り上げていく
子どもは、 身近なお母さんやお父さんの感じ方を通して、世界を知っていきます。 そして、その経験が心に刻まれ、未来のものの見方や感じ方につながっていきます。
たとえば、お母さんが「このお花、きれいだね」と言えば、子どもも 「お花はきれいなものなんだ」と感じる心 を育んでいきます。「○○ができてうれしいね」と言えば、自分の成長を喜ぶ気持ち が生まれます。
こうした 日々の何気ない声かけや共有した感覚 が、子どもの記憶となり、やがて 子ども自身の世界の感じ方や未来の行動につながっていく のです。
あなたの「感じたこと」を、ぜひ 言葉にして子どもに伝えてみてください。 その一言が、子どもの世界を広げる大切なきっかけになります。

自分が感じたことを、たくさん子どもに伝えていきましょう!
お読みくださって、ありがとうございました。
明日の運勢を占おう!おみくじはコチラをタップ(クリック)
引用文献・参考文献
・カルロ・ペルフェティ:認知神経リハビリテーション入門.共同医書出版.2016
・浅野大喜:リハビリテーションのための発達科学入門.共同医書出版.2012

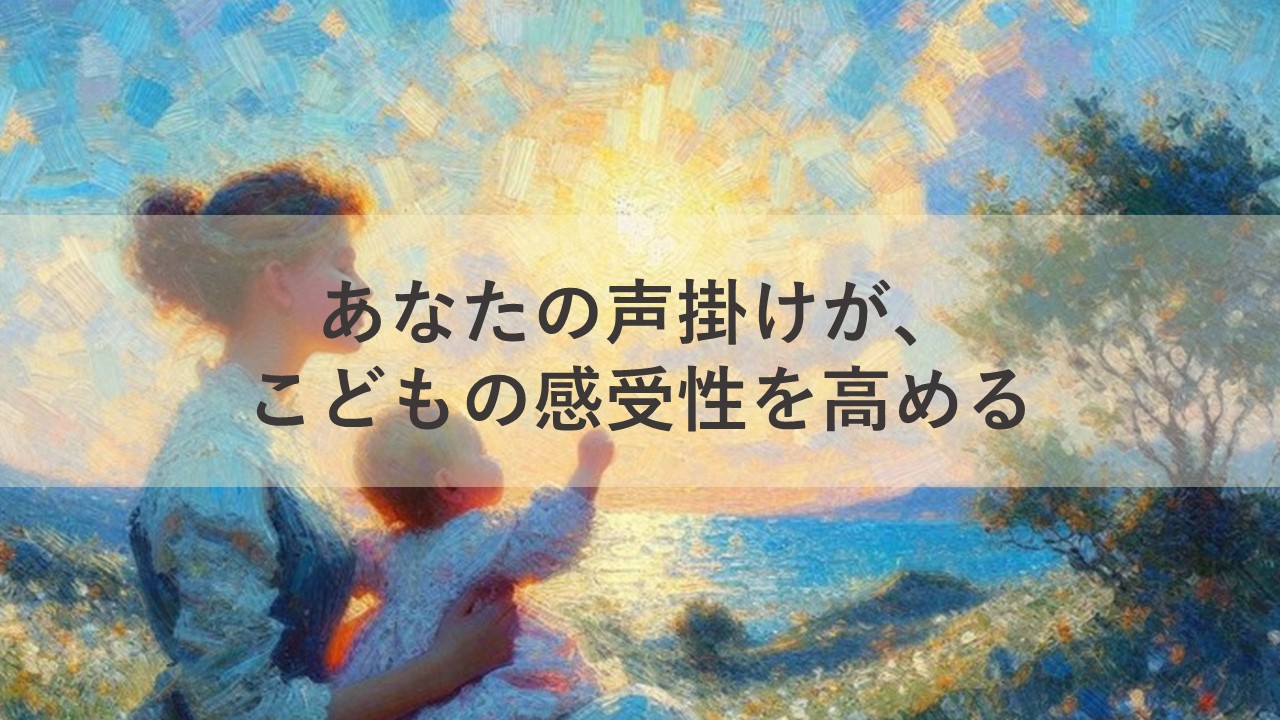

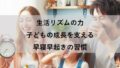
コメント