 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 ASD と統合失調症 — 「皮膚感覚」「表情認知」「社会的脳ネットワーク」のちがい
自閉症スペクトラム(ASD)と統合失調症は、一見似て見える部分もありますが、脳の働き方や感覚の受け取り方はまったく異なります。本記事では、触覚(皮膚感覚)、表情認知、社会的脳ネットワークの研究をもとに、科学的にわかりやすく解説します。
 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 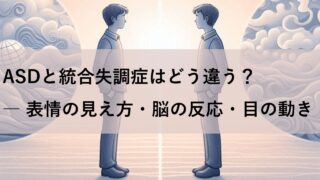 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 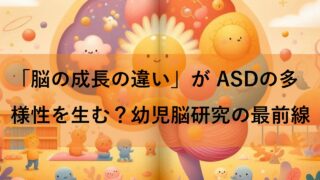 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 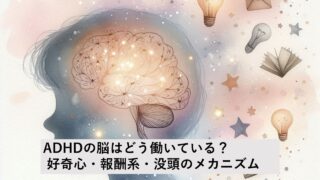 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識  まずはここから!小児リハを学ぶ
まずはここから!小児リハを学ぶ 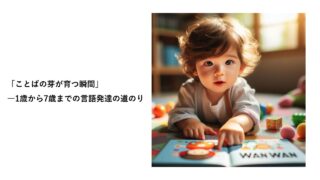 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識 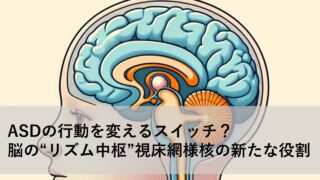 もっと知りたい小児の知識
もっと知りたい小児の知識  まずはここから!小児リハを学ぶ
まずはここから!小児リハを学ぶ 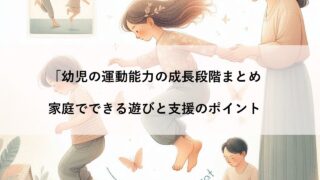 まずはここから!小児リハを学ぶ
まずはここから!小児リハを学ぶ 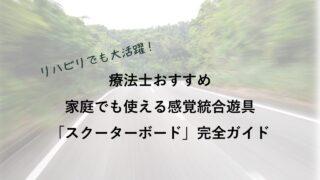 9割が知らないおもちゃの効果
9割が知らないおもちゃの効果