三男(当時5年生)が学校の授業で「ふりかけ」が必要だということで買ってきました。どうやら、調理実習でご飯を炊く授業をするようです。真剣に選んでいました、ふりかけを。
そこにきたのは四男(当時3年生)です。
おおきい焼きのりを持ってきて、「これにすればよいじゃん」
これはわざとなのか? 本気なのか? どちらにせよ、かわいかった思い出です。
さて、ブログでは、叱ることはせずに、良いところを見つけて伸ばす、思いに共感するといったことが多いですが、でも実際には叱らなければならないこともあります。
その時の効果的な伝え方、反発をまねく伝えかたについてお話したいと思います。
叱り方のパターン

叱り方のパターンについて解説します。叱り言葉のパターンは14に分類されるそうですが、その中の6パターンについて解説します。
望ましくない理由を説明する
この叱り方は、子どもに対してなぜその行為が望ましくないのかを説明することで、理解を促すものです。例えば、「おもちゃを投げると他の人を傷つける可能性があるから、やめてほしい」といったように、具体的な理由や影響を示しています。
子どもの人格に対する評価
このパターンでは、子どもの行動に対してではなく、子ども自身の人格や性格を批判するような叱り方です。例えば、「いつもだらしない」とか「もうあんたはだめだ」といったように、子ども自身を否定するような言葉を使います。
突き放し
突き放しの叱り方は、親としての関与や支援を否定するような言葉を使う方法です。例えば、「もう好きにしなさい」「勝手にやりなさい」といったように、子どもを自己解決させるような姿勢を示します。
感情表出
このパターンでは、親の感情や感情的な反応を子どもに示すことで、彼らの行動が望ましくないということを伝えます。例えば、「がっかりした」「悲しい気持ちになった」といったように、親の感情をストレートに表現します。
望ましい行為の実行要求
この叱り方は、望ましい行動や行動の変更を子どもに直接要求する方法です。例えば、「勉強しなさい」「部屋を片付けなさい」といったように、具体的な行動を指示します。
問いただし
この叱り方は、子どもの行動を問いただすことで、彼らに自己反省を促します。例えば、「なぜそのようなことをしたの?」といったように、子どもに自分の行動について考えさせます。
疑問形をとっていますが、すでに親の中で答えがきまっており、当然子どももそうするべきだと親は期待しています。
強く反発をまねく叱り方

強い反発を招く叱り方は、次の2つです。
・子どもの人格に対する評価
・突き放し
このふたつは、どんなお子さんにとっても強い反発を招いた叱り方です。
子どもの人格に対する評価や突き放しは、その子の心に深い傷を残す可能性があります。子どもたちは自己価値やアイデンティティを形成する過程にあります。その過程で、大人や周囲の人々からの評価や承認は非常に重要です。
しかし、子どもたちが自分の人格や存在に対する否定的な評価を受けると、彼らの自尊心や自己肯定感が傷つきます。これによって、子どもたちは自分自身を受け入れることが難しくなり、不安や自己否定感が生じる可能性があります。
また、突き放しのような叱り方は、子どもが自分自身や自分の行動を否定されたように感じることがあります。これは子どもたちにとって非常にストレスフルであり、彼らが親や他の大人に対して反発する原因となります。子どもたちは支援や指導を求めているときに、無視されたり無関心な態度を取られることを感じると、自分が大人に理解されずに孤立していると感じるかもしれません。
したがって、子育てにおいては、子どもたちの人格や存在を尊重し、建設的なコミュニケーションを心がけることが重要です。叱る際には、その行動や選択に焦点を当て、彼らが改善できるように具体的な指導やサポートを提供することが効果的です。さらに、子どもたちが自分の気持ちや考えを表現できるように促し、彼らと共に解決策を考えることも重要です。こうしたアプローチによって、子どもたちは自己肯定感を高め、より健全な成長を遂げることができるでしょう。

この叱り方はオススメできません!!
反発を招きにくい、効果的な叱り方
逆に反発を招きにくい叱り方はどのようなものでしょうか?
・望ましくない理由を説明する
・感情表出
望ましくない理由を説明する叱り方では、子どもに対してなぜその行動が望ましくないのかを理解させることが重要です。親が論理的な理由や根拠を説明することで、子どもは自分の行動がなぜ問題であるかを理解しやすくなります。このようなアプローチは、子どもが納得しやすく、反発を招きにくいです。
感情表出は、親が子どもの行動に対して感情的な反応を示すことで、子どもは自分の行動が親にどのような影響を与えたかを理解しやすくなります。親が悲しい、がっかりしたといった感情をストレートに表現することで、子どもは自分の行動が親にとってどれほど重要であるかを理解しやすくなります。感情表出は、親子のコミュニケーションを深め、子どもが受け入れやすい叱り方の一つです。
子ども自身を叱るのではなく、その行為を叱る。どうして叱られるのかを理解することで反発を招きにくいようです。これら叱り方は、子どもが自分の行動に責任を持ち、自己評価を高めるのに役立ちます。また、親と子どもの信頼関係を損なうことなく、建設的なコミュニケーションを築くことができます。

ただし、親子関係によって、叱られた子供の受け取り方が変わってきますので注意が必要です。
親子関係において、親が自分のこと(子どものこと)を不満に思っていると感じている子どもは、叱られると、自分に対する不満をぶつけていると受け取ってしまい、感情表出の叱りであっても、その親の気持ちは素直に子供には通じないようです。
叱り方によって教師や親に抱く感情

叱り方によって子どもが抱く感情が変化する事が示唆されています。
叱り方が子どもの感情に与える影響は非常に重要です。厳しい叱り方や受け入れにくい叱り方をすると、子どもたちは不快な感情や否定的な評価を受けることになります。
これは、どんなに素晴らしい教育者であっても、子どもたちの学びや成長に悪影響を与える可能性があります。
さらに、厳しい叱り方を受けた子供たちは、逆に反省する気持ちが低下することが指摘されています。つまり、厳しい叱り方は本来の目的である子どもの反省や成長を促す効果を逆に阻害することがあります。
一方、子どもに受け入れやすい叱り方をすると、子どもは良い感情を抱く傾向があります。叱る際には、子どもの心情や感情を考慮し、建設的なアプローチを取ることが重要です。
また、叱る時間が長引くと、子どもたちの反省感情が低下する傾向があることも研究で示されています。そのため、叱り方は適切なタイミングや方法を考慮して行うことが必要です。
要するに、子どもの感情や心理状態を尊重し、叱り方を適切に行うことが重要です。子どもたちが安心感や理解を得られるようなアプローチを取ることで、より効果的な教育や子育てが行えるでしょう。

叱る時間は短く! あまりキツい言葉を使わないほうが、子どもたちにとっては効果的!
叩いてしつけは、逆効果どころか恐ろしい連鎖が生まれます。
「たたいて、しつける」「たたいて、叱る」

言語道断!絶対にしてはいけません!!
子どもの肉体的、精神的に傷つくことはもちろん、時には命をも危険にさらします。親だから許される…そんな言い訳は通用しません。
悪いことをした=暴力でわからせる
「悪いことをした=暴力でわからせる」という方程式が子どもの中で成立してしまうと、深刻な問題が生じます。この方程式が成立すると、子どもたちは暴力を正当化し、他者との関係を暴力や力で解決することを学んでしまいます。
例えば、学校で友達が悪いことをしたとき、自分の言うことを聞かないと感じた場合、暴力を用いることで問題を解決しようとする可能性が高くなります。親からの暴力を受けることが日常的であれば、子どもはそれを自然な行動として受け入れ、模倣する傾向があります。その結果、子どもたちは他者への尊重やコミュニケーション能力が欠如し、暴力的な行動を正当化する傾向が強まります。
このような状況は子どもたちの健全な発達に大きな障害を与えます。暴力は身体的・精神的な傷害を与えるだけでなく、社会的な問題や犯罪の温床となります。また、家庭内暴力やいじめなどの被害者は心の傷を抱え、その影響は長期間にわたって及びます。
したがって、親や教育者は暴力を叱咤するだけでなく、非暴力的な解決方法やコミュニケーションスキルの重要性を子どもたちに教える必要があります。子どもたちが適切な手段で問題を解決するための能力を身につけることが、彼らの健全な成長と社会的な安全を保障するために不可欠です。

暴力は、暴力を生みます。おそろしい連鎖が生まれるわけです。
まとめ
叱るという行為は、今後の子ども自身による適切な判断と行動変化を促すことに目的があります。つまり、叱りたい理由は「子どもの行動を変えたいから」ですよね。子どもたちに、その親の気持ちを伝え受け取ってもらいたいなら、叱り方も気を付ける必要があります。
私自身も、子育ての真っ最中です。子育てにおける叱り方や接し方は、子どもたちの成長と健やかな発達に大きな影響を与えますね。間違いを認め、子どもに対して謝ることは、大人としての責任と成長の機会でもあります。
そのような姿勢を示すことで、子どもたちも他者への思いやりや責任感を学びます。リセットし、新たなスタートを切ることは、子育ての過程で何度も必要なことですね。お互いに成長し合いながら、愛情と理解をもって子どもたちと向き合っていきましょう。

子育ては、いつだってやり直せます!!
お読みくださって、ありがとうございました。
引用文献
・松田君彦他:親の叱りことばの表現と子どもの受容過程に関する研究(1).鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編(54).pp187-pp203.2002
・竹内史宗:子どもは「叱り」をどのように感じているか.The Annual Report of Educational Psychology in Japan Vol.34.pp143-pp149.1995

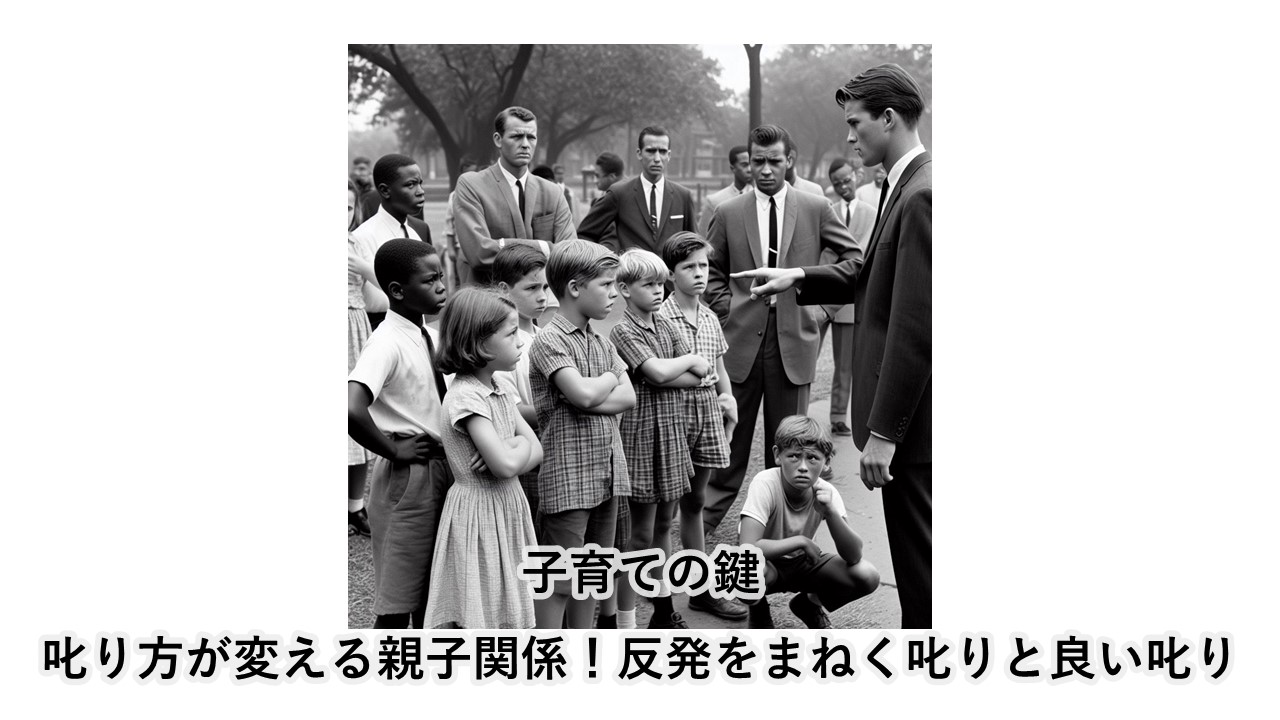


コメント